1:20mシャトルランの仕組みとスコアの理解
ビープ音とレベルの変化
シャトルランは「レベル制」で構成されており、レベルが上がるにつれてビープ音の間隔が短くなり、求められるスピードも速くなります。序盤は比較的ゆるやかなペースでも、後半はスプリントに近いスピードが要求され、心肺機能だけでなく下半身や体幹の持久力も重要になります。
「往復=1回」ではない
多くのケースでは、「20m走るごとに1点」としてスコアが加算されます。つまり、片道で1ポイント。ラインを踏んで折り返すのではなく、片道走るごとに1回分がカウントされる方式です。ビープ音に間に合わなくなった時点でテストは終了し、その直前の記録がスコアになります。学校によって若干の記録方法の違いはありますが、概ねこの方式が一般的です。
スコアは心肺能力の目安
このテストで高得点を取るには、持久力と効率的な動きの両方が求められます。無駄のないフォームやリズムを身につけることで、エネルギー消費を抑え、より長く走り続けられます。単なるスタミナ勝負ではなく、走るテクニックも重要なポイントです。
2:ウォーミングアップとクールダウンの役割

ウォーミングアップの目的
持久系の種目では、スタート前の準備運動がパフォーマンスに大きく影響します。ウォーミングアップの目的は次の通りです:
-
筋肉の柔軟性を高める:ダッシュを繰り返すため、事前に筋肉を温めることでケガのリスクを軽減。
-
心拍数と体温を徐々に上げる:急な負荷に対応しやすくなり、ビープ音のリズムにスムーズに乗れる。
-
集中力を高める:精神面でも準備を整え、本番への意識を高めることができる。
動的ストレッチと軽運動が効果的
テスト直前のストレッチには、動的ストレッチが適しています。ラジオ体操のようなリズミカルな動き、軽いジョギング、スキップ、サイドステップなどを取り入れることで、全身をしっかり温めることができます。これにより、神経系も活性化され、スタートダッシュもスムーズに行えるようになります。
クールダウンで疲労回復を促進
テスト後は、軽めのジョギングやウォーキングで徐々に心拍を落とし、静的ストレッチで筋肉をゆっくりと伸ばしましょう。乳酸の蓄積を防ぎ、筋肉痛の予防にもなります。しっかりとクールダウンを行うことで、次の練習やテストへのコンディションも整えやすくなります。
3:フォームとターン動作のコツ
効率的な走り方の基本
20mシャトルランでは、ただ速く走るだけではなく、正しいフォームで省エネに走ることがポイントです。
-
腕振り:リラックスした状態で、自然に前後へ振る。しっかり振ることで足の回転もスムーズに。
-
重心の位置:少し前足寄りに重心を置き、前傾しすぎないように姿勢を保つ。
-
呼吸:一定のリズムで呼吸することで、乳酸の蓄積を防ぎ、後半のバテを防止。
素早い方向転換のテクニック
ターン動作は、体力を無駄にしないためにも重要なポイントです。以下の点を意識してみましょう。
-
減速と準備:ライン直前で少し減速し、安定した足元で次の動作に備える。
-
コンパクトな動き:腕や身体の動きを大きくしすぎず、コンパクトにまとめて回転をスムーズに。
-
足のつき方:ラインぎりぎりを踏み、外側の足を軸にして素早く方向転換。ブレを最小限に抑える。
ターン動作は慣れが重要です。ターンだけを練習するドリルなども取り入れると、動きにキレが出てスコアアップにつながります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4:ペース配分と呼吸のリズムをマスターする
前半は“飛ばしすぎ”に要注意
20mシャトルランは、序盤こそゆっくりとしたペースで始まりますが、ここで油断して飛ばしすぎると、後半に失速しやすくなります。テストは後半にかけて急激にペースが上がっていく構成になっているため、前半は意識的に余裕を持った走りを心がけましょう。リラックスしたフォームでリズムを整えながら走ることで、レベルが上がった際にも無理なく対応できるようになります。
呼吸のリズムが持久力のカギ
後半に入るとテンポが速まり、自然と呼吸も乱れがちになります。そこで重要なのが、自分なりの呼吸リズムを確立することです。例えば「3歩で吸って3歩で吐く」など、動きに合わせて呼吸のタイミングを決めておくと、酸素の供給がスムーズになり、持久力も維持しやすくなります。
呼吸のテンポは「2拍子」でも「3拍子」でもOK。大切なのは、無理のない範囲で一定のリズムを保つこと。日頃の練習から取り入れて習慣化しておくと、本番での安定感が格段にアップします。
呼吸は心の安定にも直結する
呼吸が乱れると、体だけでなくメンタルも不安定になりやすくなります。焦りやパニックが動作のミスやリズムの乱れにつながることも。だからこそ、呼吸を意識的にコントロールすることが、心の落ち着きにも効果的です。苦しくなった時こそ、呼吸を整えることで集中力を保ち、粘り強く走り切れる状態を作ることができます。
5:日常でできる持久力アップのトレーニング

有酸素運動の基本は“長距離ラン”
20mシャトルランでスコアを伸ばすには、心肺機能の底上げが欠かせません。そのためには、週に2~3回程度の長距離ジョギングを取り入れるのがおすすめです。無理に長距離を走る必要はなく、最初は3〜5km程度からスタートし、自分のペースで続けましょう。
会話ができるくらいのペースで始め、慣れてきたら徐々にスピードを上げていくことで、効率的に持久力を強化できます。こうした基礎的なトレーニングが、シャトルラン後半での“粘り”につながります。
インターバルトレーニングで実戦力を強化
心肺にしっかり負荷をかけるなら、インターバルトレーニングが効果的です。これは「高強度の運動」と「低強度の休息」を交互に繰り返すトレーニング方法。シャトルランのような、繰り返し短距離を走る種目にはぴったりです。
例:
-
200m全力ダッシュ → 200mジョギング × 5セット
-
100m全力ダッシュ → 100mジョギング × 10セット
距離や回数は体力に合わせて調整しましょう。徐々に負荷を高めていくことで、**高強度運動に耐える“実戦力”**が身につきます。
階段・坂道ダッシュで心肺に刺激を!
もし環境が整っていれば、階段や坂道でのダッシュも取り入れてみましょう。平地よりも心肺や筋肉への負荷が大きく、シャトルランの後半のようなキツい場面でも粘る力が養えます。
ただし、勾配がきつすぎたり、足元が滑りやすい状況では無理をせず、安全第一で取り組んでください。
6:筋トレで走りの“効率化”を図る
下半身を重点的に鍛える
シャトルランにおけるパフォーマンスを左右するのが下半身の筋力です。特に大腿四頭筋、ハムストリングス、ふくらはぎ、股関節周りの筋肉を鍛えることで、スピード・安定性・持久力すべてが向上します。
-
スクワット:基本の筋トレ。重心がブレないように意識して行いましょう。
-
ランジ:前後に足を踏み出し、股関節の柔軟性も同時に鍛えられます。
体幹トレーニングでフォームを安定させる
方向転換が多いシャトルランでは、体幹の安定性も重要な要素。体幹が弱いと、走行中にバランスを崩したり、ターンで姿勢が崩れやすくなります。
-
プランク:30秒〜1分を目安に、背中を真っすぐキープ。
-
サイドプランク:体の側部を鍛えて、方向転換時の安定性を強化。
これらの筋トレを週に2〜3回程度取り入れることで、走りそのものが効率的かつ安定してきます。
7:集中力とメンタルを鍛えて限界を超える
小さなゴールを設定しよう
後半になるほどつらくなるシャトルランでは、明確な目標設定がメンタル維持に効果的です。いきなり高い目標を掲げるのではなく、
-
「前回より+1回」
-
「レベル○○まで粘る」
といった段階的な目標を立てることで、継続的なやる気を保ちやすくなります。
ポジティブな自己対話を習慣に
しんどくなったときは、心の中で前向きな声かけをしましょう。
-
「あと1本いける!」
-
「ここを乗り越えれば成長できる!」
といったポジティブなセルフトークは、集中力の維持とパフォーマンスの向上に直結します。あらかじめ自分の“励ましワード”をいくつか用意しておくと、本番で実践しやすくなります。
イメージトレーニングで自信を育てる
競技前に自分が理想的に走っている姿をイメージするのも、効果的なメンタルトレーニングです。フォーム、呼吸、ターン、スコアアップなど、できるだけリアルに想像してみましょう。
この“成功体験の先取り”によって、自信と集中力が高まり、本番で力を発揮しやすくなります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8:練習スケジュールの立て方と疲労コントロールのコツ
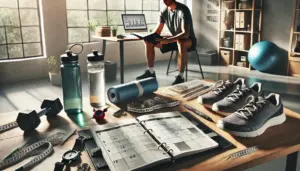
無理なく継続できる練習計画を
高校生は勉強、部活動、そして日々の生活と忙しい毎日を送っています。そこにトレーニングを加えるとなると、疲労の蓄積に注意しなければなりません。以下のポイントを意識して、体に無理のないスケジュールを組みましょう。
-
週に1〜2日は完全休養を入れる:特にテスト期間や試合前は、しっかり休むことで体と心のリセットが図れます。
-
高強度・低強度の練習を交互に配置:インターバルトレーニングなど負荷の高い翌日は、軽いジョグやストレッチ中心の“リカバリーデー”を設けるのがおすすめです。
-
学校や部活と連動した計画を:体育の授業や部活で負荷の高い運動をした日は、自主練を軽めにするなど、柔軟な対応がパフォーマンス維持につながります。
睡眠と食事でパフォーマンスを底上げ
日々の練習効果を最大限に引き出すには、睡眠と栄養の質がカギになります。特にスマホやゲームなどの影響で睡眠時間が削られがちな現代では、「眠りの質」が非常に重要です。
また、食事ではタンパク質・炭水化物・ビタミン類をバランスよく摂取することが必要不可欠です。
-
肉・魚・卵・豆類:筋肉の回復と成長に
-
ご飯・パン・パスタ:エネルギー源として重要
-
野菜・果物:ビタミン・ミネラルの補給に
偏った食生活や無理なダイエットは逆効果。健康的な体づくりが、シャトルランのスコアアップに直結します。
9:飽きずに続けるための練習バリエーション
マンネリを防ぐ“変化のある練習”
20mシャトルランそのものを練習メニューに取り入れるのは効果的ですが、毎回同じやり方だと飽きがきてしまいます。集中力が切れてしまうと、トレーニング効果も半減してしまいます。
そこで、以下のような工夫を取り入れてみましょう。
-
距離や音を変えてみる:10mや15mシャトルランなど、短距離でターンの回数を増やすことで敏捷性がアップ。
-
心拍数ベースで区切る:心拍数が一定値に達したら休憩を入れ、インターバル形式で強度を調整。
-
ペア練・チーム戦にする:友達と一緒に競いながら練習すると、モチベーションが自然と上がります。
クロス・トレーニングで体への刺激を変える
同じ部位ばかりを使い続けると、ケガや疲労のリスクも高まります。そこで、走る以外の運動を取り入れる「クロス・トレーニング」が効果的です。
例:
-
水泳:全身を使いながら関節への負担が少ない
-
自転車:下半身強化と心肺向上を同時に狙える
-
なわとび・球技:楽しく運動能力を底上げ
こうした“変化のある刺激”が、長期的な成長を後押しします。
10:模擬テストと振り返りで成長を加速させる
模擬テストで自分の伸びを可視化
努力を結果につなげるには、定期的な模擬テストで成長を確認することが大切です。練習の手応えだけでなく、実際のスコアや感覚を記録することで、自信や改善点が明確になります。
-
頻度の目安:1〜2ヶ月に1回
-
記録項目:レベル到達点、苦しくなったタイミング、呼吸やフォームの感覚
動画で“自分の走り”を客観視しよう
可能であれば、模擬テスト中の自分の走りを動画で撮影してみましょう。自分では気づけなかったフォームの癖やターンのミスが可視化でき、修正ポイントが一目で分かるようになります。
-
腕振りが小さい・左右差がある
-
ターンでバランスを崩している
-
視線や姿勢が安定していない
こうした細かい動きを把握することで、次の練習へのフィードバックがより的確になります。
振り返り→修正→再チャレンジの流れが重要
模擬テストの後は、「どこができたか・できなかったか」を整理し、次回に向けた修正点を具体化しましょう。たとえば、
-
レベル10から急に苦しくなった → レベル9〜11の強度を想定したインターバル練習を追加
-
ターンで遅れていた → ターン練習を増やしてフォームを改善
このように、**PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)**を回していくことが、効率よくスコアアップにつながる鍵となります。
おわりに:積み重ねが結果をつくる
ここまで、20mシャトルランのスコアを伸ばすための様々な戦略を紹介してきました。大切なのは、地道な努力を続けることです。日々のトレーニング、生活習慣の見直し、メンタルのコントロール――それらをコツコツと積み重ねることで、確実に結果はついてきます。
また、一人で続けるのが難しいと感じたら、仲間と一緒に励まし合いながら練習するのも良い方法です。シャトルランは終わりが見えるテストです。ビープ音が止まるその瞬間まで、自分を信じて走り切ってみてください。
紹介したテクニックや練習法を参考に、無理なく安全に、そして前向きに取り組んでいきましょう。あなたの努力は、必ず「自己ベスト更新」というカタチで報われるはずです。数字で成長を実感できるこのテストで、自信と達成感を手に入れてください!


