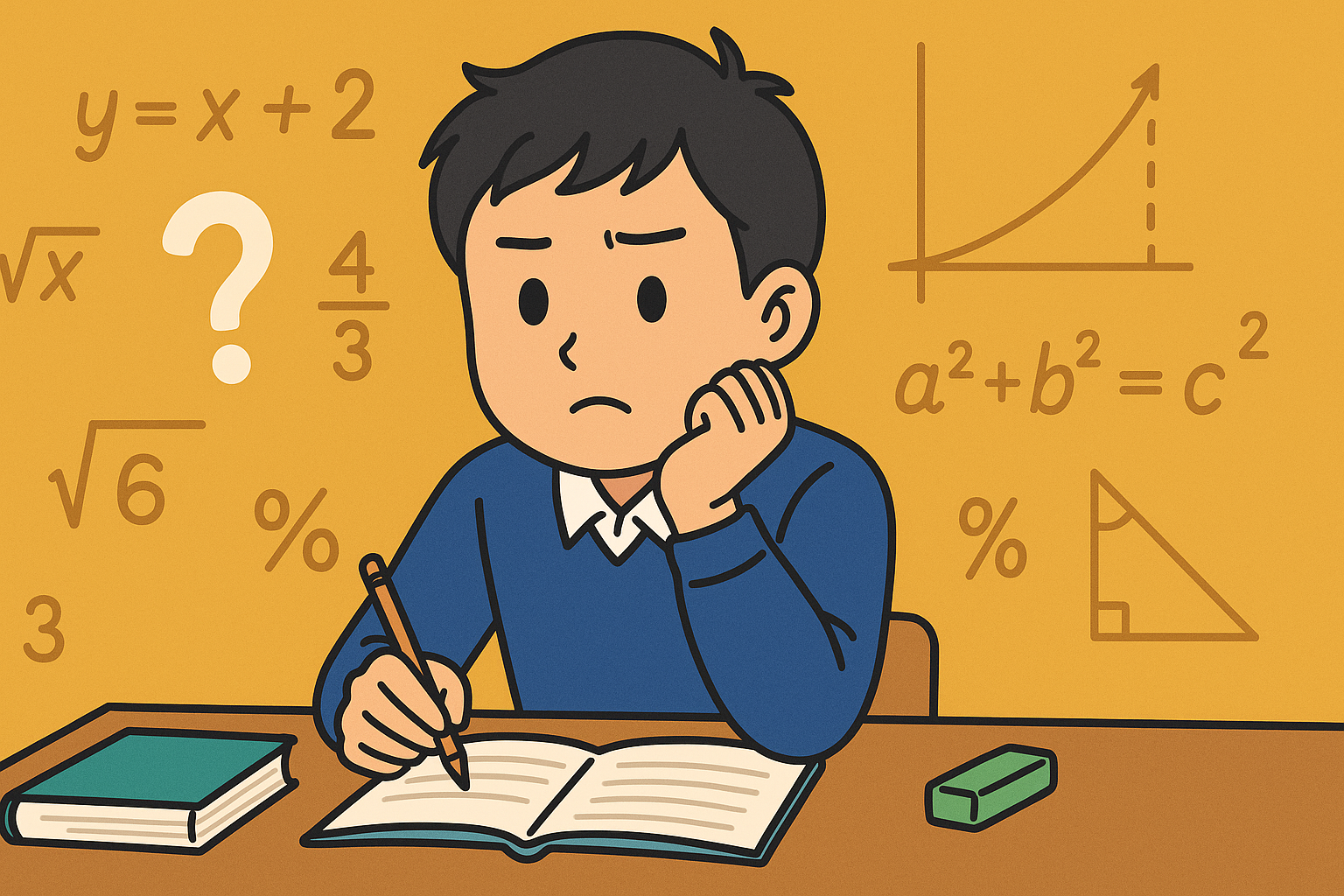はじめに
「数学が苦手…」「テストの点数がいつも低くて自信がない…」そんな風に感じている中学生のみなさん、安心してください!この記事では、数学が苦手な人でも楽しく、着実に克服できる5つのステップを紹介します。筆者自身も中学時代、数学に大苦戦していましたが、ここで紹介する方法を試すことで、苦手意識を克服し、最終的には得意科目に変えることができました。
実は、数学が苦手な人の多くは、やり方を知らないだけなのです。正しい方法を知れば、「あれ?意外とできるかも?」という感覚が芽生えてきます。私自身も、最初は公式の意味すらわからず、授業中に先生の話を聞いても「???」となることが多かったです。でも、ちょっとした工夫や習慣を変えることで、テストの点数がぐんと上がり、自信もつきました。
この記事を読むことで、
- 数学に対する考え方が変わる
- 具体的な勉強法がわかる
- 自分に合った学習スタイルが見つかる
- どうすれば苦手を乗り越えられるかが明確になる
などの効果が期待できます。また、実践しやすいコツやアイデアも盛りだくさんなので、「今日からやってみよう!」と思える内容になっています。
**ぜひ最後まで読んで、自分に合うステップを見つけてみてください。**数学が楽しくなる瞬間は、もうすぐそこです!
ステップ1:苦手な理由を明確にしよう
なぜ数学が苦手なのか、考えたことはある?
まずは自分がなぜ数学が苦手だと感じているのかを知ることが第一歩です。漠然と「数学は難しいから嫌い」と思っている人も多いですが、実は苦手意識の正体はもっと具体的なところにあることがほとんどです。
よくある理由としては:
- 計算ミスが多い
- 問題の意味がわからない
- 公式が覚えられない
- 勉強のやり方がわからない
- 問題を見るだけで嫌な気持ちになる
- 自信がなくて最初からあきらめてしまう
**どれか1つでも当てはまる人は、それが克服のヒントになります!**苦手な理由をしっかりと把握すれば、闇雲に勉強するのではなく、「何をどうすればいいか」が明確になります。
たとえば、「計算ミスが多い」と気づいたら、注意力を鍛える練習や見直しの時間を確保することが対策になりますし、「問題の意味がわからない」という人は、国語力や読解力を少し意識して鍛えることが近道です。
自分の「つまずきポイント」を見つけよう
おすすめなのは、最近のテストやワークの見直しです。どの問題でつまずいているかを見つけるだけでも、成績アップの大きな手がかりになります。
- 間違えた問題をチェック
- 同じパターンでミスしていないか確認
- 解説を読んで、理解できるか試す
- 自分の理解度を3段階(◎〇△)で評価してみる
- 「なぜ間違えたのか?」をメモしておく
さらに、「解説を読んでも理解できない」ときは、それがまさに“つまずきポイント”です。そこに時間をかけてじっくり向き合うことで、全体の理解度がぐんとアップします。
**原因がわかれば、対策が立てやすくなります。**そしてその対策は、あなた専用の攻略法になります。
ステップ2:目標を設定してモチベーションを上げよう

具体的な目標がやる気のカギ!
「数学ができるようになりたい」と思っていても、目標があいまいだと行動に移しにくいですよね。そこで大切なのが、具体的な目標を立てることです。
例えば:
- 次のテストで70点以上を取る
- 毎日15分は数学を勉強する
- 図形問題だけは完璧にする
このように、**数値や範囲がはっきりしている目標がベスト!**目標が明確であればあるほど、「何をすればいいか」がわかりやすくなり、行動につながりやすくなります。
また、目標には「短期目標」と「中・長期目標」の2つを設定するのが効果的です。
例:
- 【短期】今週中に方程式の基礎問題を10問解く
- 【中期】次の定期テストで平均点以上を目指す
- 【長期】中3までに数学を得意科目にする!
このように時間軸で分けることで、毎日の行動にも意味が出てきて、勉強のモチベーションが長続きします。
小さな達成を積み重ねよう
大きな目標をいきなり達成するのは難しいので、小さなゴールをいくつも設定して成功体験を増やすことが大事です。
- 1日1問解けるようにする
- 1週間で公式を3つ覚える
- 3日間続けて勉強できたらカレンダーにチェックを入れる
- 勉強後に「今日のひとこと感想」を書く
こうした工夫を積み重ねていくと、「自分ってけっこうやれるかも!」という自信とやる気が自然にわいてきます。
小さな成功が、大きな自信に変わる。これがモチベーションアップの秘訣です!
ステップ3:基本を徹底的にマスターしよう
応用よりも、まずは基礎!
数学が苦手な人ほど、応用問題に苦しみがちです。だけど、それは基礎がしっかりしていないからかもしれません。どんなに難しい問題でも、土台となる基礎ができていないと、うまく対応できません。
たとえば、連立方程式が苦手な場合も、実は「移項」や「計算の順序」があいまいなまま進めてしまっていることが原因だったりします。つまり、応用問題が解けないのは才能ではなく、基礎の積み重ねが足りていないだけなんです。
こんな勉強法がおすすめ
- 小学校の計算ドリルを復習する
- 教科書の例題をノートに写して解く
- 計算練習を毎日少しずつやる
- 1日1ページだけでもドリルに取り組む
- 基礎問題だけの問題集を1冊やり切る
**「簡単すぎる」と思っても、基礎こそが数学の土台です!**サッカー選手が毎日リフティングをするように、数学でも基本的な動作を何度も繰り返すことで、自然と力がついていきます。
解き方のプロセスを理解しよう
答えを出すことだけに集中するのではなく、どんな考え方でその答えにたどりついたかを意識することが大切です。数学は「答えが合っていればOK」ではなく、「正しく理解しているかどうか」が重要なんです。
- なぜその公式を使うのか
- どうしてその順番で解くのか
- 似た問題と何が違うのか
- 他の方法でも解けるのか
こうしたプロセスに注目することで、応用問題にも対応できる柔軟な思考力が身につきます。わからなかったら、「この問題はどんな公式を使うんだろう?」「どの情報が大事なんだろう?」と自分に質問してみましょう。
基礎をしっかり固めることが、苦手克服の一番の近道です!
ステップ4:苦手な単元は「見える化」しよう
苦手なところを可視化して整理
「なんとなく苦手」では対策ができません。自分がどこでつまずいているのか、曖昧なままでは正しい勉強法を選ぶこともできません。だからこそ、まずは自分の苦手な単元をはっきりと見える形にして整理することが大切です。
このステップでは、苦手な部分を洗い出し、それに対してどんなアプローチが必要かを見極める準備をします。
チェックリストを作ってみよう
| 単元 | 得意・ふつう・苦手 |
|---|---|
| 正負の数 | 苦手 |
| 方程式 | ふつう |
| 図形の証明 | 苦手 |
| 関数 | 得意 |
| 資料の整理 | ふつう |
| 確率 | 苦手 |
このように、単元ごとに自己評価するだけでも、対策すべきポイントがはっきりします! さらに、色分けや星マークなどを使って視覚的に整理すれば、勉強の計画も立てやすくなります。たとえば「★=要重点対策」などのマークを加えるのも効果的です。
また、苦手の度合いを「1〜5」のレベルで数字で表す方法もおすすめです。自分の感覚を数字に置き換えることで、少しずつ改善している実感を得られやすくなります。
苦手な単元は「分割して学ぶ」
例えば「図形が苦手」でも、一つ一つの内容に分けてみると、実はそこまで難しくない場合が多いんです。漠然と「全部苦手」と思っていたものが、「これは理解できる」「ここだけが苦手」と分類できるようになります。
- 三角形の性質
- 円の面積
- 角度の計算
- 作図のやり方
- 図形の証明文の書き方
などに分けて考えると、一つ一つはそこまで難しくないと気づけます。それに気づくだけでも、「これなら自分でもできるかも!」という前向きな気持ちになれるはずです。
さらに、分割した内容ごとに目標を設定すれば、勉強の進め方もより具体的になります。
- 今週は三角形だけに集中する
- 次は角度の計算を5問ずつ解いてみる
- 証明は毎日1題、ノートにまとめてみる
というように、「小さなテーマ」に分けることで、無理なく継続的に取り組めるようになります。
ステップ5:質問できる環境をつくろう
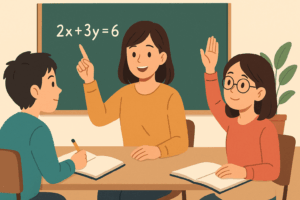
一人で悩まないで!
「わからないけど、誰にも聞けない…」と感じたこと、ありませんか?実はこの「聞けない」というのが、苦手をそのままにしてしまう一番の原因です。恥ずかしい、怒られるかもしれない、変に思われたらどうしよう…そんな気持ちはとてもよくわかります。
でも、数学は“理解”が命! わからないことをそのままにしてしまうと、どんどんつまずきが広がってしまいます。反対に、早めに質問して解決すれば、スムーズに次に進めることができます。
質問することは「恥ずかしい」ことではなく、**「できるようになるための一歩」**なんです!
こんな方法があります
- 先生に積極的に質問する(放課後や休み時間を活用)
- 友達と勉強会をする(自分が教える側になると理解が深まることも)
- YouTubeや学習アプリを使う(いつでも見直せて便利)
- 家族に聞いてみる(おうちの人も案外覚えているかも?)
- SNSで中学生向け学習コミュニティを探す
**自分に合ったやり方で、疑問をその場で解決することが大切です。**とくに今は、ネットで無料で解説動画が見られる時代。うまく活用すれば、先生がすぐそばにいるような感覚で学習できます。
「わからない」と言える勇気が、成長の第一歩です!
ステップ6:ミスのパターンを分析しよう
同じ間違いを繰り返していない?
「またこの問題でミスした…」そんな経験、ありますよね?
実は、多くの人が同じようなミスを何度も繰り返しています。それは、自分のミスの原因をしっかり分析できていないからなんです。「わかっていたはずなのに…」という悔しさをなくすためにも、ミスの傾向を把握して、同じ失敗を繰り返さない工夫が必要です。
ミスの原因を探ると:
- 計算ミス(符号の間違い、小数点のずれなど)
- 問題文の読み違い(条件の見落としや勘違い)
- 時間配分ミス(後半で焦って間違える)
- 解き方を忘れてしまっている
- 手順を飛ばして解こうとしてミスする
このような原因は、意識するだけでも減らせることが多いのです。大事なのは、「自分はどこで間違えやすいか」を知ること。
対策方法
- 間違えた問題を「ミスノート」に記録する(ノートを1冊用意)
- なぜミスしたのかを一言でまとめる(例:「急いで+−を逆にした」)
- 同じミスを防ぐための注意ポイントを赤ペンで書く
- 定期的にミスノートを見直す(テスト前には必ずチェック)
- 間違えた問題を“類題”で再チャレンジする
このように、ミスの履歴を「見える化」することで、自分だけの改善ポイントが明確になります。 そして、それは「次こそできる!」という自信にもつながります。
「ミスは成長のチャンス」と考えて、前向きに活かしていこう!
ステップ7:ゲーム感覚で楽しもう
勉強=つまらない? それは違う!
数学の勉強が「作業」になると、つまらなく感じがち。特に問題集を黙々と解いていると、「いつまでこれを続けるの?」とやる気がなくなってしまうこともあります。
でも実は、ゲーム感覚で楽しむ方法もあります! 勉強を「遊び」のように工夫することで、自然とやる気も集中力もアップするんです。
楽しみながら取り組むアイデア
例:
- タイムアタックで計算練習(ストップウォッチで記録)
- 問題をレベル別に分けて攻略(レベル1→レベル5までボス戦形式で)
- 勉強した分だけシールやポイントを貯める(目標達成でご褒美も!)
- クイズ形式で家族と勝負する
- オリジナルの「計算カードゲーム」を作ってみる
「今日は昨日より1分早く解けた!」というような達成感を味わえると、勉強がもっと楽しくなります。 成績が上がることだけを目標にするのではなく、「自分との勝負」にしてしまうと、自然と夢中になれます。
また、友達と一緒に競い合うのもモチベーションアップに効果的。「○○分で何問解けるか勝負しよう!」というような簡単なゲームでも、意外と燃えるものです。
勉強も工夫次第で“遊び”になる!まずは1つ、楽しみ方を取り入れてみよう!
ステップ8:反復練習で知識を定着させよう
一度解けた=理解できた、ではない!
「一回やってみたらできたから大丈夫!」と思っても、時間がたつと忘れてしまうのが普通です。特に数学は、公式や手順を覚えただけではなく、繰り返し解いて身体にしみ込ませることが大切です。人間の脳は、忘れるようにできているからこそ、「覚え直す」ための習慣が必要なんです。
「自分、前にもこの問題間違えたな…」と感じたことがあるなら、それは反復が足りていない証拠。だからこそ、復習のタイミングと方法がとても重要です。
だからこそ、復習が超重要!
- 1日後、3日後、1週間後に同じ問題を解く(エビングハウスの忘却曲線に基づいた復習)
- 解けなかったら再チェック!(ノートに印をつけておこう)
- 問題を変えて同じ考え方を試す(形式を変えて理解を確認)
- 自分の苦手なパターンだけを集めた「弱点プリント」を作る
- 一度解いた問題をシャッフルして再挑戦
また、復習のときに「なんで間違えたのか」を振り返ることで、記憶がより深く定着します。ただ正解を見るのではなく、解き直すことが大切なんです。
記憶は繰り返しで強くなる。反復は、苦手克服の最強の味方です!
ステップ9:教材選びもポイント!
自分に合った教材を使ってる?
勉強に使う教材は、思っている以上に重要です。難しすぎたり、逆に簡単すぎる教材ではやる気が続きませんし、理解も深まりません。だからこそ、自分に合った教材を選ぶことが、効率的な学習のカギとなります。
「この教材は自分にとってちょうど良い難しさか?」を意識することで、自然と集中力も高まり、継続しやすくなります。
教材選びのコツ
- 学校の教科書・ワークを中心に(まずは授業内容の定着を最優先)
- 解説が丁寧な問題集を選ぶ(図解や手順がしっかりしているもの)
- 自分のレベルに合ったものを選ぶ(無理に難問に挑まない)
- 苦手な単元に特化した参考書も活用する(図形だけ、関数だけなど)
また、教材は紙だけに限りません。最近はYouTubeやアプリも充実しており、動画や音声で学ぶスタイルも効果的です。自分の理解スタイルに合うものを組み合わせると、さらに効果的な学習ができます。
おすすめの併用スタイル
- アニメーションで解説してくれる動画(動きがあると理解しやすい)
- ゲーム感覚で学べるアプリ(計算ドリルやクイズ形式など)
- 解いた問題をアプリで記録し、成長を可視化
これらのツールをうまく活用すれば、飽きずに勉強を続けられるようになります。
「自分に合った教材」は、最強の先生!迷ったら、まずは使ってみて比べてみよう!
ステップ10:毎日の習慣にすることが成功のカギ
継続は力なり!
一気にがんばるより、毎日少しずつ続けることが大切です。最初は5分でもOK。「今日は少しだけでもやった」という積み重ねが、やがて大きな成果につながります。習慣になると、「今日はサボりたいな…」という日でも、自然と手が動くようになるんです。
習慣にしてしまえば、やる気に頼らなくても行動できるようになるのがポイント。つまり、努力しなくても毎日勉強できる自分になれるということです!
続けるコツ
- 勉強時間を決めて習慣化する(例:夕食後の15分)
- 終わったらご褒美を設定する(小さなチョコやゲーム時間など)
- できたことを記録する(スタンプ、カレンダー、アプリなど)
- 「できた日」を見える化して達成感を感じる(100日チャレンジなど)
- 勉強場所や時間を固定することで習慣化が加速する
また、モチベーションが下がったときには、無理に頑張ろうとせず、「軽くやる」ことを意識すると続きやすくなります。たとえば、**「今日はノートを見るだけ」「問題を1問だけ解く」**といったライトな内容でもOK。
**「勉強しなきゃ…」より「今日もやったぞ!」という気持ちが成功への近道です。**自分のペースで、無理なく続けていきましょう!
まとめ:今日から始めよう!数学克服の第一歩
数学が苦手でも、正しいステップを踏めば必ず克服できます! どんなに苦手意識が強くても、「できない」から「ちょっとできる」へ、そして「得意かも!」へと変わる道筋は必ずあります。
ここで紹介した10のステップは、どれも特別な才能が必要なわけではありません。大切なのは、
- 自分に合った方法を見つけること
- 小さな成功体験を積み重ねること
- 続けること
- 諦めないこと
- わからないことを恥ずかしがらないこと
数学が得意になるために、いきなり難しいことに挑戦する必要はありません。「今の自分にできることをやる」ことが、一番の近道です。
今この記事を読み終えたあなたは、もう第一歩を踏み出しています! 読みながら「ちょっとやってみようかな」と思えた時点で、あなたの中に変化が始まっています。
明日からではなく、**今日から1つでもステップを実践してみましょう。**ノートを開いてみる、1問だけ解いてみる、それだけでも立派な進歩です。きっと少しずつ、「できる!」という感覚が育っていきますよ。
あなたにも数学が得意になる未来が待っています!焦らず、一歩ずつ前へ。がんばってね!