第1章:はじめに
生徒会選挙の演説は、自分の魅力やビジョンを伝える大切な舞台であると同時に、聴衆である生徒や先生方に印象を残す絶好のチャンスです。多くの演説は真面目で堅い雰囲気になりがちですが、あまりに形式的すぎると、聞き手の集中力が途切れてしまうことも…。
そこでおすすめなのが、少しだけユーモアを交える工夫。ほんの一言でも笑いを取れれば、あなたの人柄やセンスが伝わり、「親しみやすい人」「面白そうな人」という好印象につながるのです。
とはいえ、「ギャグを入れたほうが良い」とわかっていても、
-
「滑ったらどうしよう…」
-
「ネタが学校の雰囲気に合っているか不安…」
と悩んでしまい、結局無難な演説に落ち着いてしまう…という声もよく聞きます。でも、それではせっかくの個性を発揮するチャンスがもったいないですよね。
本記事では、
-
生徒会演説に使えるユニークなギャグ例
-
自然に笑いを誘うコツ
-
ギャグを使う際の注意点
をわかりやすく解説しています。
💡 ポイントは、誰も傷つけず、自然と笑える“やさしいユーモア”を意識すること。
ぜひ最後まで読んでいただき、気に入ったネタがあれば、あなたの演説に活かしてみてください!
第2章:なぜギャグが有効なのか?
2-1:アイスブレイクの効果
長い演説の場では、どうしても緊張感や退屈さが漂いがち。そこで軽いギャグを一つ入れるだけで、その場の空気がガラリと変わります。
🎤 笑いには、「話を聞いてもらえる空気」を作る力があるのです。
心理学的にも、笑いは聴衆の緊張を和らげ、話し手に対する好意や興味を引き出す効果があります。
2-2:印象に残り、記憶される
演説では「学校を良くする」「イベントを盛り上げる」「部活動を支援する」など、よくあるテーマが並びがち。その中でギャグを取り入れることで、あなたの個性を際立たせることができます。
🤔「そういえば、あの演説で笑ったな」<br>→ それが記憶に残る大きな武器になります。
2-3:距離感を縮められる
生徒会役員はリーダー的存在として少し遠い存在に思われがち。でも、ユーモアがある人には自然と親しみを感じるもの。
💬 「この人、話しかけやすそう」<br>→ そんな印象を与えられれば、投票にも好影響を与えるかもしれません。
第3章:生徒会演説で使えるギャグのパターン
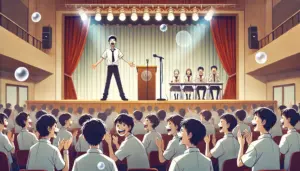
3-1:自己紹介でのギャグ
演説の冒頭、自己紹介の場面は聴衆が一番集中しているタイミング。ここでサラッと笑いを取ると、「面白い人かも?」と一気に興味を引くことができます。
🎯使えるネタ例:
-
名前を使ったダジャレ
-
名前の由来にまつわるエピソード
-
有名人やキャラクターとの関連付け
例1:
「私の名字は“加藤”。“加える藤”と書いて加藤ですが、加藤浩次さんとは関係ありません。でも、勢いだけは負けていないつもりです!」
例2:
「田中と申します。皆さん、“田中”と聞いて思い浮かぶ有名人は誰ですか?<br>僕は、田中将大選手のように、逆転ホームランならぬ“逆転アイデア”を放っていきたいと思っています!」
3-2:学校ネタを活かしたギャグ
学校生活に関するネタは、全員が共感できる鉄板テーマです。校則や先生方、学校の設備など、日常の中に笑いのヒントがたくさんあります。
⚠️ ただし、先生や校則をネタにする場合は、あくまで“愛あるツッコミ”に留めましょう。
例1:
「うちの学校では“制服のボタンは全部留める”のが校則ですよね?<br>でも僕は、女子からも“心のボタン”を留めっぱなしにされている気がします…。<br>今年こそは、皆さんと心のボタンを外し合える1年にしたいです!<br>もちろん、校則はしっかり守ります!」
例2:
「うちの食堂、カレーが人気すぎてすぐ売り切れますよね?<br>僕のテンションまで、辛口になってしまいます!<br>来年は“カレー確保対策”にも力を入れたいと思います!(本気です)」
3-3:流行ネタやSNS文化を取り入れたギャグ
TikTokや流行語、人気店など、SNSやニュースで話題のネタを取り入れると、「今どき感」や親近感が出ます。
🧠 ただし、あまりにマニアックなネタは避け、みんなが知っている話題を選びましょう。
例1:
「最近はTikTokで“バズる”のが流行ってますが、僕も**“バズる公約”**を用意しました!<br>ただし、バズるには皆さんの“いいね!”が必要です。一緒に盛り上げてください!」
例2:
「学校の近くに新しいタピオカ屋さんができましたね!<br>私も飲みましたが、これからの学校生活、“タピる”くらい楽しんでいけたら最高ですよね!」
第4章:ギャグを使うときの心得
4-1:笑いは「共有」するもの
ギャグで大切なのは、「一緒に笑う空気」をつくることです。誰かをネタにして笑いを取るのではなく、みんなでクスッと笑える内容を心がけましょう。
⚠️ 特定の個人やグループをバカにするようなネタは絶対NG。
特に先生やクラスメイトを揶揄するのは、高リスクです。
たとえ笑いが起きても、誰かを傷つける内容なら逆効果。票を失うだけでなく、信頼も失いかねません。
4-2:万が一スベったら?
準備万端のギャグでも、受けないことはあります。
そんな時に焦ると、場の空気がさらに凍りつく可能性も…。
💡 おすすめの切り返し方:
-
「……今の、笑うところですよ?」(軽い自虐)
-
「いや~、皆さんレベル高すぎますね(笑)」(聴衆へのリスペクト)
-
「あれ、緊張しすぎて噛んだかな?」(ボケの上書き)
失敗を笑いに変える柔軟さが、逆に好印象になることも。
一つのギャグがスベったからといって、演説全体がダメになるわけではありません。心構えを持っておくことが何より大切です。
4-3:ギャグ“だけ”にならないように
演説の目的は、「自分の考えや公約を伝えること」。
笑いだけを狙って公約が頭に入らなければ、本末転倒です。
🎤 ギャグはあくまでスパイス。<br>メインディッシュはあなたの誠実さとビジョンです。
ウケ狙いに走りすぎると、「結局この人、何をしたいのか分からなかった」という印象で終わるリスクも。
内容と笑いのバランス感覚が、選ばれる鍵です。
第5章:すぐ使える!演説ギャグ例
5-1:短くテンポ良く決める
演説ではサクッと伝わるギャグが効果的。長いダジャレや凝ったコントは、場が冷めてしまうことも…。
例1:
「今日が人生初の“立候補”。でも当選しても“立往生”しないように頑張ります!」
例2:
「この学校の未来を、僕と一緒に“ミラ(見ら)い”ましょう!……今のは聞かなかったことにしてもらえますか?」
5-2:軽い自虐ネタで親近感アップ
少しだけ自分をいじることで、柔らかい印象を与えられます。
ただし、自信のなさがにじみ出るような過度な自虐はNG!
例1:
「僕、朝がすごく苦手なんです。でも生徒会長になったら、“遅刻しない仕組み”を作ります! 皆さん、僕を支えてください!」
例2:
「私、掃除当番をよく忘れるタイプで…。でも、忘れ物は学校だけにして、忘れられない企画を実現させます!」
5-3:先生への感謝+ユーモア
先生方への敬意を忘れずに、笑いを添えると場が和やかになります。
例1:
「先生方、いつもありがとうございます!<br>宿題がちょっと多すぎるのはご愛嬌として、効率よく学べる方法を一緒に考えたいです!」
例2:
「先生たちから『最近の若者は…』って言われますけど、私たちも『最近の先生は元気すぎる!』って思ってます(笑)<br>お互いを知るために、生徒と先生の交流イベントを増やしたいです!」
5-4:投票呼びかけにも一工夫
ラストの「投票お願いします」も、一味違った表現で印象づけましょう。
例1:
「僕を選んで後悔はさせません!なぜなら、後悔する前に全力で結果を出すからです!<br>ぜひ、その一票で僕を試してみませんか?」
例2:
「私に投票すれば、明日の学校がちょっと変わるかも。<br>まだ“未知数”? だからこそ面白いんです。<br>無限大の可能性、一緒に方程式を解いてみませんか?」
第6章:ギャグを入れるタイミングと工夫

6-1:前半・後半に一度ずつ
演説の構成としては、
-
自己紹介
-
公約説明
-
まとめ
-
投票呼びかけ
が王道。その中で、
-
最初の自己紹介
-
最後の締めの一言
この2カ所にギャグを入れると、最初と最後に好印象を残すことができます。
6-2:本題中にも小ネタを
真面目な話が続く中でも、軽い笑いを挟むと聴衆の集中力が保たれます。
例:購買部の売り切れ問題について
「あのメロンパン、買えた人は勝ち組ですよね。<br>僕なんて、毎日“メロンパンウォーズ”に敗北してます(笑)」
真剣さの中にユーモアを交えることで、話に緩急が生まれ、聞き手も飽きにくくなります。
6-3:その場の空気を読む
いくら完璧に用意したギャグでも、
-
会場がシリアスな雰囲気
-
時間が押している
-
直前の演説で似たネタが使われた
など、予定通りにいかない場面はよくあります。
そんな時は、ギャグを飛ばす・縮める・別の案に切り替えるなど、柔軟に対応できる判断力が問われます。
第7章:練習と準備の重要性
7-1:声に出してリズムを確認
ギャグは**「言い方」と「間」が命。**
原稿では面白く見えても、読み上げるとイマイチ…ということはよくあります。
-
鏡の前で練習する
-
実際に声に出してタイミングを測る
-
間の取り方をシミュレーション
など、本番を想定した練習を重ねましょう。
7-2:第三者の意見を聞く
自分で「これはウケる!」と思っても、他人の反応は違うこともあります。
-
友人
-
家族
-
先生
など、複数の人に演説を聞いてもらい、率直なフィードバックを得ることで、完成度がグッと高まります。
7-3:代替パターンを準備しておく
本番で以下のようなトラブルがあるかもしれません:
-
似たネタを他の候補者が使ってしまった
-
マイクの不調で一部聞こえなかった
-
突然の時間短縮で全体を削る必要が出た
💡 だからこそ、複数のギャグや話し方を準備しておくことが大切です。
状況に応じて柔軟に切り替えられる準備力が、成功のカギを握ります。
第8章:ギャグ以外でも笑いは取れる!
8-1:表情とジェスチャーで勝負!
言葉の力も大切ですが、表情や身振り手振りでも笑いは生まれます。微笑んだり、ほんの少しオーバーな動きを入れたりするだけで、場が和みやすくなるものです。
😄 たとえば、「驚いた!」という場面で目を見開いて肩をすくめる…だけでも笑いを誘うことがあります。
ただし、やりすぎるとおふざけ感が強くなってしまうので注意。ユーモアの演出は「少し足りないくらい」がちょうどいいのです。
8-2:軽いパフォーマンスで印象付ける
ダンスやリズムネタが得意な人は、演説の最後に少しだけ披露してみるのも◎。
たとえば:
-
手拍子しながら話す
-
ボディパーカッションを数秒入れる
-
ダンスの「決めポーズ」だけ入れる
ただし、本番で練習不足だと空気が凍るリスクも…。準備と空気の読み方がカギです。
8-3:小道具で視覚に訴える!
-
ホワイトボードでイラストを描く
-
パペット人形で寸劇風に話す
-
「メロンパン」と書いた札を取り出して笑いを誘う
など、視覚的な工夫はインパクト大!
もちろん、学校のルールに沿って、やりすぎない範囲で行いましょう。
第9章:構成で差がつく!ギャグの使い方

9-1:寸劇風ストーリーで展開
公約の内容を伝えながらも、寸劇風に話を展開すると、臨場感と笑いを同時に演出できます。
🥐 例:「購買部のメロンパンが売り切れた話」
-
「購買部に駆け込んだのに…メロンパンがない! 僕の心も売り切れ寸前です…!」
-
「そんな悲劇をなくすために、在庫管理システムを導入したいんです」
-
「売り切れアラームの音声? もちろん僕の声で叫びます!『メロンパンがないぞーっ!』」
テンポと間を大切に、声の抑揚をつけて演じれば、場の空気が一気に明るくなります。
9-2:逆説を活かした「ギャップ笑い」
あえてマイナスから入ってプラスで締めるという「ギャップ構成」は、共感も笑いも取りやすいテクニックです。
🎓 例1:「運動苦手だけど…」
「僕、体育は苦手でボールが友達になってくれません。でも、生徒会の仕事は頭脳戦。僕の出番、きましたね!(笑)」
🧍♂️ 例2:「地味キャラを武器に」
「僕、あまり目立ちません。でも、生徒会長がいつも前に出すぎても疲れるでしょ? だから、僕くらいがちょうどいいバランスです!」
“自分らしさ”をベースにした逆説ギャグは、説得力があり、好印象につながります。
9-3:時事ネタは“さりげなく”
時事ネタを入れる場合は、「わざとらしくない自然さ」が鍵です。
🧃 例:「エコ活動×自虐ネタ」
「僕、家ではちゃんとゴミ分別してます。でも、まだまだ“ゴミな男”から卒業できません(笑)<br>だからこそ、学校でもエコ意識を高める活動を進めたいんです!」
SDGsや流行ネタを少しだけ交えれば、賢さとユーモアの両立が可能になります。
第10章:まとめとメッセージ
10-1:ギャグは主役じゃない
ここまでギャグの重要性をお伝えしてきましたが、あくまで主役はあなた自身の想い・公約・姿勢です。
✨ ギャグは、あなたの魅力を引き出す“味付け”でしかありません。
「とにかく笑わせよう」と思いすぎると、空回りしたり、印象が軽くなったりすることも。
自然体で、あなたらしい演説を心がけてください。
10-2:自分に合った笑い方を
-
明るく元気なタイプ → 勢い系・リズム系のギャグ
-
落ち着いた雰囲気 → 皮肉系・じんわり系のギャグ
といったように、自分のキャラに合わせた笑いのスタイルを見つけるのがベストです。
😌 無理に「面白いキャラ」を演じようとせず、“等身大の自分”に合った笑いを探してみてください。
10-3:楽しむことが一番の成功法
最後に、最も大事なことをひとつ。
💡 「自分が演説を楽しむこと」が、最高のギャグよりも伝わります。
緊張しすぎると笑顔も出ず、言葉にも余裕がなくなってしまいます。
練習した自分を信じて、堂々と、笑顔で演説に臨んでください。
その姿こそが、一番の“票を集める武器”になるのです。
第11章:演説スクリプト例(カスタマイズOK)
※こちらは前章でご提示いただいたスクリプトで完成度が非常に高いため、特に修正は必要ありません。必要があれば、フォント装飾や構成の整え直しを行います。
第12章:おわりに
生徒会演説で使えるギャグのテクニックや構成、注意点をたっぷりとご紹介してきました。改めて強調したいのは、**ギャグは「あなたの真剣さを伝えるためのスパイス」**だということです。
🎯 覚えておきたい3つのルール:
-
✅ ギャグは“共有できる笑い”を意識すること
-
✅ 内容より“誠意”が伝わることが最重要
-
✅ 公約・想いをしっかりと軸に据えること
本気の思いにユーモアを添えることで、聴衆に届く演説は完成します。
そしてその経験は、今後の人生でも大きな財産になるはずです。
🌟 あなたの演説が、誰かの心に残るように。心から応援しています。がんばってください!


