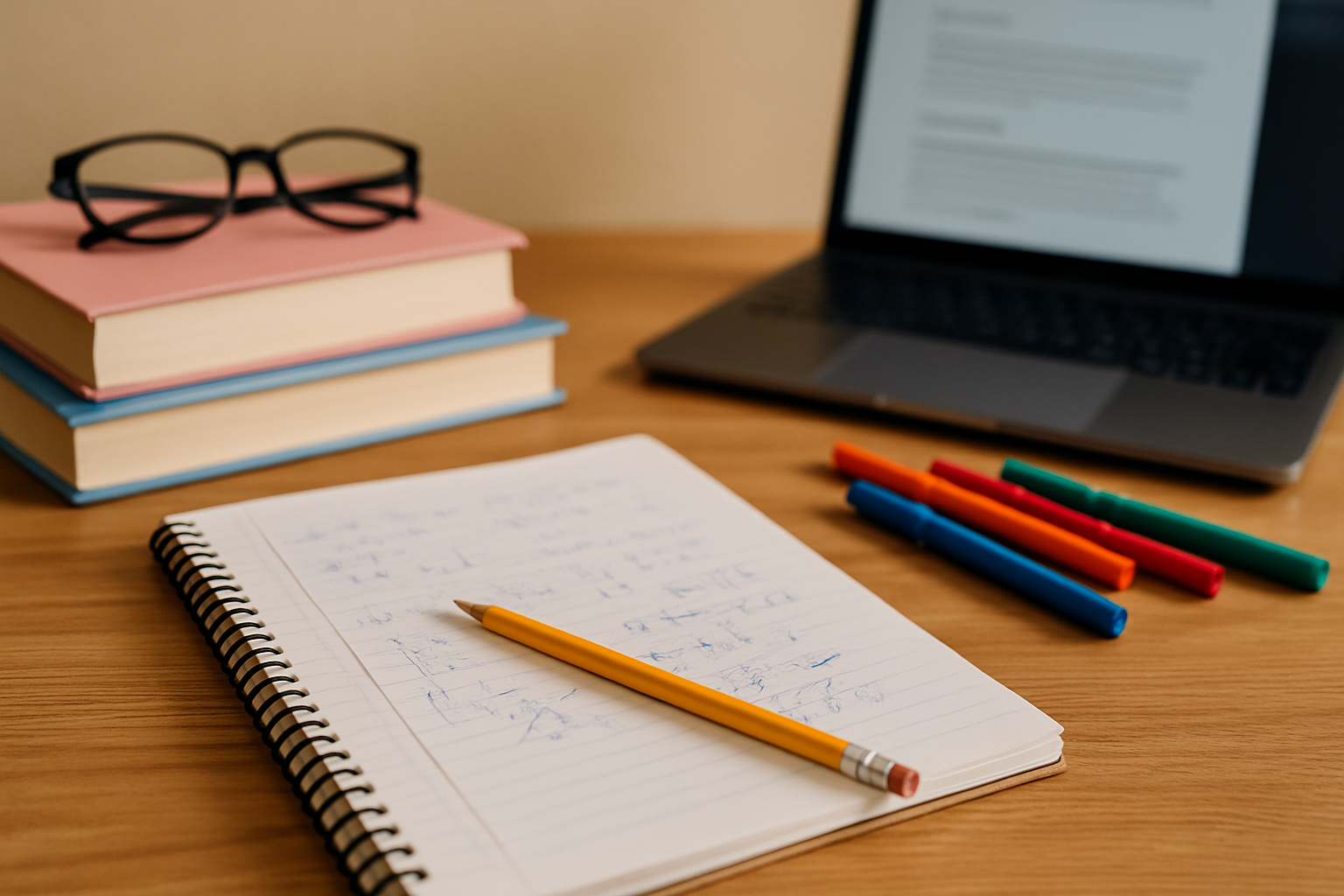はじめに|勉強って難しい?でもコツがある!
「テスト勉強、頑張ってるのに結果が出ない……」そんな風に感じていませんか?高校生活は勉強だけじゃなく、部活や友達付き合い、バイトなどやることが盛りだくさんで、つい勉強が後回しになりがちですよね。でも、ちょっとした工夫や自分に合った勉強法を知るだけで、勉強の効率はグッとアップします。実は「やる気が出ない」「集中できない」という悩みも、やり方を変えるだけで自然と改善することが多いんです。
たとえば、私自身も高校1年生の頃は、ただ教科書を読むだけの勉強で結果が出ずに落ち込む日々が続いていました。でも、あるとき「自分に合ったやり方」を意識し始めてからは、勉強がちょっとずつ楽しくなり、成績も少しずつ上がっていったんです。完璧じゃなくてもいい。少しずつ「自分なりのコツ」を掴んでいくことで、自信がついていきます。
この記事では、実際に効果があった勉強法や、今日から使えるちょっとした裏ワザをたっぷり紹介していきます。特に「テストで点数を上げたい!」「やる気を出したい!」という高校生に向けて、楽しく、前向きに取り組める内容にしました。
どれも実際に多くの人が効果を感じた方法ばかりなので、きっとあなたにも合うものが見つかるはず。自分のスタイルに合った方法を見つけて、ぜひ明日から試してみてくださいね。この記事が、あなたの勉強のきっかけになれば嬉しいです!
1. 勉強時間より「質」が大事!効率重視の考え方
ダラダラ長時間より、集中した1時間
よく「3時間勉強した」と自慢する人がいますが、実際に大切なのはその“中身”です。長時間机に向かっていても、スマホを触りながらだったり、テレビを見ながらなんとなくノートを開いているだけでは、脳はまったく集中していない状態です。それでは時間だけが過ぎてしまい、成果にはつながりません。勉強は“質”が勝負です。たとえ1時間でも、本気で集中できた時間のほうが、何倍も価値があります。
私自身も以前は、「長く勉強していれば安心」という気持ちで、夜遅くまでだらだらとノートを眺めるだけの日々がありました。でも成績は伸びず、むしろ疲れだけが残るように。そこで試してみたのが「短時間集中型」の勉強スタイルです。集中して取り組むことで頭に残る量が劇的に変わり、時間にも気持ちにも余裕が生まれました。
タイマー活用で集中力UP
- ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)を試す
- 集中タイムにはスマホを別室に置く
- 終わったら自分にご褒美(おやつ、ストレッチなど)を用意する
- 勉強前に「今日はここまでやる」と範囲を決める
- 作業開始前に軽い運動や深呼吸で集中スイッチを入れる
特にポモドーロ・テクニックは、高校生にもおすすめの方法です。25分という区切りは短すぎず長すぎず、集中力が保ちやすい絶妙な時間設定。さらに5分の休憩を挟むことで、疲れが溜まりにくくなり、次の集中にもつながります。スマホを別の部屋に置くなど、誘惑を断ち切る工夫も大切です。
こうした「集中する時間」と「リラックスする時間」を意識的に切り替えるだけで、勉強の効率は驚くほど向上します。効率よく勉強すれば、他の時間も確保しやすくなり、部活や趣味との両立もグンと楽になりますよ!
2. 科目別の勉強法を知ろう!得点アップの近道
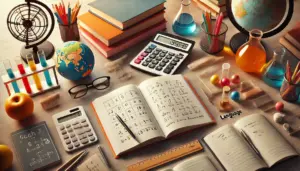
科目ごとに効果的な勉強法は異なります。それぞれの特徴に合わせたアプローチをすることで、学習効率が大きく変わります。ここでは英語・数学・国語の3科目について、それぞれの得点アップにつながる具体的な勉強法を紹介します。
英語:毎日の音読&単語暗記がカギ
英語は積み重ねが重要な科目です。毎日少しずつ継続することが成果につながります。
- 音読は発音より“リズム”が大事。英文の抑揚やリズムを意識しながら読むことで、リスニング力と読解力が同時に鍛えられます。
- 単語は毎日5個ずつ覚えるのがおすすめ。数は少なくても、繰り返し復習することが記憶の定着に繋がります。
- 英文をノートに書き写しながら音読すると、視覚・聴覚・触覚を同時に使えて記憶効果がアップ。
- 英語の例文を自分の生活に置き換えて話す練習をすると、自然と使える表現が身につきます。
私の場合、通学中に音読アプリを使って英文を聴きながら口に出して真似していました。初めは恥ずかしかったけど、慣れると意外と楽しく、英語への抵抗感が減っていきました。
数学:パターン暗記+とにかく手を動かす
数学は「理解」と「練習」がセットです。見ているだけではできるようになりません。
- 解法を理解したら、似た問題を繰り返し解いて定着させましょう。
- 間違えた問題はそのままにせず、なぜ間違えたのかを分析することで理解が深まります。
- ミスノートを作って「自分だけの参考書」にする。これは特におすすめです。
- 問題ごとに「ポイント」や「落とし穴」をメモしておくと、次に見返すときにすぐ理解できます。
- 苦手な単元は動画や解説サイトを活用して「先生を変える」感覚で理解を深めるのもアリ。
僕自身、数学が大の苦手だったのですが、ミスノートを作り始めてから「自分のつまずき」に気づけるようになり、そこから一気に点数が上がりました。
国語:読解力は“慣れ”で育つ
国語は才能より“慣れ”が大事。特に現代文や古文は、読む経験を積むことで力がついていきます。
- 毎日少しずつ長文を読む習慣をつけると、自然と読むスピードと理解力が上がります。
- 文章を読んだら「要点は何か?」を自分の言葉でまとめる練習をすると、記述式にも強くなります。
- 難しい文章でも、わからない言葉をそのままにせず、辞書アプリなどですぐに調べる癖をつけるとボキャブラリーが増えます。
- 漢字や語彙はアプリやカード形式で毎日5分でも触れる習慣を。
- 古文はまず「現代語訳」から読んで、内容を理解してから本文に戻るとスムーズです。
私は新聞のコラムや本の短いエッセイを毎朝読むようにしていました。それだけで国語の点数が安定し、読書が好きになるきっかけにもなりました。
それぞれの科目に合った方法で、自分に合うやり方を探しながら学習していくのが得点アップの近道です。
3. ノートの取り方が成績を左右する!?
「まとめる」より「考える」ノートを意識
ノート作りというと、カラフルなペンで綺麗に仕上げることに注力しがちですが、実は見た目よりも「内容の質」が重要です。色ペンをたくさん使って、きれいにまとめただけのノートは、見返しても情報が頭に入りにくく、自己満足で終わってしまうケースが多いです。
では、どんなノートが「成績アップにつながるノート」なのでしょうか?それは、自分の思考や理解のプロセスが詰まったノートです。たとえば、
- 問題→自分の考え→正解
- なぜ間違えたのか?を書いておく
- 解いたときの感情やひっかかったポイントをメモする
- 「なぜこうなるのか?」という問いを残す
こうした“思考の痕跡”があるノートは、後から見返したときにそのときの考えを再体験でき、理解が深まります。さらに、自分だけの「参考書」のような存在になるので、テスト前の復習にも最適です。
私自身も以前はまとめノートばかり作っていましたが、復習のときに内容が頭に入らず困った経験があります。そこで「自分の間違いと向き合うノート」に変えてみたところ、復習がぐっと楽になり、同じミスを繰り返さなくなりました。
スマホでノートを撮って復習もOK
紙に書くのが苦手な人や、ノートを持ち歩くのが面倒という人には、デジタルノートの活用もおすすめです。iPadやスマホのノートアプリ(GoodNotesやNotabilityなど)を使えば、手書きの感覚を残しつつ、データとして管理できます。
- ノートをスマホで撮影してクラウド保存
- タグ機能で教科別に整理
- すき間時間にスマホでサッと復習
- 録音機能付きのアプリで授業内容を記録
デジタルノートの利点は、「いつでもどこでも見返せる」こと。私も移動中にスマホでノートを見たり、寝る前に1日分の内容を確認する習慣を取り入れることで、勉強の定着率が上がりました。
ノートは「自分の思考を深める道具」として活用すれば、勉強がもっと効果的になります。見た目より“中身重視”でいきましょう!
4. 暗記が苦手な人におすすめ!覚えるコツ
五感を使うと記憶に残りやすい
暗記が苦手と感じている人の多くは、ただ目で見て覚えようとしています。でも人間の脳は、視覚だけよりも、複数の感覚を同時に使うことで記憶が定着しやすくなるんです。五感をうまく使えば、覚えるのが驚くほどラクになります。
- 声に出して読む(聴覚)
- 書いて覚える(触覚)
- イメージと一緒に覚える(視覚)
- 手でジェスチャーを加える(運動感覚)
- 香りや場所と結びつけて記憶する(嗅覚・空間感覚)
例えば、「水の沸点=100℃」を覚えるときに、ただ数字だけを見るより、「お風呂より熱い!」「カップラーメンを作る温度だ!」など、身近なイメージや経験と結びつけると一気に記憶が定着します。私も社会の年号などは「語呂合わせ+イラスト」で覚えるようにしていました。頭の中で絵やストーリーを描くことで、単純な数字も忘れにくくなります。
また、部屋の中で場所を変えながら暗記するのも効果的です。「この単語はベッドの上で覚えたな」といったように、空間と記憶がリンクすると、思い出しやすくなるんですよ。
クイズ形式で楽しく復習
暗記を「つまらない作業」だと思っていませんか?でも工夫次第で、暗記も楽しいゲームになります。
- 友達と交互に問題を出し合う
- フラッシュカードアプリ(Anki、Quizletなど)で反復練習
- 家族に問題を出してもらう
- 単語カードをお風呂やトイレに貼る
- 朝起きてすぐ、寝る前に一問テスト
このように、遊び感覚で取り入れると、気づいたらたくさん覚えていた!ということもあります。特に人と関わる形式で暗記すると、記憶に残りやすくなるのもメリットです。
暗記は「工夫」の勝負。苦手意識を手放して、自分なりの楽しいスタイルを見つけてみましょう!
5. スキマ時間を制する者が成績を制す!

「勉強する時間がない」と感じている人にこそ注目してほしいのが、“スキマ時間”の活用です。通学時間や休み時間、授業のちょっとした空き時間、寝る前の5分など、日常の中に散らばっている「使える時間」を合わせると、実は1日10分×6回=1時間以上にもなります。
この「スキマ時間」をうまく活用できるかどうかが、成績アップのカギを握ると言っても過言ではありません。
私もバス通学だったので、その時間に英単語を覚える、数学の公式を見直すなどの習慣をつけたことで、授業中の理解度がグッと上がりました。電車やバスに揺られながらの勉強でも、集中できるように工夫すれば十分効果的なんです。
スキマ時間活用法
- 単語帳を常に持ち歩いて、いつでもチェックできるようにする
- 教科書の要点や図解をスマホで撮影して、待ち時間に確認
- 音声で暗記(録音して聞く)—自分の声で重要語句や解説を録音し、通学中や家事中に耳で復習
- 勉強アプリ(スタディサプリや英単語アプリなど)を活用して、ゲーム感覚で学習
- 朝起きたらまず単語を10個確認→夜寝る前に同じ単語をもう一度確認して定着
こうした細切れの時間を意識して使うと、「まとまった時間が取れないから勉強できない」という言い訳が消えます。しかもスキマ時間なら短いので集中力が続きやすく、反復もしやすいんです。
ポイントは、「あらかじめ何をするか決めておく」こと。なんとなくスマホをいじって終わってしまうのではなく、「この10分は英単語のチェック」と決めておけば、迷わず取り組めます。
スキマ時間を侮るなかれ。毎日の積み重ねが、いつの間にか大きな差になりますよ!
6. 目標設定でやる気が続く!
「目的」があると勉強が楽しくなる
「なんとなく勉強しているけど、やる気が出ない……」そんなときは、明確な目標があるかどうかを見直してみましょう。目標があると、そこに向かって「なぜ今、これを勉強するのか」がハッキリし、自然と集中力もやる気も高まります。人は目的があると、行動に意味を見出せるようになるんです。
例えば、ただ「勉強しなきゃ」と思うより、「英語の小テストで90点取るぞ!」と決めた方が、勉強内容が具体的になりやすいですよね。さらにその目標に期限を設けると、行動計画が立てやすくなり、実行力もアップします。
目標のレベルを分けてみよう
- 短期目標:次の小テストで80点以上!
- 中期目標:学年末までに学年順位20位以内に入る
- 長期目標:○○大学に合格!
このように、短期・中期・長期で段階的に目標を立てると、日々の勉強にも意味が生まれ、達成するごとに達成感が得られます。私も実際に、毎月「今月の目標」をノートに書いて、達成できたかを振り返る習慣をつけていました。それだけで自然と意識が変わり、やる気の波も少なくなりました。
目標は“見える化”すると効果的
目標は心の中で思っているだけでは意味がありません。できれば紙に書いて、勉強机の前やスマホの待ち受けに貼っておくのがおすすめです。毎日目にすることで、自然と意識が引き戻され、「やろう!」という気持ちを思い出すきっかけになります。
また、達成したときはしっかりと自分を褒めてあげるのも大切です。モチベーションの維持には「できた!嬉しい!」という感情がとても効果的だからです。
目標はゴールであり、地図でもあります。自分だけの“学習の道しるべ”を持つことで、迷わず進めるようになりますよ!
7. スマホとの付き合い方を考えよう
勉強中のスマホは最大の敵!?
スマホはとても便利なツールですが、勉強中においては集中力を奪う“最大の敵”になることもあります。通知が1回鳴るだけで、集中していた気持ちが一気に途切れてしまうこと、ありませんか?SNSの通知、友達からのメッセージ、ゲームアプリの誘い……「ちょっとだけ見よう」と思ったその5分が、気づけば30分以上になっていたなんてことも珍しくありません。
また、スマホを手元に置いておくだけで、無意識のうちに意識が分散してしまうという研究結果もあります。つまり、見ていなくても“あるだけで邪魔”になっている可能性があるということです。
私もスマホの誘惑に何度も負けた経験があります。机に向かったはずが、気づいたらSNSで好きな芸能人の投稿を見ていた……そんな自分にガッカリすることも。でも、ある日スマホを別室に置いてみたら驚くほど集中できたんです。それ以来、勉強中はスマホと“距離を取る”ようにしています。
おすすめの対策
- スマホを別の部屋に置いて、視界から完全に外す
- 勉強用の集中アプリを使う(「Forest」「Focus To-Do」「Study Bunny」など)
- 機内モードやおやすみモードに設定して通知を遮断する
- アプリの使用制限を設定して、一定時間使えないようにする
- タイムロック付きのボックスやケースに入れる
- 親や兄弟に預けて、勉強が終わるまで触れないようにする
- アナログ時計やタイマーを使ってスマホなしで時間管理する
こうした小さな工夫を積み重ねることで、スマホの誘惑に振り回されずに済むようになります。最初は不安でも、慣れてしまえば「スマホが手元にない方が気が楽」と感じるようになるはずです。
誘惑に勝つには、誘惑を視界から消すのが一番。環境を自分で整えることで、集中力はぐっと上がりますよ!
8. 模試や過去問の使い方で差がつく!

模試は「解いた後」が大事
模試を受ける目的は「今の実力を知ること」と「弱点を見つけること」です。点数だけ見て一喜一憂して終わりにしてしまうと、模試の本当の価値を活かせません。模試は「受けた後の分析」がもっとも重要です。
- 間違えた理由を分析し、「なぜ間違えたのか」「どうすれば防げたのか」を記録
- 出題傾向をチェックして、どの分野の問題が多く出題されているか把握
- 自分が苦手とする単元や設問形式をあぶり出す
- ケアレスミスと知識不足を分けて考える
- 解説をしっかり読み、自分なりに要点をまとめ直す
私の場合、模試のあとに「反省ノート」を作って、各教科の失点原因を書き出すようにしました。たったこれだけでも次回の勉強の優先順位が明確になり、模試を受けるごとに力がついていくのを実感できました。
過去問は宝の山
過去問は、そのまま「出題者からのメッセージ」です。どんな力を見ているのか、どんなミスをしやすいかなど、問題の形式から多くのヒントが得られます。
- 本番形式で時間を計って解くことで、実戦力が身につく
- 問題の傾向を知ることで、効率的な対策ができる
- 似た問題を集めて「頻出パターン集」を自作するのも効果的
- 解いたあとは自己採点+分析が必須
- 間違えた問題を「過去問ノート」にまとめておくと、復習しやすい
私は志望校の過去問を5年分コピーして、1週間に1年分ずつ解いていました。解いた後には、必ず「この問題で問われていることは何か?」を考えるようにして、自分の理解度を測るようにしていました。これを続けることで、自然と「得点する力」が身についていきました。
模試も過去問も、“受けっぱなし”では効果が半減します。使い倒す気持ちで、復習と分析に力を入れていきましょう!
9. メンタルの整え方も重要!
勉強とメンタルはセットで考える
勉強は「心」と「頭」が連動している活動です。不安や焦りがあると、いくら机に向かっても集中できず、内容が頭に入ってこないことってありますよね。逆に、心が安定していると驚くほどスムーズに勉強が進むこともあります。だからこそ、メンタルケアは勉強と同じくらい大切なんです。
特にテスト前や受験期は、プレッシャーや緊張で心が押しつぶされそうになることもあります。そんなときは、自分のメンタルとしっかり向き合って、無理をしないことが大切です。「がんばらなきゃ」と思うあまり、自分を追い詰めすぎると逆効果になることも。
メンタルを整えるためのコツ
- 深呼吸やストレッチでリラックス(体の緊張をほぐすだけでも気分が変わります)
- 好きな音楽を聞いたり、アロマを焚くなど、五感を使って気分転換
- 友達や家族と話して、気持ちを言葉にするだけでも心が軽くなります
- 勉強したことをSNSや日記で記録して、「自分はこれだけやったんだ」と自信に変える
- 1日5分だけでも「何もしない時間」を作る(ぼーっとするのも大切)
- 頑張った自分に、小さなご褒美をあげる(好きなスイーツ、動画タイムなど)
私自身、気持ちが沈んだときは、カフェに行ってお気に入りの紅茶を飲みながらノートを見直すことにしていました。場所を変えるだけでも、気分が切り替わって前向きになれるんです。
心のコンディションを整えることは、成績アップへの土台づくり。疲れたときは、自分を責めずに「今日はここまででも十分」と思える柔らかさも、受験を乗り切るためには必要なスキルですよ。
10. 自分に合ったスタイルを見つけよう!
勉強法は「人それぞれ」
勉強法には正解がありません。周りがやっている方法が、自分にとって効果的とは限らないんです。むしろ「みんなと同じ方法」で結果が出ないと、「自分には向いていないのかも……」と自信を失ってしまうことも。でも大丈夫、自分に合ったやり方を見つけることが何より大切です。
- 朝型?夜型?:朝の方が頭がスッキリして集中できる人もいれば、夜の静かな時間の方がはかどる人もいます。まずは試して、どちらが自分に合っているかを見極めましょう。
- 音楽を聞きながら?無音がいい?:BGMが集中力を高める人もいれば、完全な静寂でないと集中できない人も。ジャンルも重要で、クラシックや自然音が人気です。
- グループ派?一人派?:誰かと一緒に勉強することでやる気が出る人もいれば、自分のペースでじっくり取り組みたい人もいます。どちらが自分にとってストレスが少ないかを基準に考えるのがおすすめです。
私もいろいろ試しました。夜に静かな音楽をかけながら、1人でタイマーを使って集中する方法が自分には一番合っていました。最初は人に勧められた方法をそのまま真似していましたが、なかなかうまくいかず、ストレスばかり溜まっていたんです。でも、自分のリズムや性格に合わせて調整していくことで、徐々に「自分にピッタリなスタイル」ができあがっていきました。
自分に合った方法を見つけるには、まず“試してみる”ことが大切です。一度やってみて「合わなかったな」と感じたら、少し変えて再チャレンジすればOK。トライ&エラーを繰り返しながら、最終的に自分のベストスタイルを作り上げていきましょう。
そして、あなたのスタイルが見つかったら、それを大切にしてください。他の人がどうしているか気にしすぎず、自分の感覚を信じることが、勉強の継続と成果につながりますよ!
まとめ|明日から始めよう!小さな一歩が大きな成果に
ここまで、勉強の効率を上げるためのさまざまな方法やコツを紹介してきましたが、一番大切なのは「実際にやってみること」です。情報を知るだけでは変化は起きません。行動に移してこそ、本当の成長が始まります。
どんな方法も、最初から完璧にできる人なんていません。最初は失敗してもいいんです。「これは自分に合わないかも?」と思ったら少しアレンジしてみたり、他の方法を試してみたりすることが大切です。トライ&エラーの繰り返しが、あなたの「勉強スタイル」を育てていきます。
「失敗=ダメ」ではなく、「失敗=成長の材料」として捉えてみてください。大切なのは前向きな気持ちを忘れずに、コツコツと続けること。そうすれば、気づいたときには「なんか前より勉強が楽になったな」「ちょっと自信がついてきたかも」と思える日がきっとやってきます。
まずは、この記事の中から気になった方法を一つ選んで、今日から試してみましょう。小さな一歩でも、積み重なれば大きな成果につながります。
勉強を「ツライもの」から「自分を成長させてくれるもの」に変えるのは、あなた自身です。未来の自分のために、今日の一歩を踏み出してみてくださいね!