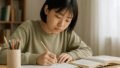はじめに
部活も勉強もがんばりたい!と思っている中学生のみなさん、こんにちは!毎日の学校生活の中で、「時間が足りない」「もっと効率よく勉強したいのに」と感じている人も多いのではないでしょうか?実際、授業、宿題、部活、さらには友達との付き合いや家族との時間…やることが多すぎて、気づいたら夜!なんてこと、私もよくありました。
私は中学生のとき、バスケットボール部に入っていて、週に6日間は練習がありました。土日は朝から練習や試合で一日が終わることもよくあり、平日の放課後はヘトヘト。それでもテストの点数を落としたくなくて、毎日あの手この手で時間を作って勉強していました。最初はなかなかうまくいかなかったけど、少しずつ自分に合ったやり方を見つけて、両立できるようになっていったんです。
今回の記事では、「部活と勉強を両立したい」と本気で考えているあなたのために、時間の使い方や勉強のコツ、そして気持ちの切り替え方など、私自身の体験を交えながら紹介していきます。「両立は無理…」と思っている人にも、今日からすぐに試せるヒントがたっぷり詰まっていますよ!
大切なのは、「完璧にやらなきゃ」と思いすぎず、「少しずつでも前に進もう」という気持ちです。このページを読み終わったとき、きっとあなたの中に「やってみよう!」という前向きな気持ちが芽生えているはずです。
なぜ部活と勉強の両立が難しいのか?
時間が限られている
中学生の1日は、学校の授業、部活、宿題、家の手伝い…とスケジュールがびっしり詰まっています。朝早くから登校して、授業を受けて、放課後は部活で走り回る。そして帰宅してからは宿題やテスト勉強。特に運動部に入っていると、練習が遅くまで続いたり、休日にも大会が入っていたりして、自由に使える時間がかなり少なくなってしまいます。
私が中学生だったときも、週末はほとんど部活で埋まり、友達と遊ぶ時間もなく、気づいたらテストが目前…ということがよくありました。そんなときに「もっと時間があればいいのに」と何度思ったことか。でも実は、限られた時間の中でどう動くかが大事なんですよね。
体力・気力の問題
部活から帰ってきたあと、「さあ、勉強しよう!」と思っても、体が動かない…。そんな経験ありませんか?疲れてソファにゴロンと寝転がったら最後、気づいたら寝ていた、なんてことも。これは決してサボりではなく、自然なことです。身体が疲れていると、集中力も下がるし、やる気も出にくくなります。
さらに、長時間の練習やハードな試合の後は、精神的にもエネルギーを使い果たしている状態。そんな中で「やらなきゃ」と思うと、余計にストレスを感じてしまうんです。だからこそ、上手にリフレッシュしてから勉強に取り組む工夫が必要です。
時間の使い方がわからない
「よし、勉強しよう」と思って机に向かっても、気がついたらスマホを触っていたり、動画を見始めたり…。そんなふうに、何から手をつけていいか分からず、結局だらだらと時間を過ごしてしまうことってありますよね。
私も当時、やることリストを作っていないと、「まずどれをやる?」「全部面倒くさいな…」と感じて、勉強が進まない日がありました。でも、「今はこれをやる時間」と自分の中でルールを作ることで、気持ちが切り替わるようになりました。時間の使い方に慣れていないと、どうしても効率が悪くなってしまうので、まずは「自分の行動を見える化すること」から始めるのがおすすめです。
目標を明確にしよう

なぜ勉強するのかを考える
「成績を上げたい」「志望校に合格したい」「将来の夢に近づきたい」など、勉強する目的を明確にすると、やる気もアップします。ただ「勉強しなきゃ」と思うだけでは、なかなか行動に移せませんよね。そこで大切なのが、自分がなぜ勉強するのか、どんな未来を描いているのかをしっかり考えることです。
たとえば、「将来は医者になりたいから、理科と数学を頑張りたい」といった具体的な理由があると、日々の勉強も前向きな気持ちで取り組めるようになります。また、目標がはっきりしていると、途中でつまずいたときにも、「なぜやっているのか」を思い出すことで、立ち直るきっかけにもなります。
私の場合は、「高校は○○高校に行って、将来は英語を使った仕事がしたい」と思っていたので、英語の単語帳やリスニングを毎日少しずつでも続けるようにしていました。具体的な目標があるだけで、頑張る理由が明確になるんです。
目標を紙に書いて貼ろう
目に見える場所に目標を書くと、自然と意識するようになります。特に勉強机の前や、毎朝見る鏡の横など、日常的に目に入る場所がベストです。
私は机の前に「定期テストで5教科400点!」と書いた紙を貼っていましたが、それだけでなく、「今月の目標」「今日のひとこと応援メッセージ」なども付け加えて、自分を励ます工夫をしていました。書くことで頭の中が整理されるし、言葉として目にすると「よし、やってみよう」という気持ちになります。
カラフルなペンやイラストを使って自分だけの“やる気ボード”を作るのもおすすめです。楽しみながら目標を意識できると、毎日のモチベーション維持にもつながりますよ。
タイムスケジュールを作ってみよう
平日の一日の流れを見直す
帰宅後の時間帯をどう使っているか、まずは書き出してみましょう。頭の中で「だいたいこの時間にこれをやってる」と思っていても、実際に紙やアプリに書き出してみると、思っていた以上に無駄な時間が見つかることがあります。
たとえば、帰宅後すぐにスマホをチェックしている時間が15分のつもりだったのに、気づけば30分以上使っていた…なんてことも。まずは自分の行動を正直に見つめ直すことが、時間管理の第一歩です。私は自分の1日の流れを30分単位で記録してみたことで、「ここで時間をムダにしてたんだ!」と気づくことができました。
また、見直した流れの中で「やらなきゃいけないこと」と「やりたいこと」のバランスを考えることも大切です。すべてを詰め込みすぎると、逆にストレスになって続きません。まずは無理のない範囲で、自分が続けられそうなスケジュールを考えてみましょう。
スケジュール例
以下は一つの例ですが、自分の部活や生活スタイルに合わせてアレンジしてみてください。
- 17:30 帰宅・軽食(部活で疲れているので、エネルギー補給を忘れずに!)
- 17:50 リフレッシュタイム(ストレッチや仮眠10分など)
- 18:10 宿題・勉強タイム(まずは学校の宿題から)
- 19:00 好きな教科の勉強(やる気が出る教科でエンジンをかけよう)
- 19:30 夕食・休憩(家族との会話もリラックスの時間)
- 20:00 暗記中心の勉強(単語や年号など、集中力が必要な内容)
- 20:45 翌日の準備・軽いストレッチ(心と体を整える時間)
- 21:00 入浴・リラックスタイム(お風呂で一日の疲れを流しましょう)
- 21:30 日記・振り返りノートを書く(今日の良かったこと、改善点を記録)
- 22:00 就寝(スマホは手の届かない場所に置くと◎)
このように、具体的な行動と時間を組み合わせておくと、「今は何をやる時間か」が明確になり、迷いが減ります。最初は理想どおりにいかなくてもOK!毎日少しずつ調整しながら、自分だけのベストスケジュールを見つけていきましょう。
スキマ時間を活用する
通学時間や休み時間もチャンス!
「勉強する時間がない」と感じる中学生こそ、スキマ時間の活用がカギです。特に通学中や授業と授業の間の休み時間など、意外と“何もしていない時間”はあります。
例えば、通学中に英単語や歴史の年号をスマホアプリで確認するだけでも、毎日続ければ大きな差になります。バスや電車の中では、画面を見るのが難しいときもありますが、そんなときは音声で単語を聞くのもおすすめ。リスニングの力も同時に鍛えられます。
また、学校の休み時間にも、友達と一緒にクイズ形式で問題を出し合えば、楽しく記憶にも残りやすいです。単語カードを小さなポーチに入れて持ち歩けば、どこでもすぐに取り出して使えるので便利ですよ。
私も当時、駅までの徒歩時間を使って、歴史の語句をぶつぶつつぶやきながら覚えていました。暗記は「繰り返し」が大事なので、スキマ時間で何度も見ることがとても効果的なんです。
自分専用の暗記ノートを作ろう
スキマ時間に最大限活用できるアイテムが「自分専用の暗記ノート」です。これは、自分が覚えたいことをコンパクトにまとめたノートで、持ち歩きやすいサイズにするのがポイント。B6サイズやA6サイズの小さめのノートがおすすめです。
ノートの中には、苦手な単語や漢字、理科の公式など、覚えたい情報を色分けして書いたり、図やイラストを入れたりして、自分だけのわかりやすい構成にしましょう。重要なところはマーカーで強調して、見た瞬間に思い出せるように工夫すると効果的です。
私は「電車ノート」と呼んで、自分の苦手な英語表現を集めたノートを毎朝読んでいました。時間が限られているからこそ、自分に必要な情報だけをギュッと詰め込んだノートが大活躍します。
さらに、1ページごとに日付を書いておくと、どのくらい繰り返し見ているかが分かってモチベーション維持にもつながります。スキマ時間を味方にすれば、忙しい毎日でも確実に知識が身についていきますよ!
勉強法を工夫しよう

ポモドーロ・テクニックを試す
ポモドーロ・テクニックとは、「25分間集中して作業→5分間休憩」を1セットとし、それを繰り返すことで集中力と効率を高める方法です。短時間で区切ることで、「あと○分だけ頑張ろう」という気持ちになれ、長時間の勉強よりも集中が続きやすくなります。
部活で疲れて帰ってきた日でも、「とりあえず25分だけやってみよう」と思えば、意外とスムーズに机に向かえます。私はこの方法を取り入れてから、「今日は疲れてるから無理…」と思う日でも、短時間なら集中できることが増えました。
また、5分間の休憩時間には軽いストレッチをしたり、好きな音楽を1曲聴いたりして、リフレッシュするとより効果的です。ポモドーロのサイクルを4回繰り返したら、15〜30分ほどの長めの休憩を取るようにしましょう。アプリを使えば時間管理も楽になりますよ。
好きな教科から始める
勉強を始めるとき、苦手な教科から取りかかろうとすると、気分が重くなりがちですよね。そんなときは、あえて自分の「得意な教科」や「好きな分野」から始めることで、自然とエンジンがかかります。
私は英語が好きだったので、まずは単語の復習やリスニングからスタートすることが多かったです。すると「今日はちょっと頑張れそう!」という前向きな気持ちになって、他の教科にもスムーズに移れました。
また、「得意な教科→苦手な教科→得意な教科」という順番で組み合わせると、全体的なやる気が落ちにくくなります。まるで勉強にリズムをつけるような感覚で、飽きずに続けることができます。
勉強はただ机に向かえばいいというものではなく、「どの順番で、どんな気持ちで取り組むか」も大事です。自分に合った流れを見つけることで、日々の勉強がもっと楽しく、効率的になりますよ。
部活の疲れをリセットする工夫
軽いストレッチでリラックス
部活で全力を出したあと、体がだるかったり筋肉が張っていたりすることはよくあります。そんなときにおすすめなのが、帰宅後の軽いストレッチ。無理なく体をほぐすことで、筋肉の疲れが取れやすくなり、血行も良くなります。
特に、太もも、ふくらはぎ、肩回りなど、よく使った部分を重点的に伸ばすと効果的です。深呼吸をしながらゆっくりと体を伸ばすことで、気分もリラックスでき、心も体も落ち着いていきます。
私はストレッチをしながら「今日の練習どうだったかな」と少し振り返る時間にしていました。自分の頑張りを確認することで、ポジティブな気持ちになれて、次の勉強への気持ちの切り替えにも役立ちます。
お風呂でリフレッシュ
ストレッチと並んで効果的なのが、ぬるめのお湯での入浴です。38〜40度くらいのお湯に10〜15分ほど浸かるだけで、全身の筋肉がゆるみ、心までふっと軽くなります。お風呂の中は、自分と向き合うリラックスタイムにもなります。
私の場合は、お気に入りの音楽を流しながら、ゆっくり目を閉じてリフレッシュしていました。ときにはアロマの入浴剤を使って香りで癒されるのもおすすめ。疲れた体をいたわることで、「よし、勉強も頑張ろう」と自然と前向きな気持ちになれるんです。
また、入浴後は体が温まって血行がよくなっているので、集中力が高まりやすくなります。勉強の前に軽くリラックスする時間を持つだけで、学習効率がぐんと上がることもありますよ。
大切なのは、「疲れたまま勉強しようとしない」こと。まずは一度心と体をリセットして、無理なく次の行動に移る準備をしましょう。それが結果的に、時間の使い方も効率よくなる秘訣です。
家族との連携も大事
家族にスケジュールを伝えよう
勉強や部活に集中したいときは、家族との情報共有がとても大切です。「今日はテスト前で勉強に集中したい」「明日は朝練があるから早く寝たい」など、予定や気持ちをきちんと伝えることで、家族も協力しやすくなります。
例えば、「この時間は勉強しているから静かにしてほしい」とお願いすれば、テレビの音量を下げてくれたり、用事を後回しにしてくれたりするかもしれません。お互いに思いやりを持って過ごせると、家庭の雰囲気もよくなり、勉強にも集中しやすくなります。
また、スケジュールを紙に書いて冷蔵庫に貼っておく、リビングのカレンダーに書き込むなど、目で見て分かるようにするとさらに効果的。家族とのちょっとした一言や、メモの共有でスムーズに連携がとれますよ。
応援してもらえる環境を作る
自分が頑張っている姿を見せることで、家族からのサポートも自然と増えていきます。誰かに応援してもらえる環境があると、やる気も長続きしやすいですよね。
私の母は、私が勉強しているときによく「がんばってるね」と声をかけてくれたり、好きなおやつをそっと机の横に置いてくれたりしていました。その小さな気づかいがすごく励みになったのを覚えています。
また、家族と定期的に「最近どう?」と話す時間をつくるのもおすすめです。自分の思いを聞いてもらうことで、気持ちが楽になったり、新しいアイデアが浮かんだりすることも。
家族は、あなたにとって一番身近な応援団です。勉強や部活に対する姿勢を見せながら、時には助けてもらい、感謝の気持ちを伝えることで、より良いサポート関係が築けますよ。
モチベーションを保つコツ

小さな目標を設定する
勉強のやる気を保つためには、「小さな成功体験」を積み重ねることがとても大切です。大きすぎる目標は、達成するまでに時間がかかるため途中でやる気をなくしてしまうこともあります。そこで、「今日は英単語を20個覚える」「数学の問題を3問解く」など、すぐに達成できるような小さな目標を立ててみましょう。
達成できたら、必ず「できた!」という達成感を味わってください。その感覚が次のやる気につながります。私は、やったことにシールを貼るチェックリストを作って、自分の頑張りを“見える化”していました。少しずつシールが増えていくのが楽しくて、「あともう1問やってみよう」と思えるようになったんです。
また、目標は毎日変えてOK。「今日は暗記中心に」「明日は復習メインで」など、気分や予定に合わせて柔軟に設定することで、無理なく継続できます。目標の内容を“選べる”という自由さがあると、やる気をコントロールしやすくなりますよ。
ごほうびを用意する
頑張った自分にちょっとしたごほうびを用意するのも、モチベーションを保つ効果的な方法です。「テストが終わったらゲーム1時間」「勉強が終わったら好きなマンガを読む」など、自分にとって嬉しいご褒美をあらかじめ決めておくと、「あと少しがんばろう!」という気持ちになります。
ごほうびは高価なものでなくても大丈夫。私は好きなお菓子を勉強後に食べたり、好きな音楽を大音量で聞く時間を作ったりしていました。それだけでも「今日もやりきった!」という満足感が得られます。
また、家族や友達に「ここまでできたら褒めて!」と宣言しておくのもおすすめです。他人に認められると、達成感も2倍になりますし、ちょっとした“報告の場”がモチベーションになりますよ。
ごほうびは「やらなきゃ」から「やりたい!」に気持ちを変えるための仕掛け。自分がワクワクできる工夫を見つけて、毎日の勉強を前向きに続けていきましょう。
失敗から学ぼう
うまくいかない日があってもOK
毎日頑張っていても、思うように進まない日って必ずありますよね。疲れて勉強できなかった日、集中できなくて思ったほど進まなかった日、友達とケンカして気分が落ち込んだ日…。そんな日は「自分はダメだ」と思いがちですが、実はそれが自然なんです。
完璧を目指しすぎると、小さな失敗ですぐに落ち込んでしまいます。だからこそ、「今日はうまくいかなかったな」と認めて、次の日に気持ちを切り替えることが大事です。一日うまくいかなくても、翌日からまたやり直せばいいんです。
私も、「今日は何もやる気が出なかった…」と布団の中で反省する日がありました。でも翌朝、「じゃあ今日は1つだけでもやってみよう」と気持ちを新たにすると、不思議とリズムが戻ってきました。失敗は悪いことではなく、成長のための通過点。落ち込むよりも、「よし、次はこうしよう」と前向きに考える力を育てていきましょう。
振り返りノートをつけよう
毎日の終わりに、自分の行動や気持ちを振り返る「振り返りノート」は、失敗から学ぶための大きな味方です。日記のように、「今日はこんなことがあった」「ここがうまくいかなかった」「ここはよく頑張った」と自由に書くことで、自分の成長を実感しやすくなります。
振り返りを続けていくと、「この時間は集中できたな」「前回より早く宿題が終わったな」など、小さな変化にも気づけるようになります。うまくいかなかった理由や改善点も書き出しておけば、次に同じことが起きたときにどうすればいいか、考える材料になります。
私は1日1行でもいいから何か書くようにしていました。できたことをポジティブに書くと、「今日もちゃんと前に進んだ」と自信になり、失敗に対しても優しくなれます。かわいいノートやお気に入りのペンを使うと、書く時間が楽しみになって続けやすいですよ。
大切なのは、振り返りを「反省の時間」ではなく、「成長のための時間」として楽しむこと。続けることで、きっとあなたの心の中に前向きな変化が生まれていきます。
勉強も部活も楽しもう!
どちらかをあきらめなくていい
「勉強か部活、どちらかを選ばないとダメなのかな…」と悩んだことはありませんか?確かに、両方を完璧にこなすのは簡単ではありません。でも、ちょっとした工夫や心がけ次第で、どちらもバランスよく楽しむことは十分に可能なんです。
私自身、中学生の頃にバスケ部に所属していて、毎日ハードな練習の後に家で勉強するのは大変でした。でも、「どちらかをあきらめたくない!」という気持ちを持ち続けていたからこそ、自分なりのペースで工夫を重ね、両立のスタイルを見つけることができました。
大事なのは、「全部を100点満点でやる」ことではなく、「今できるベストを尽くす」こと。今日は部活が大変だったから勉強は少しだけ、逆に部活がない日は集中して勉強する、そんなふうにメリハリをつけるだけでも、心に余裕が生まれます。
両立ができたときの達成感や、自分に自信がついていく感覚は、とても気持ちがいいものです。どちらかをあきらめる必要はありません。あなたも、自分のやり方を見つけて、勉強も部活も思いっきり楽しんでください!
仲間と助け合おう
一人で頑張り続けるのは、ときどきつらくなることもありますよね。そんなときこそ、同じように部活や勉強をがんばっている仲間と助け合うことがとても大事です。
たとえば、勉強でわからないところを友達に教えてもらったり、自分が得意な教科を教えてあげたりするだけで、お互いに理解が深まります。教えることで自分の知識も整理されて、記憶にも定着しやすくなるというメリットもあります。
また、部活の仲間と「今日もがんばろう!」と声をかけ合ったり、休み時間に一緒に勉強したりすることで、やる気が自然とわいてきます。一緒に頑張る仲間がいるというだけで、不思議と前向きな気持ちになれるんです。
私も友達と「次のテスト、一緒に80点以上取ろうね!」と目標を共有して、お互いに問題を出し合ったり励まし合ったりしていました。仲間と協力することで、辛いことも楽しみに変わります。
勉強も部活も、一人でがんばる必要はありません。仲間と一緒に、支え合いながら成長していくことが、きっとあなたの力になりますよ!
中学生におすすめの時間管理アイテム
タイマーやアプリを活用
スマホをうまく使えば、時間管理がぐんと楽になります。おすすめのアプリをいくつか紹介します。
- Studyplus:勉強時間や内容を記録できるアプリ。グラフで可視化されるので、自分がどれだけ勉強しているか一目でわかります。SNS感覚で他のユーザーと励まし合える機能もあり、モチベーションアップに効果的。
- ポモドーロ専用アプリ:集中と休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」を活用するためのタイマー付きアプリ。25分+5分のサイクルで、飽きずに勉強を続けられます。カウントダウン機能がシンプルで使いやすいものを選びましょう。
- Googleカレンダー:予定を時間ごとに書き込めるデジタル手帳のような存在。部活や塾、テスト勉強の計画を色分けして管理すると、自分の一週間の流れが見えやすくなります。
これらのツールを使えば、自分の行動を振り返ることができ、計画的に過ごす習慣が自然と身についていきます。慣れてきたら、時間ごとの「やることリスト」も作ってみるとさらに効果的です。
100均の手帳でもOK!
デジタルだけでなく、紙のツールも根強い人気があります。特に100円ショップで手に入るシンプルな手帳は、中学生にも手軽に取り入れられておすすめです。
予定を書くことで頭の中が整理され、「次に何をすればいいか」が明確になります。また、色ペンやシールで装飾すると、楽しくなって続けやすくなるのもポイント。私もカラーペンを使って、自分だけのオリジナル手帳を作っていました。
さらに、手帳には「その日やったこと」や「良かったこと」など、簡単な振り返りを一言書くスペースを作っておくと、日々の成長を実感できます。書くことには記憶の定着を助ける効果もあるので、勉強と時間管理を両方サポートしてくれる心強いアイテムです。
スマホが使えない環境でも、紙の手帳はいつでもどこでも使えるという強みがあります。デジタルとアナログ、両方をうまく使い分けて、自分に合った時間管理スタイルを見つけてみてください!
まとめ
部活と勉強の両立は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、ちょっとした工夫と意識を変えるだけで、ぐっと楽になります。大切なのは、完璧を求めすぎず、自分なりのペースで続けていくこと。無理をせずに、日々の中で「できたこと」に目を向けていくと、自然と自信もついてきます。
今回紹介したように、目標を明確にしたり、時間を区切って集中したり、スキマ時間を活用したりするだけでも、大きな変化が生まれます。そして何より、自分自身の努力をしっかりと認めてあげることがとても大切です。失敗しても、それは前に進んでいる証拠。転んでも、また立ち上がればいいんです。
毎日、少しずつで構いません。今日からできそうなことを1つ選んで、さっそく実践してみましょう。「タイマーを使って勉強してみる」「目標を紙に書いて貼ってみる」そんな小さな行動から、大きな成果につながっていきます。
あなたなら、きっとできる!これまで頑張ってきた自分を信じて、これからも前向きに一歩ずつ進んでいきましょう。あなたの努力は、必ず未来の力になります。心から応援しています!