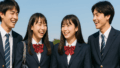はじめに
「勉強しなきゃいけないのはわかってるけど、やる気が出ない…」「どれだけ勉強しても成績が上がらない…」そんな悩み、あなたも抱えていませんか?
勉強は多くの高校生にとって避けて通れない課題ですが、「どうやって勉強すればいいのかわからない」という声もよく耳にします。特に中学生の頃と比べて授業のスピードや内容が難しくなり、ついていけなくなることも。筆者自身も高校に入ってから、これまでの勉強法が通用しなくなって戸惑った経験があります。
この記事では、「中学生でもできる効率的な勉強法」をテーマに、高校生がテストで一歩リードするための具体的なコツを紹介していきます。実際に筆者が中学〜高校時代に試して効果があった方法や、勉強が苦手な友人たちに教えて喜ばれたテクニックも盛り込みながら、できるだけわかりやすく解説していきます。
ポイントは、「難しいことはしない」「誰でもすぐに始められる」「少しの工夫で大きな差がつく」というシンプルな考え方。習慣を変えるのは難しく感じるかもしれませんが、ほんの小さな行動の積み重ねが、確実に結果に表れます。
「勉強って、どうしてもつまらないし、疲れるし、やりたくない」と思っていた自分も、ちょっとした工夫で「やってよかった!」と感じられるようになりました。
さあ、勉強のやり方を見直して、次のテストで一歩リードしましょう!この記事を読み終わる頃には、あなたも「ちょっとやってみようかな」と思えるはずです。
1. 勉強の基本は「計画」にあり
なぜ計画が必要なのか?
勉強をがんばっているのに結果が出ない…そんな人の多くは、「計画を立てていない」「無理なスケジュールを組んで挫折する」パターンに陥っています。頑張っているのにうまくいかないと感じると、やる気も下がりがちですよね。
しかし、あらかじめ計画を立てておけば、
- やるべきことが明確になる
- 勉強時間の管理がしやすくなる
- 達成感を得やすく、モチベーションの維持につながる
- 自分のペースで取り組める安心感が生まれる といったメリットが得られます。
また、計画を立てることで、苦手な科目や単元にもバランスよく時間を配分でき、得意不得意の偏りを防げます。成績アップに直結するのは「継続」と「バランス」。その基盤を作るのが、まさに計画なのです。
効果的な計画の立て方
1週間単位で「何を」「どれくらい」やるかを決めると、日々の勉強に迷いがなくなります。日ごとのタスクが明確になることで、時間をムダにせず、集中して取り組むことができます。
例:テスト2週間前のスケジュール(5教科対応)
- 1週目(月〜金):各教科の基礎固め(ワーク・教科書の復習)
- 1週目(土日):学校配布のプリント・小テストの解き直し
- 2週目(月〜金):過去問・応用問題で仕上げ、模擬テスト形式も有効
- 2週目(土):全体の振り返り、苦手な部分を再確認
- 2週目(日):軽い復習と早めの就寝で本番に備える
ポイント
- 無理なく続けられる量を設定(例:1日90分×2セット)
- 予備日や調整日を用意して「できなかったとき」に備える
- 紙のスケジュール帳か、スマホアプリ(Googleカレンダーなど)を活用
さらに、「今日は英語を30分、数学を45分」など、具体的な時間割にすると実行しやすくなります。私は毎週日曜に次週の勉強スケジュールを立てることを習慣にしています。おかげで、「今日は何しよう?」と迷う時間がなくなり、集中して取り組めるようになりました。
一見手間に思える計画作りも、慣れれば3分で完了します。その3分が、1週間をぐっとラクに、そして実りあるものに変えてくれるのです。
2. 「勉強する場所」にこだわってみよう

自宅より集中できる場所って?
勉強場所を変えるだけで、驚くほど集中力が変わります。自宅での勉強は気軽で安心感がありますが、誘惑が多すぎてついスマホやテレビに手が伸びてしまいがちです。特に家族の話し声や生活音が気になって集中できないという声もよく聞きます。
そんな時は、思い切って「自宅以外の場所」で勉強してみるのがおすすめです。たとえば、「学校の図書室」「図書館」「カフェ」などは環境が整っており、集中しやすい空間が広がっています。また、環境を変えることで気持ちも切り替わり、「勉強モード」に入りやすくなるという心理的な効果もあります。
場所ごとのメリット・デメリット
- 図書室・図書館:静かで集中しやすく、長時間の勉強に最適。ただし、席が空いていない場合もあり、移動の手間がかかることもあります。
- カフェ:ほどよい雑音が「集中の助け」になる人もいます。人の目があることでダラけにくくなるのもメリット。ただし、お金がかかる点や長時間の利用には気を遣う必要があります。
- 学校の教室(放課後):友達と一緒に勉強でき、わからないところをすぐに質問できるのが魅力。ただし、話しすぎたり雑談が多くなったりする可能性もあるため、時間のメリハリを意識しましょう。
他にも、公民館の自習室やコワーキングスペースなどを利用している学生もいます。最近では、Wi-Fiや電源のある自習カフェも増えており、快適に勉強できる場所の選択肢は広がっています。
私は試験前によく市立図書館に通っていました。周りもみんな静かに勉強しているので、「自分も頑張らないと」と自然とスイッチが入ります。お気に入りの席を見つけて、そこで勉強するのが毎回の楽しみでもありました。
大切なのは、自分にとって「集中しやすい環境」を見つけること。一度場所を変えてみるだけで、勉強の効率がグンと上がるかもしれません。いろいろな場所を試して、あなたにとってベストな勉強スポットを見つけてみてください。
3. 科目ごとの勉強法を工夫する
科目によって頭の使い方が違う!
「全部同じやり方で勉強しても成績が伸びない…」と感じている人は、科目ごとに適した勉強法を試してみましょう。教科ごとに求められる力や使う脳の働きが違うため、それに合わせて工夫することで効率がぐっと上がります。
英語:
- 音読と書き取りで記憶に定着
- 単語帳は毎日10分ずつ、寝る前や通学中のスキマ時間を活用
- シャドーイング(音声を聞きながらマネして発音)でリスニング力と発音力を同時にアップ
- 英文をノートに書き写して文法チェックも忘れずに
英語は「読む・書く・聞く・話す」の4技能をバランスよく鍛えることが大切。私は英語の成績が伸び悩んでいた時、毎日音読を取り入れたことで、リスニング力もアップし、長文がスラスラ読めるようになりました。さらに、シャドーイングも取り入れたら、英語の授業がぐっと楽しくなったのを覚えています。
数学:
- 解き方の「流れ」を理解する(答えだけでなく途中式にも注目)
- 解けなかった問題に印をつけて復習(解説を読んで理解し、再度チャレンジ)
- 同じタイプの問題を繰り返し解くことで公式やパターンが自然に身につく
- ノートには自分の間違えたポイントをメモしておくと次に活かしやすい
数学は「数をこなす」ことも大事ですが、「なぜそうなるのか」を理解することで応用問題にも対応できるようになります。私は、間違えた問題は赤ペンで「なぜ間違えたか」を書き出して、次に同じミスをしないようにしていました。
理科・社会:
- 図や表を使ってイメージで覚える(特に地理や生物は図解が有効)
- 語呂合わせやストーリーで記憶(歴史の年号や元素記号など)
- 暗記だけでなく、「なぜそうなるのか?」という背景知識にも触れる
- ノートやルーズリーフにまとめ直して、自分だけの「オリジナルまとめノート」を作る
理科・社会は「覚えることが多くて苦手」という人も多いですが、視覚的に理解するとぐっと頭に入りやすくなります。私は歴史の年号を歌にして覚えたり、理科はイラストを描いてイメージで記憶したりしていました。覚えやすいだけでなく、楽しくなるのもポイントです。
それぞれの科目に合った方法で取り組むことで、「勉強が苦にならない」「結果が出るから続けたくなる」と良いサイクルが生まれます。自分に合ったスタイルを見つけて、少しずつでも続けていきましょう!
4. 「復習」のタイミングを見直そう
人は忘れる生き物
エビングハウスの忘却曲線によれば、人は学んだことを1日で約7割忘れてしまうそうです。つまり、せっかく一生懸命勉強しても、何もしなければ次の日にはそのほとんどを忘れてしまっているということ。
でも安心してください。これは人間の脳の仕組みであり、決してあなたの記憶力が悪いというわけではありません。この“忘れる”という性質に逆らうのではなく、うまく付き合っていくことが大切なんです。その鍵が「復習のタイミング」。
効果的な復習スケジュール
- 学んだ当日:軽く見直し(10分)
- ノートをざっと読み返し、キーワードに線を引く
- 「今日のポイント3つ」を自分の言葉でまとめてみる
- 翌日:ノートや問題を再確認(30分)
- 実際に問題を解いてみて、理解が浅い部分をチェック
- 間違えたところは赤で解説メモを書き込む
- 1週間後:応用問題にチャレンジ
- 類題や応用問題で本当に理解できているか確認
- 学習した単元全体をまとめ直して、知識の定着を強化
この「1日→翌日→1週間後」のサイクルを意識するだけで、記憶の定着率は格段に上がります。また、繰り返すうちに「前にやったから少し覚えてる!」という実感が出てきて、それが自信にもつながります。
私は理科が苦手だったのですが、授業の後すぐに内容をまとめ直し、次の日に教科書の図と照らし合わせながら再確認、そして1週間後に関連問題を解くという3ステップを続けたところ、テストの点数が20点以上アップしました!
「忘れる前に復習する」という流れを習慣にするだけで、勉強がグンとラクになります。難しく考えず、まずは当日10分の見直しから始めてみましょう。
5. 「スマホ」との付き合い方を工夫する

スマホ=悪者じゃない!
「勉強中にスマホをいじってしまう…」という悩みは多いですが、使い方次第でスマホは強力な味方になります。ただ、SNSやゲームなど誘惑が多いのも事実なので、「どう使うか」がとても大切なんです。
「スマホ=悪」と決めつけて無理に我慢すると、かえってストレスが溜まり、勉強の効率が落ちることもあります。そこでおすすめなのが、「スマホをあえて勉強の味方に変える」方法。これを意識するだけで、集中力や継続力が驚くほど変わってきます。
活用法
- タイマーアプリでポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)を活用して、短時間で効率よく集中
- 英単語アプリ(mikanなど)やYouTubeの勉強チャンネル(スタディサプリ、Try ITなど)でスキマ時間に学習
- 勉強時間記録アプリ(Studyplusなど)で「見える化」して達成感を味わう
- ボイスメモで自分の声を録音して英単語や歴史のポイントを確認
- スクリーンショットで参考資料や板書を保存して、復習に活用
私自身、スマホで勉強時間を記録し始めたら、「今日は何時間できた!」という小さな達成感が毎日のモチベーションにつながるようになりました。また、YouTubeの解説動画でつまずいた問題が一気に理解できた経験もあります。
ただし、通知が多いSNSやゲームアプリは大きな誘惑。勉強中は通知を切る、アプリを一時的に非表示にする、時間制限を設定するなどして、集中を邪魔されない工夫をしましょう。
私はiPhoneの「集中モード」を使って、通知を完全にカットしています。勉強専用のホーム画面を作って、使うアプリだけ表示させるようにしたら、集中力が全然違いました。スマホとうまく付き合えば、あなたの学びを何倍にも強くしてくれる心強い相棒になりますよ。
6. 「目標」を明確にする
なぜ頑張るのか?を考える
勉強を続けるうえで、「なぜ自分は頑張るのか?」という理由や動機を持つことはとても重要です。ただ漠然と「勉強しなきゃ」と思うだけでは、モチベーションが続かず、ついダラダラしてしまいがちです。
明確な目標を持つことで、日々の勉強に意味が生まれ、「今日もやろう!」という前向きな気持ちになれます。また、目標があると、自分の成長を実感しやすくなり、やる気を持続しやすくなります。
目標の例
- 数学で80点以上を取る(前回は70点だったから+10点)
- 学年順位を20位上げる(前回50位→今回30位を目指す)
- 志望校に合格する(入試科目の得点目標も具体的に設定)
- 英単語を毎日20個覚えて、1週間で140語習得する
- 毎日最低でも30分間は勉強する習慣を身につける
「目標は大きく」とよく言いますが、最初から高すぎる目標を立ててしまうと、達成できなかったときに落ち込む原因になります。まずは小さなゴールを積み重ねて、ステップアップしていくのがコツです。
モチベ維持のコツ
- 小さな目標を設定して達成感を味わう(例:「今日は英単語30個覚える」など)
- ご褒美を用意する(テストが終わったら好きなアニメを一気見する、好きなスイーツを食べるなど)
- 目標を紙に書いて貼る、スマホの待ち受けにするなど「視覚化」する
- SNSで宣言してみると、ちょっとしたプレッシャーが力になることも
私は「学年10位以内に入る」と紙に書いて机に貼っていました。毎日その目標を目にすることで、自分の意識が自然と高まり、勉強への姿勢が変わっていったのを覚えています。また、途中でくじけそうになったときも、その目標が背中を押してくれました。
目標は、勉強に取り組む“意味”を与えてくれる大切な存在です。まだ明確な目標がない人も、まずは「今よりちょっと良くなること」を意識して、小さな目標から始めてみましょう。
7. 「睡眠・食事・運動」も勉強の一部
生活習慣を整えることの大切さ
どれだけ一生懸命勉強しても、体調が悪ければ集中力はガクッと下がってしまいます。実は、「よく眠る」「きちんと食べる」「体を動かす」ことは、成績アップに直接つながるとても重要な要素です。つまり、勉強の“土台”になるのが、生活習慣なのです。
睡眠不足や栄養バランスの偏った食事、長時間座りっぱなしで体を動かさない生活は、思考力や集中力を鈍らせてしまいます。逆に、規則正しい生活を送ることで、頭もスッキリし、勉強効率が飛躍的にアップします。
ポイント
- 睡眠:最低6〜7時間はしっかり眠ること。深夜までの勉強は一見頑張っているように見えますが、かえって記憶の定着を妨げる原因になります。特に22時〜2時は「脳のゴールデンタイム」と呼ばれ、記憶を整理するのに最適な時間帯。可能であれば、この時間には寝ておくのが理想的です。
- 食事:朝食は必ず食べましょう。脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足すると、午前中の集中力が大きく低下します。バナナやご飯、パンなどの炭水化物をしっかり摂るのがおすすめ。また、昼食と夕食も栄養バランスを意識して、偏らないように心がけましょう。
- 運動:長時間勉強すると、体がこわばって血流も悪くなりがち。軽いストレッチや散歩、ラジオ体操などで体をほぐすことで、脳への血流が良くなり、集中力が回復します。特に、勉強の合間に5〜10分のリフレッシュ運動を取り入れると、気持ちの切り替えにもなり効果的です。
私自身、テスト前に夜遅くまで詰め込み勉強をしていた時期がありましたが、結局翌日眠くて集中できず、思うような成果が出ませんでした。それ以来、夜はしっかり寝て、朝に復習するスタイルに切り替えたところ、頭がスッキリして内容もよく覚えられるようになったんです。
「生活習慣なんて関係ない」と思いがちですが、実はそこを見直すだけで、勉強の質がぐんと高まります。無理なく続けられる範囲で、まずは睡眠・食事・運動のどれか1つから意識してみましょう。それだけで、あなたの勉強がもっとラクに、もっと効果的になるはずです。
8. 「仲間」と一緒に勉強する

ひとりより、みんなで
勉強はひとりでもできるけれど、仲間がいればもっと効率よく、もっと楽しくなることがあります。特にやる気が出ないときや集中が続かないとき、仲間の存在は大きな力になります。
友達と一緒に勉強することで、新たな発見があったり、お互いに刺激を受けたりできるのが大きなメリットです。自分では気づかなかった視点を得たり、理解が深まったりするのも共同学習の魅力です。また、「みんな頑張っているから、自分もがんばろう」と思える心理的な効果も見逃せません。
おすすめのやり方
- わからないところを教え合う(教えることで自分の理解も深まる)
- クイズ形式で問題を出し合う(ゲーム感覚で楽しく学べる)
- 勉強時間を一緒に決めて集中タイム(タイマーで区切って集中→休憩)
- 週1回の勉強会を開いて、課題の進捗を共有する
- グループチャットで勉強報告を送り合う
例えば、私は仲の良い友達3人と「オンライン自習室」を作って、夜1時間だけZoomで一緒に勉強していました。それぞれの目標を話してからスタートするので、気持ちが引き締まり、自然と集中モードに入れます。不思議とサボりにくくなり、習慣化できたのはこの仲間のおかげです。
勉強仲間は、競争相手というより「一緒に成長していく仲間」。気軽に相談できる関係だからこそ、苦手な部分も話しやすく、効率よく克服できました。特に受験期には、このような勉強仲間の存在が心の支えにもなります。
学校の友達でも、SNSの勉強アカウントで知り合った人でもOKです。あなたもぜひ、気の合う仲間を見つけて一緒に勉強してみてください。きっとひとりでは得られないパワーを実感できるはずです。
9. 「苦手克服」は小さく始める
苦手な教科、どうする?
「どうせ無理」「どうせできない」と諦めてしまいがちな苦手科目。でも、ほんの少しの成功体験で、勉強への気持ちは大きく変わります。苦手科目こそ「小さな一歩」が重要。最初から完璧を目指すのではなく、「できた」を少しずつ積み重ねることで、自然と自信とやる気が湧いてきます。
特に、苦手意識が強い場合は、「やらなきゃ」と思うだけで気が重くなりがちです。そんな時こそ、無理のないスタートで、「やってみたら意外といけるかも」と思える体験を作るのがポイントです。
ステップ例
- 問題集の一番簡単な問題からスタート(成功体験を得やすい)
- わかったところに◎をつけて自信をつける(「できた」が見える化)
- 毎日5分だけでも触れる(短時間でも「続ける」ことが大切)
- 苦手な単元を1つに絞って、1週間かけてじっくり取り組む
- 成果が出たら小さなご褒美を用意してモチベアップ
たとえば、私は中学時代、数学が大の苦手でした。特に関数や図形の応用問題になると、手が止まってしまい、自信もなくしていました。でも、「とにかく毎日計算問題だけでもいいから続けよう」と決めて、たった5分の取り組みを始めました。
すると、少しずつ「できる問題」が増えていき、「あれ、ちょっとわかるかも」と思える瞬間が増えてきたんです。やがて、応用問題にも自然とチャレンジするようになり、気づけば数学が怖くなくなっていました。
苦手克服に必要なのは、「才能」や「長時間の勉強」ではなく、「最初の一歩」を踏み出すこと。そして、その一歩を習慣に変えることです。どんなに小さな努力でも、続ければ必ず力になります。
10. 「アウトプット」で本物の力に変える
インプットだけじゃもったいない!
勉強した内容を「人に説明する」「問題として出す」などのアウトプットをすると、記憶がより強固になります。実際、脳は「教える」「使う」という行動を通じて、学んだことを長期的に記憶に残す仕組みになっています。
また、自分で説明することで「理解できていなかった部分」に気づくことができます。これは、ただ読む・聞くといった受け身の学習では得られない大きなメリットです。アウトプットはまさに“知識を本物の力に変える作業”と言えるでしょう。
おすすめの方法
- 教科書の内容を友達に教える(口に出すことで定着が深まる)
- 自作問題をノートに作ってみる(試験形式に近い思考練習になる)
- SNSで勉強アカウントを作って発信(勉強記録をシェアすることで継続のモチベに)
- 家族に今日習ったことを3分で説明してみる(聞き手が分かりやすいかも意識)
- 解いた問題をブログ形式でまとめてみる(解説力がつく)
私もInstagramで勉強記録を投稿していたら、フォロワーから「自分もがんばろうと思った」とコメントをもらい、逆に励まされました。そのうち、自分の記録を見るのが習慣になり、「また今日も投稿したいから勉強しよう!」という気持ちが自然と芽生えるようになったんです。
アウトプットは、自分の理解を深めるだけでなく、誰かを元気づけたり、学びの輪を広げたりすることもできます。小さな発信や説明が、あなたの学力も周囲のモチベーションも高めてくれる大切な一歩になります。ぜひ今日から、ひとつでもアウトプットを意識してみてください。
まとめ|今日からできる一歩を踏み出そう!
勉強って、やり方次第で「しんどいもの」から「楽しくなるもの」に変わります。今回紹介した方法は、どれも中学生でも実践できるものばかり。つまり、高校生であるあなたが本気で取り組めば、その効果はもっと大きく、テストでも大きな差をつけることが可能です。
この中のどれか一つでも、「これならできそう」と思えるものがあったなら、それがあなたにとっての第一歩です。たとえ今日すぐに全部できなくても、焦る必要はありません。大切なのは、まず行動に移すこと。そして、小さな成功体験を積み重ねていくことです。
「続けること」が成功の秘訣です。毎日5分でもいいから、自分の成長のために時間を使ってみましょう。やがてそれが習慣となり、自分でも驚くほどの力に変わっていきます。結果が出るまでには少し時間がかかるかもしれませんが、そのプロセスも自分を育てる大切な時間です。
最後に一言。完璧を目指さなくても大丈夫。むしろ、最初から完璧を求めすぎると続かないものです。大切なのは「昨日よりちょっとだけ前に進むこと」。昨日より1問多く問題を解けた、昨日より5分長く集中できた——その積み重ねが未来を変えます。
今日からできることを、ひとつだけでいいので始めてみてください。あなたの努力は、きっと未来の自分を助けてくれます。そしてその未来は、あなた自身の手でつくっていくものです。自信を持って、前に進んでいきましょう!