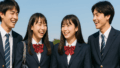はじめに
「よし、勉強するぞ!」と意気込んで机に向かったのに、気がついたらスマホを手に取り、SNSをチェックしたりYouTubeで動画を見たりしていた…そんな経験、一度はありますよね?特にテスト前は、焦りやプレッシャーからか、ついつい現実逃避のようにスマホをいじってしまうことがよくあります。
この記事では、そんなテスト期間中にありがちな「高校生 あるある」をテーマに、誰もが一度は経験したことがありそうな行動や、ついついやってしまうクセ、そしてそれに対するちょっとした工夫や対処法も紹介していきます。中には笑えるような「あるある」もあるかもしれませんし、「ああ、これ自分のことだ…」と共感できる内容もきっとあるはずです。
筆者自身も、高校時代に何度も同じようなことを繰り返してきた身。そんな体験談も交えながら、みなさんと一緒に「勉強あるある」を楽しんでいけたらと思っています。
「自分だけじゃないんだ!」とホッとしたり、「じゃあ今日からちょっと変えてみようかな」と前向きな気持ちになれたりするきっかけになれば嬉しいです。最後まで楽しく読んでいただける内容になっているので、ぜひリラックスして読み進めてみてくださいね!
1. スマホは1分だけ…のはずが1時間
気づけばタイムスリップ
「ちょっとだけSNSチェックしよ〜」と思ってスマホを開いた瞬間、気づいたら1時間経っていた…これほど多くの高校生が共感する「高校生 あるある」はなかなかありません。通知が来ていないか気になってロック解除、そこからTikTokを少しだけ見るつもりが、次々と流れてくるおすすめ動画の誘惑に抗えず、あっという間に時間が過ぎてしまうんです。
Instagramで友達のストーリーを見たり、「いいね」された投稿をチェックしたりしているうちに、まるで時間がワープしたかのような感覚になります。「あと1個だけ…」と見続けてしまうのは、アプリの設計上、次々と新しい情報が出てくる仕組みになっているからでもあります。
自分の体験談
僕も高校時代、「1問解いたらスマホ休憩OK」という“マイルール”を作っていたんですが、休憩時間が勉強時間を上回ってしまう日も多々ありました(笑)。最初は「5分だけ」だったはずが、「あ、これ面白そう」「これだけシェアしとこ」とどんどん時間が延びていき、結局、参考書を開いたのは数ページのみ…ということもよくありました。
特にテスト前は、「他の人も同じように頑張ってるのかな?」とSNSで他人の様子が気になって見てしまうこともあり、それが逆にプレッシャーになってしまうという悪循環に陥ったこともあります。
対策のヒント
- タイマーを使ってスマホ使用時間を“見える化”する(例:15分間だけ)
- 勉強中は別室やカバンの奥にスマホをしまって物理的に距離を取る
- アプリごとに使用制限を設定できる「スクリーンタイム」などの機能を活用する
- 勉強のご褒美としてスマホを使うのではなく、スマホの時間に明確な目的を持たせる
- SNSアカウントを一時的にログアウトする、通知を完全オフにする
スマホは便利なツールですが、使い方次第で勉強の大敵にもなります。自分に合った制限方法を見つけて、スマホとうまく付き合っていきましょう。
2. 勉強しようとすると急に掃除したくなる
なぜか部屋が気になる
勉強を始めようと決意して机に向かった瞬間、「机の上がちょっと散らかってるな」「まずは整理してからじゃないと集中できないな」と、気づけば掃除モードに突入。最初は机の上だけだったのが、引き出しの中、ベッド周り、床…とどんどん範囲が広がっていき、いつの間にか“勉強”ではなく“模様替え”のような状態に(笑)。
掃除を始めると、意外といろいろ気になってしまうもの。「このプリント、何だっけ?」「この本、懐かしい〜」と、思い出の品や過去のノートを発掘しては手を止め、思考はどんどん過去へトリップ。結局、その日は教科書を開かずに終わってしまった…なんてこともよくあります。
実は“逃避行動”かも
この現象、実は心理学的にも「逃避行動」と呼ばれるものの一種。脳はストレスやプレッシャーを感じると、それを回避するために別の行動に走る傾向があります。掃除はその代表例。視覚的にもスッキリするし、手を動かしているうちに“何かをやっている感”が得られるため、満足感も得やすいんです。
僕自身も、「まず部屋を整えないと集中できない派」でしたが、気がつけば2時間掃除して、疲れて昼寝してしまった…なんて日がありました。でもその時はなぜか「今日はいいことしたな」と妙な達成感があるんですよね(笑)。
対策のヒント
- 勉強を始める前に5分だけ掃除タイムを設定して、それ以上はやらない
- 掃除したい衝動が来たら、メモに書いて後でやる
- 勉強場所を変えて“掃除の誘惑”から距離を置く
掃除が悪いわけではなく、むしろ環境を整えるのは大切なこと。でもそれが勉強の妨げになるなら、ほどほどのバランスが大切です。掃除は勉強の合間のリフレッシュとして取り入れるくらいがちょうどいいかもしれませんね。
3. ノートをまとめ直したくなる

見た目重視で満足してしまう
「テスト前にノートを綺麗にまとめ直す」…これは多くの高校生が一度はやってしまう“あるある”行動。気持ちはすごく分かります。自分の理解を深めようという思いもあるし、ノートが綺麗にまとまっていると、何だかそれだけで安心しますよね。でも実際は、まとめる作業に時間と労力をかけすぎてしまい、肝心の“内容を覚える”ことが疎かになってしまうという本末転倒な結果になることも少なくありません。
僕自身も、テスト直前に「やっぱりノートをきちんと整理しよう」と思って、過去の授業ノートを1から書き直し始めたことがあります。その結果、夜遅くまでかかってしまい、次の日は眠気との戦い…。しかも、まとめて満足してしまって内容の定着はイマイチという、なんとも悲しい結末を迎えた経験が何度もあります。
色ペン地獄に陥る
- ペンの色分けにこだわってしまい、「見出しは赤」「大事なところはオレンジ」「補足は青」…と色指定が細かくなりすぎる
- 見出しにマーカーや装飾を使って“映えるノート”を目指す
- イラストや図まで描いて芸術作品のようなノートを作成
- 結果として、まとめに3時間以上かけたけど中身は頭に入ってない
これはまさに「ノート作りに全力投球」してしまったがゆえの“あるある”。見た目の達成感はあっても、実際に点数にはつながらないことが多いです。
どう使えば効果的?
もちろん、ノートをまとめ直すこと自体が悪いわけではありません。大事なのは、目的が“覚えるため”になっているかどうかということ。まとめた後に声に出して読んでみたり、自分でクイズ形式にして解き直してみたりすることで、ノートが「勉強の道具」として生きてきます。
時間がないときは、まとめ直すよりも重要な箇所にマーカーを引くだけ、付箋でポイントをメモするだけでも十分。手段と目的をしっかり意識して、時間の使い方を工夫してみてくださいね。
4. 友達とのLINEが止まらない
勉強相談がいつの間にか雑談に
「ここって出るかな?」と何気なく友達に聞いただけのつもりが、いつの間にか雑談モードに突入してしまう…。そんな流れ、あるあるですよね。最初は真面目な勉強の話をしていたはずなのに、「この前の体育でさ〜」「あの先生ってさ…」と話題が脱線。
そして気づけば、恋バナになったり、週末の予定の相談に移ったり、推し活の話に花が咲いたりして、気がつけば1時間以上LINEをしていたなんてことも。特にテスト前はちょっとした不安や緊張を共有したくて、誰かと話したくなるんですよね。
筆者もよくありました。「この問題難しくない?」と送ったLINEに返ってきたのが「てかさ〜今日さ…」という始まりで、そこから長文ラリー開始(笑)。気がつけばもう夜10時。肝心の問題は1つも解いていない、なんて日もざらにありました。
対処法
- 勉強専用のグループチャットを作って、雑談と完全に分けるようにする
- あらかじめ「〇〇時〜〇〇時までだけLINEで質問OK」と時間を区切る
- 雑談が始まりそうなときは「今勉強中だから後で話そうね」と自分から切り上げる勇気を持つ
- 通知を一時的にオフにして、集中タイムを作る
- どうしてもLINEしたい時は「◯分だけ」と時間を決めてアラームをセット
友達とのやりとりは楽しくてリフレッシュにもなりますが、テスト前は“やりすぎ注意”。連絡を取りつつも、お互いに高め合えるようなやり方を見つけていけるといいですね。
5. 眠気との戦いに敗れる
教科書=睡眠導入剤?
テスト前日、「今日こそ夜遅くまで頑張るぞ!」と意気込んで教科書を開いたはずが、数分後には目がとろん…。まるで魔法にかかったかのように眠気が襲ってきます。そう、教科書には“睡眠導入剤”的な力があるんじゃないか?と思ってしまうほど、高確率で眠くなるんです。
特に難しい数式や長い文章が並んでいるページを読むと、集中力が削られ、脳が自然と「今はもう休んでいいよ」と言っているかのような状態に。ベッドがすぐそばにある環境では、その誘惑に勝てる高校生はなかなかいません。
僕もよく、「今日は3時間やる!」と決意していたのに、30分後にはうつ伏せでノートを枕に爆睡していたことが何度もあります。気がついたら明け方で、「あれ?何も覚えてない…」という残念な朝を迎えるパターン。これもまさに「高校生 あるある」ですよね。
眠くなる原因は、単に疲れているだけでなく、夜の脳はインプットに不向きな時間帯であることも影響しています。また、長時間同じ姿勢でいると血流が悪くなり、より眠気が強くなるんです。
自分なりの対策
- 明るい照明を使って、部屋を昼間のような明るさに保つ
- 座ってではなく、あえて立って音読することで眠気を吹き飛ばす
- 時間を区切って「25分勉強+5分休憩」のポモドーロ・テクニックを試す
- 仮眠を取りたいときは、15〜20分程度に留めて深い眠りに入らないようにする
- コーヒーや紅茶などのカフェインを少し摂る(ただし飲みすぎ注意)
どうしても眠い時は無理に起き続けるより、思い切って短時間寝てリフレッシュする方が結果的に効率的です。「眠気=怠けている」ではなく、脳の限界サインとして受け止めて、上手に付き合っていきましょう。
6. やる気が出るのは夜中

なぜか深夜テンションでやる気爆発
「なんか今ならいけそう!」と感じる瞬間が、なぜか夜中に訪れることってありませんか?それまではダラダラしてたのに、突然やる気スイッチが入って、問題集を開いて一気に集中モード突入。静かな夜の空気、周囲の雑音ゼロ、LINEも鳴らない、まるで自分だけの勉強空間が出現したような気分に浸れるんですよね。
僕も「この時間こそが最強タイムなんじゃないか?」と思ったことが何度もあります。深夜のテンションで、一気に英単語を暗記したり、数学の難問を解いたりして、「これ、日中よりはかどってるんじゃ?」と錯覚するくらいの集中力を発揮できたりするんです。
でも、その代償は大きい。翌朝、目覚ましに気づかず寝坊、もしくはギリギリ起きられてもボーッとしたまま学校へ。授業中に眠気で意識が飛ぶ…というのが、深夜学習の“お決まりの結末”なんですよね。
バランスが大事
夜型が合う人もいるのは確かです。自分の集中できる時間帯が夜であるなら、それをうまく活かすのも一つの手。ただし、生活リズムを大きく崩すと体調不良を招き、結局パフォーマンスが落ちてしまうので注意が必要です。
夜型勉強を取り入れるなら、せめて深夜2時までには終える、翌朝は無理に早起きしないなど、無理のない範囲でルールを決めておくのがおすすめ。また、週末だけ夜型にして、平日はなるべく通常の生活リズムをキープするという“ハイブリッド型”も意外と効果的です。
いずれにしても、やる気が出る時間帯を自分なりに見極めて、体と心のバランスを取りながら効率よく勉強できるスタイルを見つけていきましょう。
7. 勉強計画だけ立てて満足
計画表作りが楽しい
カラフルなスケジュール表を作って「やった気」になるのは、まさに「高校生 あるある」の代表例。ノートやアプリで完璧な1週間の勉強スケジュールを組み立てて、「今回は本気だ!」と気合を入れるものの、実際にその通りに行動できたかというと…うーん、微妙という人も多いのでは?
僕自身も、見やすいようにマーカーで色分けし、「英語30分→数学1時間→休憩→理科」などと書いて満足してしまい、その後は結局スマホを触ってしまったり、気づいたら計画にないことをしていたりと、理想と現実のギャップに何度も悩まされました。
計画表を作るときって、なんだか勉強できる人になった気がして、テンションも上がるんですよね。でも、計画だけ立てて行動しないと、ただの“自己満”になってしまいます。しかも、ぎっしり詰め込んだ計画は、ちょっと崩れるだけで「もういいや」と諦めがちになるリスクもあります。
効果的な使い方
- 1日の中で「やる時間」を具体的に決めて、どのタイミングに何をするかイメージしやすくする
- 計画を詰め込みすぎないように、「予備時間」や「遊びの時間」もあえて入れて余裕を持たせる
- 小さな単位で目標を立てて、達成したらシールやマークなどで“視覚的達成感”を得る仕組みにする
- 毎日夜に「今日どうだったか」を簡単に振り返って、計画の見直しを習慣にする
- あえて手書きで書くことで、脳にしっかり残るようにする
勉強計画は「やらなきゃいけないことを整理する」ためのツール。完璧な計画よりも、「できることを、できる範囲で、継続していくこと」が何より大事です。無理なく、自分のペースに合わせた計画を立てて、少しずつ実行していく習慣をつけていきましょう!
8. ご褒美を決めすぎる
モチベアップ作戦が裏目に
「この単元が終わったらYouTube見てOK!」「テストが終わったら欲しかったゲームを買う!」など、自分へのご褒美を設定するのは、やる気を引き出す方法としてよく使われています。特にやる気が出ないときは、「あと少しで楽しめる」と思うことで乗り越えられることもあります。
でも、このご褒美作戦、うまくいく時ばかりじゃありません。ご褒美を考えることが楽しくなりすぎて、肝心の勉強そっちのけになってしまったり、「これやったらあれもOK、ついでにこれも…」と、どんどん条件がゆるくなっていって、最終的には「ご褒美が主役、勉強はついで」みたいな状態になってしまうこともあるんです。
僕も実際、「英語の課題終わったら30分ゲーム」と決めていたのに、課題を終わらせる前からゲームを起動して「ちょっとだけ…」とやり始め、結局2時間プレイして後悔したことがあります。最初はご褒美だったはずのものが、いつの間にか“誘惑”になってしまっていたんですね。
ほどほどが大切
ご褒美はモチベーションを高める手段としてとても有効です。でも、あくまで“勉強した結果のご褒美”であって、主役にしてしまうと本末転倒になってしまいます。
効果的なご褒美の使い方としては、
- 小さな目標ごとに、短時間のご褒美を設定する(例:「数学1ページ終わったら5分休憩」)
- ご褒美の前後に「振り返り」タイムを入れて、成果を実感する
- ご褒美を“時間”よりも“体験”にする(例:「終わったらお気に入りの音楽を聴く」など)
大事なのは、自分の中で“メリハリ”を持つこと。ご褒美に頼りすぎず、達成の喜び自体をモチベーションにできるようにしていけたら、もっと勉強が楽しくなるかもしれませんよ。
9. 勉強できるカフェに憧れる

かっこいいけど意外と集中できない?
「スタバで勉強してる自分、イケてる!」と、なんとなく雰囲気に酔いたくてカフェに向かう高校生も多いはず。周囲の大人たちが静かにノートPCを広げて作業している様子を見て、「自分も頑張らなきゃ」という気持ちになる…それ自体は素晴らしいことです。
ただ実際のところ、カフェは勉強に最適な環境とは限りません。コーヒーマシンの音、BGM、周りの会話、出入りの多さ、ふと目に入るおしゃれなお菓子など、注意をそらすものが意外と多いんですよね。また、長時間の利用には気を使ったり、飲み物代もバカにならなかったりと、継続的な勉強にはコスパ面でも悩みが出てきます。
僕も何度か「今日はカフェで勉強しよう!」と出かけて、参考書とノートを広げたものの、30分後には周りの話し声やスマホに気を取られて集中力が切れてしまった経験があります。しかも「せっかくだし、ちょっとだけスマホ見よう…」が長引き、結局、雰囲気を味わっただけで帰宅という日もありました(笑)。
カフェで勉強するのが向いている人も確かにいますが、大切なのは“自分に合った場所”を見つけること。静かで集中しやすく、気兼ねなく長時間滞在できる場所が、自分にとってのベストな勉強スポットです。
自分に合う場所を知ろう
- 静かな図書館:周囲も勉強している空気があり、集中しやすい環境。
- 自宅の一角:自分のペースで自由に使える。誘惑対策がカギ。
- 学校の空き教室:放課後に使える場所があれば、集中力も保ちやすい。
- 地元の公民館や学習室:意外と穴場で静かな場所も多い。
どこで勉強するにしても、自分が落ち着いて取り組める環境を見つけることが何より大切です。見た目や雰囲気に流されず、自分にとって本当に集中できる場所を選びましょう。
10. 過去問を後回しにしがち
重要なのに最後まで手が回らない
「まだ時間あるし、今は基礎を固めよう」と思っているうちに、気づけばテスト前日。そこでようやく「あっ、過去問やってなかった!」と焦る…これもかなりの「高校生 あるある」です。
過去問って、なんだか“最終確認用”みたいなイメージがありますよね。でも実際は、もっと早い段階から活用することで、理解度のチェックや勉強の方向性の見直しができる非常に重要な教材なんです。
僕も何度か、「一通り勉強してからやろう」と後回しにしていたことがあります。でも、いざ過去問を解こうとしたら、想定と違う形式で出題されていてパニック…。もっと早くやっておけば傾向がつかめたのに、と後悔した経験が何度もあります。
過去問の大切さ
- 出題傾向が分かる:よく出るテーマや問題の型を知ることで、効率的に対策が立てられる。
- 時間配分の練習になる:本番さながらの時間設定で解くことで、自分のペース配分を調整できる。
- 実戦形式で理解度チェック:覚えた知識が“使える”かどうかを確認でき、苦手が明確になる。
- 自信につながる:実際に解いてみて「できた!」という経験が、自信とモチベーションを生む。
どう活用する?
- 早めに1回解いて、傾向を把握してから勉強計画を立てる
- 一度解いた後は、解けなかった問題だけを繰り返す“弱点ノート”を作る
- 定期的に本番と同じ時間で模擬テスト形式で解く
- 友達と答え合わせして、解法を共有するのも効果的
過去問は“最後にやるもの”ではなく、“最初から使うべき道しるべ”。早めに手をつけて、効率よく学習を進めていきましょう!
11. いざとなると参考書を買いたくなる
新しい参考書=やる気の象徴
「この参考書、めちゃくちゃ分かりやすそう!」「表紙のデザインもかっこいいし、今度こそ頑張れそう!」と、つい新しい参考書を買いたくなる衝動に駆られることってありませんか?書店で平積みされている参考書を手に取って、パラパラと中を見た瞬間、「これなら自分もできるかも」とワクワクしてしまう感覚は、多くの高校生が共感できるところだと思います。
僕もテストが近づくたびに、新しい参考書を探しに本屋に行ったり、ネットで口コミをチェックしたりして、「これがあれば大丈夫」と安心していました。でも実際に買った後は、最初の数ページだけ読んで満足し、棚に並べて“積ん読”状態になることがほとんど。ページをめくるだけで「勉強した気分」になってしまうんですよね。
特に、表紙に「〇〇高校合格!」とか「これ1冊でOK!」なんて書かれていると、「これなら成績アップ間違いなし」と思い込んでしまいがち。でも、本当に大事なのは「どの参考書を使うか」ではなく、「どう使いこなすか」なんですよね。
本当に必要?
参考書を買う前に、まずは今自分が持っている教材を見直してみることが大切です。実は必要な情報がすでに手元に揃っている場合がほとんど。解いていないページや、理解が浅いところをもう一度やってみるだけでも、十分力がつきます。
もしどうしても新しい参考書が欲しいなら、「なぜその参考書が必要なのか」を自分に問いかけてみましょう。解説の丁寧さ、問題のレベル、解法のスタイルなど、自分に合っているかをきちんと確認することが大切です。また、買ったからには「1日〇ページ」「2週間で1周」など、具体的な目標を立てて活用していく意識も欠かせません。
“新しい=効果的”とは限らない。今あるものを大切に、そして使い倒す意識が、結果的には一番の近道になるかもしれませんよ。
まとめ
いかがでしたか?「高校生 あるある」として紹介した行動の数々、自分にも思い当たることがあったのではないでしょうか?スマホをいじってしまったり、掃除を始めてしまったり、つい計画倒れになってしまったり…。どれも一見ネガティブに見える行動ですが、それだけ日々の生活や学習に向き合っている証拠でもあります。
こうした“あるある”は、自分ひとりだけがしているわけではなく、誰もが通る道です。悩んでいるのは自分だけじゃないと気づくだけでも、ちょっと気が楽になりますよね。そして大切なのは、そうした“あるある”に対して、自分なりの対策や工夫を見つけていくこと。完璧じゃなくていいんです。小さな改善を積み重ねることが、やがて大きな変化につながります。
最後に一つお伝えしたいのは、「焦らなくて大丈夫」ということ。勉強はマラソンのようなもので、一時的にサボったり、遠回りしたりしても、諦めなければ必ず前に進んでいけます。スマホも掃除もノートまとめも、上手に付き合っていけば、むしろ勉強のリズムを整える強力な味方になってくれます。
ぜひ、この記事を読んだ今日から、なにかひとつでも行動を変えてみてください。たとえば、スマホを机の引き出しに入れてみる。計画表に「ゆとり時間」を入れてみる。過去問を1ページだけでも開いてみる。そんな小さな一歩が、きっとあなたの学びを前に進めてくれます。
ポジティブな気持ちで、あなたらしくテスト勉強に向き合っていきましょう。応援しています!