はじめに
高校生活で避けては通れない「内申点」。特に推薦入試やAO入試を考えている人にとっては、テストの点数以上に重要な評価指標になります。「頑張っているのに成績が伸びない…」「テストはそこそこ取れるのに内申点が低い」そんな悩みを持っている高校生も多いのではないでしょうか?
実は、内申点はテストだけで決まるわけではありません!
普段の授業態度、提出物、学校生活全体の姿勢など、さまざまな要素が関わっています。先生は「努力の過程」や「日々の姿勢」も含めて評価しているため、テストの点数だけで勝負しようとすると、思わぬところで損をしてしまうこともあります。
さらに、内申点は一度の頑張りで急に上がるものではなく、コツコツ積み重ねる姿勢の総合評価です。だからこそ「今の行動」が半年後や1年後の評価にしっかり反映されるのです。私は高校時代、テストの点数は平均程度でも、提出物や授業態度を意識的に改善することで内申点を底上げできた経験があります。「自分には無理かも…」と感じている人でも、日常の行動を少し工夫するだけで十分に改善可能です。
本記事では、テスト以外で差がつく内申点アップの方法を7つ紹介しながら、具体的にどう行動すれば先生に「この生徒は頑張っている」と感じてもらえるのかを詳しく解説します。どの方法も今日から実践できる内容ばかりなので、「内申点を上げたい!」と思う人は、ぜひ最後まで読んでみてください。きっと新しい気づきが得られるはずです。
内申点って何?どうやって決まるの?
内申点の基本的な仕組み
内申点とは、各教科ごとに先生が生徒の学習状況を5段階や10段階で評価し、その平均を算出したものです。通常は「学習の記録(通知表)」に表示されます。つまり、定期的に行われるテストの成績だけではなく、授業を受けているときの様子や提出物の出来栄え、学校生活全体の姿勢がトータルで反映される“総合評価”といえます。
評価の対象は?
内申点の評価には以下のような要素が含まれます:
- 定期テストの点数
- 授業態度や積極性
- 提出物の内容と提出状況
- グループワークでの姿勢
- 授業外活動(委員会、部活動など)
- 出席日数や遅刻回数
- 学校行事やボランティア活動での貢献度
どうやって先生は見ているの?
先生は毎日の授業や学校生活を通して生徒の様子を観察しています。ノートの取り方や授業中の姿勢、小テストの取り組み方まで一つひとつが判断材料です。また、授業後に残って質問するなどの自主的な行動もプラスに働きやすいです。反対に、提出物の遅れややる気のなさが続けばマイナス要素となってしまいます。
体験談を交えて
私自身も高校1年の頃は「内申点=テストの点数」と思い込んでいました。しかし、通知表を見てみると点数のわりに成績が伸びず、理由を先生に聞いたところ「授業中の態度や提出物の丁寧さも大切なんだよ」と教えていただきました。それから意識して取り組んだところ、次の学期には明らかに評価が上がったのです。
ポイント:「目に見える結果」だけでなく「日々の積み重ね」も重視されているんです!小さな行動の積み重ねが大きな成果につながります。
1. 授業態度で信頼を勝ち取ろう
ただ座っているだけじゃもったいない!
授業中にただ椅子に座っているだけでは、評価は上がりません。先生はクラス全体をよく見ており、誰が真剣に取り組んでいるかをしっかり把握しています。集中しているかどうかは、姿勢や視線、ノートの取り方などからも伝わります。授業態度は、その教科に対する関心ややる気を示す「無言のメッセージ」なのです。
実践すべきポイント
- 目を見て話を聞く
- 頷きやリアクションを意識する
- 積極的に発言・質問する
- 黒板を写すだけでなく、内容を自分なりにメモする
- 周囲の人に迷惑をかけない(私語や居眠りは厳禁)
- 先生が求めるリアクションに素早く反応する
さらに工夫できること
授業態度を改善するために、私は「授業ノートに授業ごとのミニ目標を書く」という習慣をつけていました。たとえば「今日は疑問を1つ見つける」「板書の補足を必ず自分の言葉で書く」といった目標です。小さな目標でも達成感があり、集中力が持続しました。また、発言が苦手な人は授業後に先生に個別で質問することでも積極性をアピールできます。
私の体験談
高1の頃、発言が苦手だった私ですが、「1時間に1回は手を挙げる」と決めたことで、先生から「積極的な姿勢がある」と評価され、内申点が上がった経験があります!さらに、ある授業では先生から「クラス全体の雰囲気を良くしている」と言われたこともあります。授業態度は、自分だけでなくクラス全体の雰囲気作りにも影響するんです。だからこそ、意識して行動すると自分の評価も仲間の学びもプラスになります。
2. 提出物は“質と期限”が命
ただ出すだけじゃ評価されない
ワークやプリントを出すとき、内容が適当だったり期限を守らなかったりすると、評価はマイナスに。逆に、しっかりした内容で期限内に提出するだけで印象はグッと良くなります。さらに、提出物は「その生徒がどの程度理解しているか」を知るための重要な手がかりでもあるため、先生は細かい部分までチェックしています。
提出物を評価UPに変えるコツ
- 丁寧な字で記入する
- 色分けや見やすいレイアウトを工夫する
- 空欄を残さず埋める
- 自分の意見や感想をひと言添える
- 余白を活用して補足を書き加える
- 図や表を使って分かりやすく整理する
さらに一歩先の工夫
私は高校時代、提出物に「今日の学び」や「次に調べたいこと」を一言書き添えていました。これだけで先生から「主体的に取り組んでいる」と高評価をもらえました。また、ワークの問題をただ解くだけでなく、間違えた理由や気づきを簡単にメモしておくと、自分の復習にも役立ち、提出物の完成度もアップします。
提出物を通して伝わる“人柄”
提出物の仕上がりは、真面目さや責任感をアピールできる場でもあります。字が乱れていたり、白紙が多かったりすると「やる気がない」と受け取られることもありますが、逆に丁寧に書かれたノートやプリントは「この生徒は努力している」と先生の印象に残ります。つまり、提出物は自分を表現するチャンスなのです。
✅ プチ工夫で印象UP!小さなひと手間が、大きな信頼につながります。
3. 委員会・係活動は内申点の隠れたチャンス
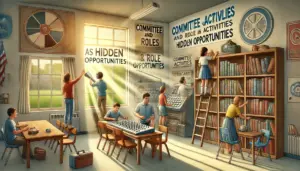
内申点に反映されるって本当?
実は、委員会活動や係の仕事も評価対象に含まれています。特に「責任感」や「リーダーシップ」が求められるポジションは内申点UPに直結します。先生は「自分の役割をきちんと果たしているか」「仲間と協力して活動できているか」をしっかり観察しています。普段の授業態度と同じくらい、委員会や係の取り組み方も大切なのです。
おすすめの関わり方
- クラス委員や図書委員、学級日誌など積極的に立候補
- ただ「やる」だけでなく、+αの工夫を意識
- 学期末には振り返りの記録をしっかり提出
- 周囲の意見を取り入れて改善点を見つける
- 仲間と分担して効率的に進める工夫をする
さらに評価を上げる工夫
委員会活動や係の仕事を「義務」として受け止めるのではなく、「自分の力を試す場」と考えるとモチベーションが上がります。例えば文化祭の実行委員なら、装飾や企画を担当するだけでなく、後輩への指導やクラス全体の雰囲気作りに貢献することもできます。こうした主体的な取り組みは先生の印象に強く残ります。
経験からひと言
私は清掃係を担当していたとき、ただ掃除をするのではなく、掃除表の見やすい管理や忘れ物チェックも加えて実行。先生から「工夫が素晴らしい」と褒められました!また、学級委員を務めた友人は「クラス全員が発言しやすい雰囲気作り」を心がけていて、その姿勢が評価されていました。委員会や係の活動は、地味に見えても先生にとっては“努力と責任感の表れ”として高く評価されるチャンスなのです。
4. ノートの取り方で“本気度”を見せる
ノートは見られている!
先生によっては、提出を求めたり、授業後にチェックする場合も。整理されたノートは、学習意欲の証拠になります。中には「ノート提出」を成績に直接反映する先生もいるほどで、普段からの記録が大きな差につながります。ノートの見やすさは、自分の理解度を高めるだけでなく、先生に「この生徒は真剣に学んでいる」と印象づけることにも直結します。
評価されるノートの特徴
- 日付・単元を明記
- 見やすく整理されたレイアウト
- 色分けで重要ポイントを強調
- まとめや自分の言葉での解釈を記入
- 質問や疑問を書き留めておく
- 単元ごとにインデックスをつけて振り返りやすくする
ノートを工夫する方法
単に黒板を写すだけではなく、授業中に先生が口頭で補足した内容や自分が理解しにくいと思った部分も残しておくことが重要です。私の場合、左側に板書内容、右側に「自分なりのコメント欄」を作っていました。そこに気づきや疑問を書いておくと、テスト前に見返したときに復習しやすく、効率的に学習できました。
体験談からのヒント
私は英語の授業で、板書の文法ルールに加えて「自分が使えそうな例文」をその場で作って書き込むようにしていました。その結果、先生から「自分の学びに落とし込んでいるね」と高く評価されました。友人の中には、イラストや図解を交えてノートを工夫している人もおり、視覚的にも分かりやすいノートは先生の目にも留まりやすいです。
🔍 まとめ欄を活用することで、学びの定着にもつながります!さらに自分だけのオリジナル要素を加えれば、内申点アップだけでなく、テスト勉強や受験対策にも大いに役立ちます。
5. 発言・質問で積極性をアピール
「目立つ=評価UP」ではない
発言や質問は、必ずしも“数”ではなく“質”が大事。クラスの雰囲気を壊さず、内容のある発言をすることがポイントです。授業中に黙っているだけでは、先生からの印象は薄くなります。逆に「ここが分からない」「こう考えました」と一言添えるだけで積極的に授業に参加していると評価されます。
効果的な発言とは?
- 質問内容を事前に整理する
- 相手の話を受けて自分の意見を述べる
- 教科ごとのキーワードを活用
- 他の人の意見を補足して深める
- 「わからない」をそのままにせず声に出す
さらにプラスの工夫
授業中に発言するのが苦手なら、授業後に先生へ直接質問するのもおすすめです。小さな発言でも、継続すれば先生に「前向きに取り組んでいる」と伝わります。また、授業だけでなくホームルームや委員会で意見を出すことも評価に繋がります。重要なのは、発言がクラスの学びに貢献しているかどうかです。
コツコツが評価につながる
私は発言が苦手でしたが、英語の授業で「先生が使った単語を復唱する」だけの練習から始め、徐々に発言の質も上がり、先生からも評価されるようになりました。数学の授業では「解法の途中まで」を発言し、先生に続けてもらう形で自信をつけました。小さな積み重ねがやがて自信につながり、「発言するのが当たり前」という姿勢が内申点アップに直結しました。
6. 清掃や学校行事にも全力で!

「どうせ誰も見てない」は大間違い
学校行事や掃除など、日常の小さな活動も、先生はしっかり見ています。コツコツ真面目に取り組む姿勢が内申点に繋がります。特に行事の裏方作業や掃除当番などは、目立たないからこそ「本気でやっているかどうか」が評価されやすい部分です。
ここが評価される!
- 真面目に掃除をする
- 行事の準備や片付けを率先して行う
- 班活動などでリーダーシップを発揮
- 周囲が面倒くさがる役割に自ら取り組む
- 行事中に仲間をサポートする
さらに一歩踏み込んだ工夫
掃除では「決められた範囲だけでなく周囲もきれいにする」ことや「道具を丁寧に扱う」ことが先生に伝わります。学校行事では「準備の段階から主体的に動く」「後片付けを最後まで残って行う」など、最後のひと踏ん張りが高評価に繋がります。私の友人は体育祭の実行委員で、終了後にグラウンド整備まで手伝い、先生から強く感謝されていました。
私の体験談
私自身も、文化祭の片付けで最後まで残り、ゴミ分別や道具の片付けを率先して行ったことがあります。そのとき先生に「最後まで責任を持って動いてくれて助かった」と声をかけられ、通知表のコメントにもその姿勢が記載されていました。地味に見える活動ほど、先生はきちんと評価してくれるのです。
🌟 地味なことでも、「誰かがやらないと回らない」役割に価値があります!小さな積み重ねが、最終的に大きな信頼と評価につながります。
7. 生活態度や遅刻・欠席も内申点に影響
出席状況は重要な評価項目
無断欠席や遅刻が多いと、内申点に大きく影響します。「体調不良」は仕方ないですが、自己管理も評価の一部です。欠席が続くと「責任感が弱い」と受け取られることもあり、逆に出席率が高いと「意欲がある」とプラス評価されます。授業を休まない姿勢は、それだけで信頼に繋がります。
生活態度で意識したいこと
- 時間を守る(登校・提出物・集合時間など)
- 学校内での言葉遣いや態度
- SNSや私生活での言動も注意
- 服装・身だしなみを整える
- 先生や友達への挨拶を欠かさない
- 校則を守る姿勢を示す
さらに工夫できる行動
生活態度を改善するために、私は「毎朝5分早めに登校する」ことを習慣化しました。これだけで遅刻がゼロになり、先生から「安定していて信頼できる」と言われました。さらに、身だしなみを整えるだけでなく、周囲への配慮(友達の忘れ物をサポートするなど)を心がけると、自然に良い雰囲気を作ることができました。
体験談から学べること
ある友人は遅刻が多く、授業態度もだらしなかったため、学力は高かったのに内申点が思ったより伸びませんでした。一方で、別の友人は成績が中くらいでも遅刻や欠席がほとんどなく、生活態度がしっかりしていたため「信頼できる生徒」として高く評価されていました。この違いは大きく、受験時にも明暗を分けました。
🚨 身だしなみやマナーも意外と見られています!小さな行動の積み重ねが信頼を生み、結果的に内申点にも反映されるのです。
8. 小テストや小さな課題も手を抜かない
先生は細かい部分まで見ている
毎週の小テストや、ちょっとしたレポートなども評価対象になります。「どうせ成績に関係ない」と思わず、全力で取り組みましょう。 小テストは先生にとって「普段の理解度」を確認するための大切な材料ですし、レポートや感想文も「学びをどう受け止めているか」を測るヒントになります。たとえ点数が低くても、見直しや復習をきちんとしているかどうかが先生には伝わるのです。
小さな積み重ねが大きな評価に
- 小テスト対策をルーティン化
- 間違えた問題は復習ノートにまとめる
- 感想文・自由課題も丁寧に仕上げる
- 提出の際に自分の考えを一言添える
- 先生のコメントを見返し、改善を意識する
さらにできる工夫
私は小テストの結果をそのままにせず、「間違えた問題専用ノート」を作っていました。そこに次回のテスト前にもう一度解き直す習慣をつけたことで、先生から「復習をきちんとしているね」と褒められました。自由課題でも、最低限の内容だけでなく、自分の興味を少し加えると「主体性がある」と評価されやすいです。
体験談から学べること
友人の一人は、小テストを軽視していたため普段の点数は悪くなかったのに通知表の評価が伸び悩んでいました。一方で、別の友人は毎回の小テストに真剣に取り組み、提出物に感想を添えることを欠かさなかったため、学力が平均的でも高く評価されていました。小さな課題こそが“努力を見せる場”なのだと痛感しました。
9. 友達との関わり方も見られている

協調性・思いやりも評価対象
学校生活は「社会の縮図」。トラブルが多い、友達と関係が悪いなども、間接的に評価に影響する場合があります。授業中のグループワークや行事の準備など、仲間と協力する場面は多く、そこでの態度や姿勢も先生はしっかり見ています。
良い人間関係を築くには?
- 挨拶を大切にする
- 他人の意見を否定しない
- トラブルがあったらすぐに相談
- クラスの輪に積極的に参加する
- 相手の立場に立って考える
- 困っている人を見かけたら声をかける
さらにできる工夫
私はクラスメイトとの関係をよくするために、毎日必ず「ありがとう」を言うことを意識していました。ちょっとしたことでも感謝を伝えると、雰囲気が良くなり信頼関係が築かれます。また、友人同士でトラブルがあったとき、すぐに担任や先生に相談したことで大事にならずに済んだ経験があります。問題を隠すのではなく、誠実に対応することも評価に繋がります。
体験談から学べること
ある友人は、学力は高かったのに人間関係のトラブルが多く、先生からの評価が低めでした。一方で、もう一人の友人は成績は中程度でも、周囲に気を配りクラスの雰囲気を良くしていたため「クラスを支えている」と高く評価されていました。人との関わり方は、成績以上に内申点に直結する大切な要素だと実感しました。
❤️ 先生にとって“信頼できる生徒”であることが、最も大きな評価に!仲間との関わり方も含め、日々の行動があなたの内申点を左右します。
10. 自分なりの目標と振り返りを持つ
振り返りこそ成長のカギ
内申点を上げるには、自分の行動を客観的に見ることが大切。「なぜ評価が低かったのか」「どこを改善すべきか」を考える習慣をつけましょう。振り返りは単なる反省ではなく、次の行動に活かすためのステップです。例えば「授業で発言が少なかった」→「次回は1回以上発言する」といったように、具体的な改善行動を考えると効果的です。
目標設定のヒント
- 月ごとに目標を設定する
- 週1回、自分の行動を振り返る
- できたことは自分をしっかり褒める!
- 小さな行動目標を積み重ねて大きな成果につなげる
- 友達や先生に「改善点」を聞いてみる
- ノートや日記に記録して可視化する
さらにできる工夫
私は毎週末に「良かったこと・改善点」を3つずつノートに書き出していました。そのおかげで次の週の行動が具体的になり、気づけば習慣化していました。目標は大きすぎると挫折しやすいため、「毎週1回は先生に質問する」「提出物は必ず期限2日前に出す」など、小さく設定することが継続のコツです。
体験談から学べること
友人の一人は、月初めに「今月の目標」を教室のカレンダーに書き込み、クラス全体でシェアしていました。これにより自分だけでなくクラスメイト同士で励まし合える環境が生まれ、結果的に全員の意識が高まったそうです。振り返りと目標設定は、個人だけでなく周囲にも良い影響を与えます。
📔 習慣化すれば、自然と行動も変わります!自分の努力を“見える化”することで、先生にもしっかり伝わり、内申点アップに直結するのです。
まとめ|内申点は“努力の見える化”!今日から変われる!
内申点は、テストだけでなく日々の積み重ねで作られていくもの。今回紹介した10のポイントは、どれも特別な才能がなくても実践できることばかりです。授業態度や提出物、係活動や学校行事など、一見小さな行動に思えるものでも、コツコツ積み重ねれば確実に先生の評価に反映されます。
「自分なんて…」と思っていたとしても、小さな一歩が未来を変えます。実際に私自身も、提出物の工夫や毎日の授業態度を改善するだけで通知表の評価が上がった経験があります。大きなことを一気に変える必要はありません。今日から始められる小さな習慣を意識することが、半年後や1年後の大きな成果につながるのです。
💬 今日からできる行動:
- 授業で先生の目を見る
- 提出物は丁寧に仕上げる
- 掃除や係活動にも一工夫を加える
- ノートにその日の学びを一言まとめる
- 「ありがとう」と「おはよう」を欠かさず伝える
最後に伝えたいのは、
🌈 **内申点は「日々の自分の努力の証明」**です。小さな積み重ねは必ずあなたの力になります。
一つひとつを大切にして、あなたらしく高校生活を送ってください。挑戦する姿勢を忘れなければ、きっと未来は大きく変わります。応援しています!


