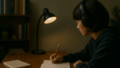はじめに
「朝起きるのが本当にツラい……」そんなふうに感じている高校生、多いのではないでしょうか?特に冬の朝や、前日に夜更かしをしてしまった次の日は、布団が魔法のように心地よく、目覚ましが鳴っても「あと5分……」とスヌーズを押してしまう、そんな経験は誰しもあると思います。
毎晩「明日はちゃんと起きよう」と思って寝るのに、いざ朝になると体が動かない。目覚ましを止めてまた寝てしまい、気づいたら家を出る時間ギリギリ。慌てて制服を着て、朝ごはんも食べずに家を飛び出す……そんなバタバタした朝を過ごしていませんか?
実際に筆者自身も、高校時代は朝にめっぽう弱く、毎朝が戦いでした。「もう無理、学校休みたい」と思ったことも何度もあります。でも、あるとき「なぜ自分は朝起きられないのか?」という原因を考え、生活を少しずつ見直していくことで、毎朝スッキリと目覚められるようになりました。
この記事では、そんな高校生の「朝起きられない問題」を根本から解決する方法をたっぷりと紹介します。睡眠の質を高めるコツや夜更かしを防ぐテクニック、朝のモチベーションの作り方など、実際に筆者が効果を感じた方法を中心に、読みやすく・わかりやすくまとめました。
毎朝が苦痛だと、1日のスタートがネガティブな気分になってしまいます。でも、ちょっとした意識の変化や行動の工夫で、その朝を少しずつ変えることができます。あなたにも、毎朝気持ちよく目覚めて、1日を前向きにスタートしてほしい。そんな気持ちを込めて、この記事をお届けします。
さあ、一緒に「朝起きられない問題」に終止符を打ちましょう!
朝起きられないのはなぜ?その原因を探ろう
朝が苦手な理由は人によってさまざまですが、共通して見られる原因を知ることで、改善への第一歩を踏み出すことができます。以下に、高校生に特に多い3つの大きな要因を詳しく紹介します。
1. 睡眠不足
高校生は成長期の真っ只中にあるため、一般的に1日に7.5〜9時間程度の睡眠が必要とされています。ところが、現実には勉強、部活、塾、そしてスマホやゲームなどの娯楽で寝る時間がどんどん遅くなり、結果として慢性的な睡眠不足に陥っているケースが非常に多いです。
夜遅くまでスマホをいじってしまい、「あとちょっとだけ」と動画を見続けて気づけば深夜……という経験、ありますよね?筆者も高校時代はそのパターンにはまり、毎朝の眠気に苦しんでいました。睡眠不足が続くと、朝だけでなく1日中ボーッとして集中力も下がり、生活全体に悪影響を及ぼします。
2. 生活リズムの乱れ
平日は早起きして学校に行くけど、土日は昼まで寝てしまう……そんな生活をしていませんか?この「休日の寝だめ」は体内時計を乱す大きな原因です。人間の体は一定のリズムで活動することに慣れており、起きる時間が毎日バラバラだと朝に体がうまく目覚めてくれません。
特に夜ふかしが常習化すると、体は夜型に傾き、早寝早起きがますます難しくなります。また、夜遅くに食事をしたりカフェインを摂ったりすることも、睡眠の質を下げる原因になるので注意が必要です。
3. ストレスや不安
精神的なストレスも、朝起きられない大きな要因の一つです。たとえば、学校での人間関係や成績への不安、家庭での悩みなど、心が緊張した状態では寝つきが悪くなり、ぐっすり眠れません。そうすると、眠りが浅くなり、朝の目覚めも悪くなってしまいます。
また、「学校に行きたくない」という気持ちが強いと、無意識のうちに起きることを拒んでしまうこともあります。これは決して甘えではなく、心のSOSであることもあるので、自分自身を責めすぎず、原因を整理することが大切です。
まずは、自分の睡眠状況や生活リズム、最近の気持ちを振り返ってみましょう。朝起きられないのは、あなたが怠けているからではなく、きちんとした理由があるのです。その原因を理解することが、改善への第一歩になります。
朝が弱い人に共通する生活習慣とは?

朝が苦手な人には、実は共通する生活習慣があります。これらの習慣が無意識のうちに身についてしまっていると、どれだけ目覚ましをセットしてもなかなか起きられないものです。以下にいくつか代表的なものを詳しく紹介します。
- 就寝時間がバラバラ:平日は夜遅くまで勉強やスマホをしていて、休日はお昼近くまで寝ている……そんな不規則な生活は、体内時計を大きく狂わせます。毎日同じ時間に寝て起きることが、朝をスッキリ迎える基本です。
- 寝る直前までスマホを見ている:スマホやタブレットの画面から出るブルーライトは、脳を覚醒させてしまうため、眠気を妨げます。特にSNSや動画視聴は刺激が強く、気づいたら1時間以上たっているなんてことも。筆者も高校時代、布団に入ってからTikTokを見始めて、気づけば深夜2時なんてことがよくありました。
- 寝室の環境が悪い(明るすぎる・うるさい):快適な眠りには、暗く静かな空間が欠かせません。蛍光灯をつけっぱなしにしていたり、外の騒音が気になったりする環境では、深い眠りに入りづらくなります。遮光カーテンやアイマスク、耳栓を活用すると良いでしょう。
- 寝る前にカフェインや刺激物を摂取している:夜遅くにコーヒーやエナジードリンク、チョコレートなどを摂ると、カフェインの覚醒作用で寝つきが悪くなることがあります。寝る2〜3時間前からは、カフェインを控えることが望ましいです。
- 運動不足で日中にエネルギーを使い切れていない:適度な運動は、夜の自然な眠気を促します。体をあまり動かさずに1日を過ごすと、寝つきが悪くなり、結果として朝も起きにくくなってしまいます。
これらの習慣は、自分でも気づかないうちに身についていることが多いです。もし思い当たる点があれば、それは改善のチャンス!まずは1つずつ見直していくことで、朝のつらさが徐々に軽減されていきます。
睡眠の質を上げるにはどうしたらいい?
毎晩きちんと寝ているつもりなのに、朝になっても疲れが取れていない……そんな経験はありませんか?それは、睡眠時間ではなく「睡眠の質」が低いことが原因かもしれません。質の良い睡眠をとることは、朝スッキリ起きるための大きなカギです。ここでは、すぐにできる実践的なポイントを紹介します。
● 寝る前のルーティンを作る
「寝る前は読書」「ストレッチをする」など、毎晩同じ行動をすると、体が”もうすぐ寝る時間だ”と理解して自然に眠くなります。このルーティンには、心と体をリラックスさせる効果があります。たとえば、軽いストレッチや深呼吸、好きな香りのアロマを使ったリラックスタイムなど、自分だけの「おやすみスイッチ」をつくってみましょう。筆者は、毎晩ノートに一言日記を書くことで、頭の中を整理しながら自然と眠くなる習慣を身につけました。
● ブルーライトを避ける
スマホやパソコンの光に含まれるブルーライトは、脳を刺激して覚醒状態にしてしまうため、眠気を妨げる原因になります。就寝1時間前からは画面を見るのをやめるのが理想ですが、それが難しい場合は、ブルーライトカット眼鏡を使う・画面の明るさを落とす・ナイトモードを活用するなどの工夫も有効です。できれば、寝る前のスマホ時間を本や音楽に置き換えることで、自然と眠気が訪れやすくなります。
● 部屋の環境を整える
快眠のためには、寝室の環境づくりも重要です。静かで暗く、リラックスできる空間を意識しましょう。遮光カーテンを使うことで外の光をシャットアウトできますし、耳栓を使えば外の騒音も気になりません。また、夏はエアコンで快適な温度に保ち、冬は乾燥を防ぐ加湿器を使うとより良い睡眠が得られます。
さらに、寝具にも注目してみてください。自分の体に合った枕やマットレスは、眠りの質を大きく左右します。筆者も枕を変えたことで、翌朝の首や肩の疲れが減り、目覚めが格段に良くなった経験があります。
これらの工夫を取り入れることで、睡眠の質は確実に向上します。短時間の睡眠でも深く質の高い眠りが取れれば、翌朝のコンディションもぐっと良くなるはずです。
夜更かしを防ぐためのテクニック
ついつい夜更かししてしまうのは、誰にでもあること。でも、夜遅くまで起きていると翌朝に影響が出るだけでなく、体にもメンタルにも悪影響を及ぼします。ここでは、夜更かしを防ぐための実践的なテクニックをいくつか紹介します。
- スマホの使用時間を制限するアプリを使う:アプリを使えば、自分ではコントロールしづらいスマホ時間を自動的に管理できます。特定の時間帯になるとロックがかかるタイプや、使用時間の記録を可視化するものなど、自分に合ったものを選びましょう。
- 寝る前の予定を立てて早めに行動開始:例えば「22時までにお風呂」「23時にベッドに入る」など、あらかじめスケジュールを決めておくと、だらだらと時間が過ぎるのを防げます。時間が見えることで、逆に自由な時間も有効に使えるようになります。
- SNSやゲームは時間を決めて楽しむ:SNSをチェックし始めると、あっという間に時間が経ってしまいます。好きなだけ見てもいい時間帯と、見ない時間帯を自分で決めておくと◎。ゲームも「1ステージだけ」「30分まで」など、ルールを作っておくのがおすすめです。
- 夜の過ごし方を変えてみる:夜にリラックスできる趣味を取り入れるのも効果的です。読書、絵を描く、音楽を聴くなど、デジタルから少し離れて過ごすと、自然と眠気が訪れやすくなります。筆者は、アロマキャンドルを灯しながら読書をする時間を作ったことで、夜更かしが減りました。
- 眠る準備の合図を自分に出す:決まった時間にパジャマに着替えたり、歯を磨いたりすることで、「もう寝る時間だ」と体と脳に教えることができます。こうした小さな習慣の積み重ねが、睡眠へのスムーズな切り替えを助けてくれます。
筆者も「YouTubeを1本だけ見るつもりが、気づいたら1時間経過……」という失敗が多々ありました。そのたびに「明日はちゃんと早く寝よう」と思うものの、また繰り返してしまうという負のループに陥りがちです。そんなときこそ、タイマーを使ったり、スマホを別の部屋に置いたりと、自分で自分をコントロールする工夫が効果的です。
夜の時間をどう使うかは、自分自身の意識次第。夜更かしを防ぐことができれば、朝もスムーズに起きられるようになり、生活の質がぐんと上がります。
朝の目覚めをスムーズにする工夫

朝の目覚めを快適にするためには、ちょっとした工夫を生活に取り入れることがとても大切です。無理やり起きようとするのではなく、自然と目が覚めるような環境づくりや習慣が、毎朝のつらさを軽減してくれます。以下に、具体的な方法を紹介します。
● 自然光で起きる
人間の体内時計は光に大きく影響を受けています。朝日を浴びることで、体は「起きる時間だ」と認識し、自然と目が覚めやすくなります。カーテンを少し開けて寝ておくだけでも、朝になると部屋に光が入り、自然な目覚めを助けてくれます。
さらにおすすめなのが、日の出の時間に合わせて徐々に明るくなる「光目覚まし時計」です。筆者も使っていますが、普通のアラームと違って音でビックリして起きるのではなく、やさしい光で目が覚めるので気分がとても良くなります。
● 目覚まし時計を複数使う
寝起きに弱い人には、目覚ましを1個だけに頼るのは危険です。音に慣れてしまって無意識に止めてしまったり、聞こえなかったりすることも。そこで効果的なのが「複数の目覚ましを使う」こと。特に、1つはベッドから離れた場所に置くことで、体を起こして歩いて止めに行かないといけないため、自然と覚醒できます。
音の種類も工夫してみましょう。例えば、1つは好きな音楽、もう1つは大きなアラーム音にするなど、段階的に目覚める仕掛けを作るのも効果的です。
● 朝の楽しみを作る
「朝起きる理由」があると、それだけで気持ちが前向きになります。たとえば、
- 好きなアーティストの音楽を流す
- 大好きな朝食メニューを用意する
- 朝だけ読むマンガや動画を決めておく
など、「朝だからこそできること」を自分なりに用意するのがおすすめです。
筆者は、朝だけ飲むお気に入りの紅茶を楽しみにしていた時期がありました。たったそれだけでも、「早く起きて飲みたいな」という気持ちになり、布団から出やすくなります。こうした小さな工夫の積み重ねが、朝をラクにしてくれますよ。
学校に行く目的を見つけよう
朝起きられない理由のひとつとして、「学校に行くのが憂うつ」「行く意味を感じない」といった心理的な要因が隠れていることがあります。特に、授業がつまらない、友達とうまくいっていない、成績に自信が持てないなど、さまざまな悩みが重なると、「どうせ行っても楽しくないし……」という気持ちになってしまうのは自然なことです。
しかし、そんなときこそ「なぜ学校に行くのか?」という目的を見直してみるのが大切です。明確な理由があるだけで、毎朝のモチベーションが変わってきます。
- 小さな楽しみを見つける:たとえば、「今日は友達とおしゃべりしよう」「好きな教科の授業がある」「お弁当に好きなおかずが入っている」など、ほんの些細なことでOKです。筆者は「帰りにコンビニでスイーツを買う」という小さなごほうびをモチベーションにしていたこともありました。
- 将来の夢や目標を意識する:自分のなりたい職業や興味のある分野があるなら、今の勉強はその土台づくりです。直接関係なさそうな科目でも、学ぶことで視野が広がり、自分の可能性を広げることにつながります。
- 自分なりの「学校の意味」を考えてみる:成績を上げることだけが学校に通う目的ではありません。友達との関係性を学ぶ場、コミュニケーションの練習の場、自分の居場所としての意味もあります。何か一つでも「これは自分にとって大切」と思えるものを見つけるだけで、学校生活への向き合い方が変わります。
さらに、モチベーションがあると、脳内で分泌されるドーパミンの働きによって自然とやる気が高まり、朝の目覚めも良くなるといわれています。つまり、精神的な「目的意識」が体にも良い影響を与えるのです。
「今日も頑張らなきゃ」と力む必要はありません。大切なのは、「今日、ちょっとだけ楽しみなことがある」と思えるような心の余白です。自分にとっての学校の意味を、焦らずゆっくり見つけていきましょう。
朝起きる力をつける「朝活」のススメ
「朝活」と聞くと、大人がやるものと思われがちですが、実は高校生にこそおすすめしたい習慣です。朝の30分〜1時間を少しでも有効に使うことで、1日が驚くほど充実したものになります。
朝は脳が最もスッキリしていて、集中力や記憶力が高まっている時間帯。この貴重な時間をただ慌てて過ごすのではなく、自分のために使うことで、心にも余裕が生まれます。
たとえば……
- 軽くストレッチをして、体を目覚めさせる。血行がよくなり、眠気も吹き飛びます。
- 読書や英単語の勉強、日記を書くなど、自分を高める静かな時間にする。
- 朝日を浴びながら散歩をすることで、自然と前向きな気持ちになれる。
- 好きな音楽を聞きながら身支度をすることで、気分が上がる。
- 将来の夢や目標を紙に書き出してみることで、自己モチベーションの向上にもつながる。
筆者は、朝活を始めたことで、通学電車の中でも集中して読書ができたり、授業中も頭が冴えていたりと、良い影響を実感しました。最初は早起きがツラくても、「朝の静かな時間って意外と気持ちいいな」と思える日が必ず来ます。
いきなり大きく生活を変える必要はありません。まずは10分でもいいので、「自分のための時間」を作ることからスタートしてみましょう。それが「朝を味方にする」第一歩になります。
食生活から見直す:朝ごはんの大切さ

「朝は食欲がないから何も食べない」そんな人も多いですが、朝ごはんは体と頭を目覚めさせるための重要なスイッチです。朝にエネルギーを補給することで、体温が上がり、脳も活性化され、自然と元気が出てきます。
実際に、朝食をしっかりとる習慣がある人は、授業中の集中力や記憶力も高いと言われています。また、朝ごはんを抜くと体がエネルギー不足になり、血糖値が下がってしまうため、イライラしたりボーッとしたりしやすくなります。
朝食は重たくなくてもOKです。以下のようなメニューを取り入れて、手軽に栄養を補給しましょう。
- バナナやヨーグルト、ゆで卵など、胃に優しい軽食
- パン+チーズ、フルーツ+プロテインドリンクなど、糖分とタンパク質をバランスよく
- 味噌汁やスープなど、温かいものをプラスすると体も温まって目覚めがよくなります
- 水や白湯をコップ1杯飲んで、水分不足を補うことも大切
さらに、前日の夜に「朝ごはんを楽しみにする」ことも、早起きのモチベーションになります。筆者は、前夜にフルーツヨーグルトを仕込んでおき、「明日の朝はこれを食べよう!」とワクワクしながら眠りについたこともあります。
朝ごはんは、ただの食事ではなく、1日のスタートに欠かせない大事な習慣です。毎朝しっかり食べることで、心も体も整い、朝からアクティブに過ごせるようになります。
家族との連携もカギ!
朝の準備をスムーズにするためには、自分一人で頑張るよりも、家族のサポートを得ることがとても大きな助けになります。家族の中で協力体制が整っていると、毎朝の時間がグッとラクになるだけでなく、気持ちにも余裕が生まれます。
たとえば……
- 一緒に早寝早起きを心がける:自分だけが早く寝ようとしても、家族がリビングでテレビを見ていたり、話し声が響いていたりすると、なかなか眠れません。家族全体で「早寝」を意識してもらうと、寝る雰囲気が整いやすくなります。
- 朝の声かけや手伝いをお願いする:朝は目覚ましが鳴っても起きられないことも多いですよね。そんなときに「もう起きる時間だよ〜」と声をかけてもらえるだけでも、目覚めやすくなります。洗顔の準備や朝ごはんの支度を少し手伝ってもらうだけでも、バタバタ感が軽減されます。
- 時には「手伝ってくれてありがとう」と感謝を伝える:当たり前に感じている家族のサポートも、きちんと感謝の気持ちを伝えることで、関係がより良好になります。「ありがとう」と言われてイヤな気持ちになる人はいません。小さな一言で、朝の空気も優しくなります。
- 家族との朝のコミュニケーションを楽しむ:忙しい朝でも、ちょっとした会話が心を和ませてくれます。「今日の予定は?」「昨日のドラマどうだった?」など、ほんの一言で朝が明るく感じられるものです。
筆者自身、高校生のときは母の「朝だよ〜」の一言に何度救われたかわかりません。一人で起きるのがどうしても難しいときは、「起こしてほしい」と素直にお願いするのも全然アリです。
家族と協力することで、朝のスタートがより軽やかになります。自分の苦手を認めて助けを借りることは、決して恥ずかしいことではありません。
アプリやアイテムを活用しよう
便利なテクノロジーも、朝起きるための強力な味方になります。現代には、目覚めをサポートしてくれる便利なアプリやグッズがたくさん登場しています。それらを上手に取り入れることで、無理なく、そして楽しみながら朝型生活へと近づけます。
- 睡眠管理アプリで生活リズムを可視化:自分の睡眠時間や質を記録してくれるアプリは、寝不足に気づくきっかけになります。グラフで可視化されると、改善点もわかりやすく、「昨日は何時に寝た?」「何時間眠れた?」などを振り返る習慣がつきます。筆者もこのアプリを使うようになってから、就寝時間に対する意識が高まりました。
- 光で起こす目覚まし時計:普通のアラームと違って、設定時刻に近づくと徐々に明るくなり、まるで朝日で自然に目覚めるような感覚になります。特に冬など、朝日が遅い時期には重宝します。音で驚かされるより、優しい光で目が覚めるのはとても快適です。
- アロマディフューザーで癒やしの空間に:ラベンダーやベルガモットなど、リラックス効果のある香りを寝る前に部屋に広げると、深い眠りにつきやすくなります。朝も爽やかな香りで目覚めれば、一日のスタートがぐっと気持ちよくなります。
- スマートウォッチやフィットネストラッカー:心拍数や睡眠パターンをモニタリングできるので、より細かく自分の生活習慣を把握できます。また、軽い振動で起こしてくれる「バイブ目覚まし」機能は、音よりも優しく起きられるのでおすすめです。
- タスクリマインダーや習慣化アプリ:寝る時間や起きる時間にリマインダーを設定すれば、忘れずに行動できるようになります。毎日同じ時間に通知が来るだけでも、生活リズムを整える手助けになります。
これらのアイテムは、ただ使うだけで効果があるわけではなく、「自分に合ったものを継続して使うこと」が大切です。興味を持ったものから少しずつ取り入れて、自分にとって心地よい朝を作るサポート役にしてみてください。
それでも起きられないときは?
どれだけ工夫しても、どうしても朝がつらい日、起きられない日があるかもしれません。そんなときに無理に自分を追い込んでしまうと、逆に気持ちが沈んでしまったり、体調をさらに崩してしまうこともあります。だからこそ、「そんな日もある」と柔軟に受け止めることが大切です。
- 自分を責めすぎない:寝坊してしまった日や、朝うまく起きられなかった日があっても、それは「失敗」ではありません。自分を責めてしまうと、自己肯定感が下がり、次の日もまた起きるのがつらくなってしまうことがあります。「今日はたまたま調子が悪かったんだな」と思って、優しく受け止めましょう。
- 無理に頑張らず、できる範囲で動いてみる:ベッドからすぐに出られないときは、まずは体を少しずつ動かしてみてください。ストレッチをしたり、窓を開けて新鮮な空気を入れたりするだけでも、体が少しずつ目覚めてきます。全てを完璧にこなそうとせず、「できることだけやってみよう」という姿勢で十分です。
- 誰かに頼る勇気を持つ:つらいときには、一人で抱え込まずに家族や友達、学校の先生、カウンセラーなどに相談することも大切です。話すだけでも気持ちが軽くなりますし、思わぬアドバイスやサポートが得られることもあります。
また、心と体の不調が長く続いていると感じた場合は、無理をせず、病院などの専門機関に相談することをおすすめします。睡眠障害やうつなどが隠れているケースもあり、早めに対処することが大切です。
朝起きることが苦手なのは、あなたが怠けているわけではありません。その背景には、日々のストレスや環境、体調などさまざまな要因があるのです。まずは自分の状態をよく見つめ、必要なときには周囲の助けを借りながら、少しずつ前に進んでいきましょう。
まとめ:朝はちょっとの工夫で変わる!
「朝が苦手」「どうしても起きられない」——そんな悩みを抱える高校生はたくさんいます。でも、安心してください。朝起きる力は、生まれつきの能力ではなく、生活の工夫や意識の持ち方で誰でも伸ばすことができるものです。
朝起きられないのは、決してあなたが悪いわけではありません。むしろ、今の社会環境やライフスタイルの中で、朝型の生活を続けること自体が難しい面もあります。だからこそ、ちょっとした習慣の見直しや、気持ちの持ち方の変化が、とても大きな意味を持ちます。
筆者自身も、昔は毎朝「起きたくない……」と布団にしがみついていたタイプでした。でも、生活リズムを少しずつ整え、朝に楽しみを作るようにしたことで、少しずつ朝に前向きな気持ちを持てるようになったのです。「朝って意外と気持ちいいな」「朝の時間を自分のために使えるって贅沢かも」と思えるようになるまでには時間がかかりましたが、小さな一歩の積み重ねで、確実に変わっていきました。
今日からできること
- スマホの使用を寝る1時間前までにする(画面の明るさも抑えると◎)
- カーテンを少し開けて寝て、自然光で目覚める習慣をつける
- 明日の朝の楽しみを1つ決めてから寝る(音楽・朝食・趣味など)
- 「今日は○○をしてみよう」と小さな目標を紙に書いておく
大切なのは、「完璧にやろう」と思わないこと。「できることから、少しずつ試してみよう」という気持ちで、自分のペースで変化を楽しんでください。
朝が少しラクになるだけで、1日全体の気分や効率もぐっと良くなります。ぜひこの記事の中から、自分に合ったヒントを見つけて、今日から少しずつ行動してみてください。
あなたの明日が、今より少しだけ明るく、気持ちのいい朝になりますように。応援しています!