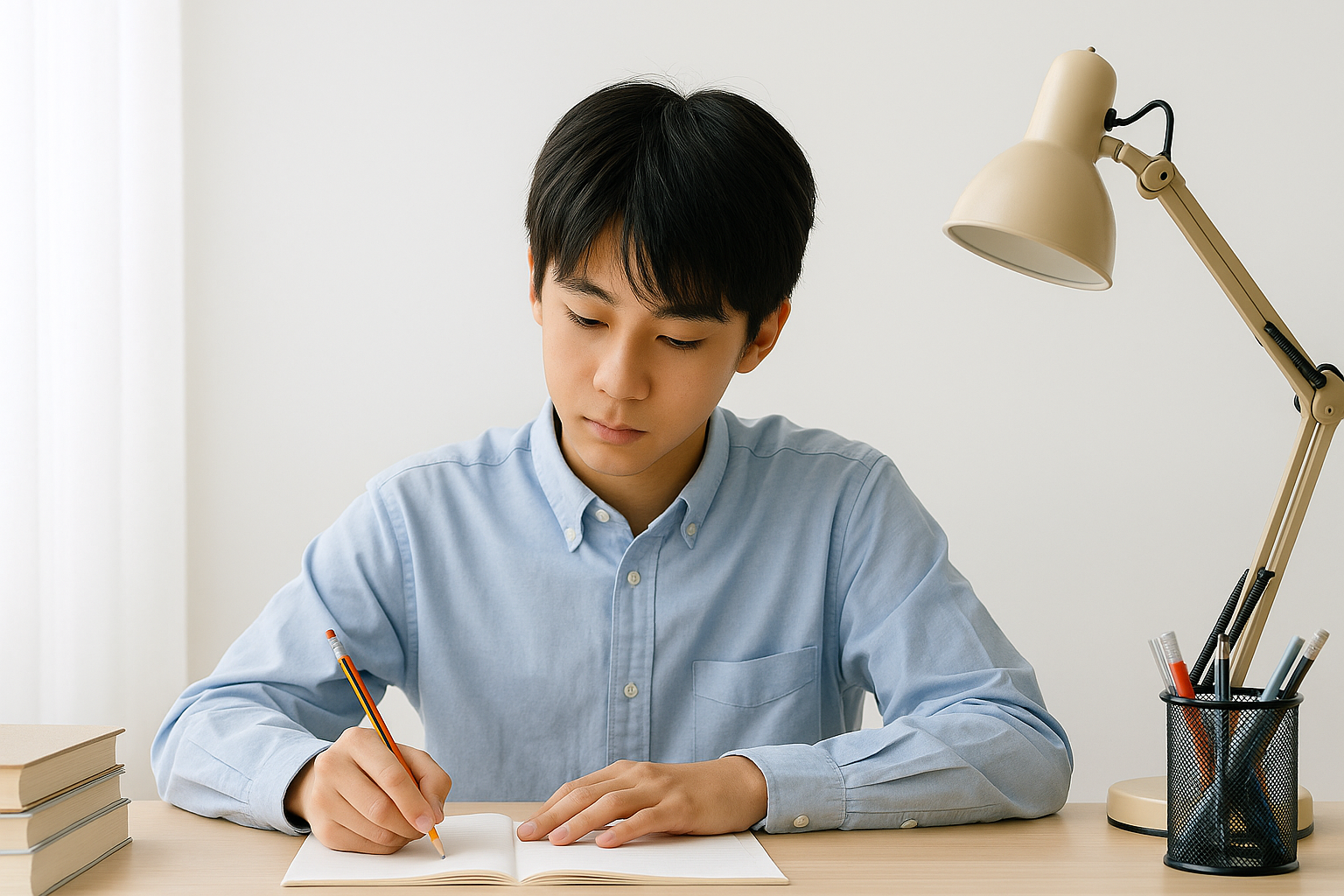はじめに
「一生懸命勉強しているのに、なかなか成績が上がらない…」
そんな悩みを抱えている中学生は、実はとても多いんです。
「塾にも行ってるし、毎日机にも向かってる。それなのに成績が伸びない…」という声をよく聞きます。 実際、私自身も中学生の頃、同じように感じていた時期がありました。
振り返ってみると、その原因はただひとつ。
「正しい努力の仕方」を知らなかったから なんです。
つまり、頑張っているつもりでも、間違ったやり方をしてしまっていたということなんですね。
この記事では、成績を上げたい中学生が知らずにやってしまいがちな“勉強のNG習慣”について、できるだけ具体的に解説していきます。
さらに、ただNGを指摘するだけではなく、
- なぜそれがNGなのか?
- どうすれば改善できるのか?
- 実際にどんなふうに勉強を進めると良いのか?
といったポイントも交えながら、今すぐ使える実践的なアドバイスもご紹介していきます。
このブログを読み終える頃には、
「勉強ってこうすれば良かったんだ!」
と、今までのモヤモヤが晴れて、自信を持って勉強に取り組めるようになっているはずです。
ぜひ、最後までじっくり読んで、明日からの勉強に役立ててくださいね!
あなたの努力が、正しく実を結びますように。
1. とりあえず机に向かうだけの「なんとなく勉強」
やる気はあるけど、内容がない!?
「とりあえず1時間は勉強しよう!」と机に向かってみたものの、
- ノートを眺めるだけ
- 教科書をペラペラとめくるだけ
- スマホをチラチラ見る
- 鉛筆を持ちながら、ぼーっとしてしまう
こんな状態では、**勉強している“つもり”**になってしまいます。
この「なんとなく勉強」は、実は非常に多くの中学生がやりがちなNG習慣です。 やる気はあるのに、中身が伴っていない。そんな状態では、勉強時間をどれだけ増やしても成果は期待できません。
特に注意したいのは、時間をかけることが目的になってしまっているケースです。 「とりあえず1時間やったからOK」という考えだと、集中力が分散し、頭に何も残らないまま終わることになりかねません。
なぜNGなのか?
- 学習の質が低く、記憶に残らない
- 成果が出にくく、モチベーションが下がる
- 「やった気分」だけが残り、勉強の意味がなくなる
- 時間ばかり使ってしまい、他の教科に手が回らない
- 自分の成長が感じられず、勉強がつまらなく感じてしまう
改善ポイント
- その日の目標を明確にする(例:英単語を10個覚える)
- 時間を決めて集中(タイマーを使うのもおすすめ)
- 「何を、どのくらい」やるかを可視化(ToDoリスト化)
- 小さなゴールを設定して、「できた!」の感覚を増やす
- 勉強前に「今日はこれをやる!」と声に出して意識を高める
目の前の時間を“なんとなく”過ごすのではなく、明確な目的と集中力を持って取り組むことが、成果につながる第一歩です!
2. 「まとめノート」ばかり作る
キレイに書いて満足してない?
カラーペンでカラフルにまとめたノート、見栄えはいいですよね。
でも、時間をかけてノートを作ること=勉強したことにはなりません。
「このノートを見返せばバッチリだ」と思っていても、実際に問題を解いてみると手が止まる…そんな経験ありませんか? 私自身、中学生のときは「とにかく見やすいノートを作ろう!」とカラーペンや定規を使って時間をかけていました。 でも、肝心のテストになると解けない。なぜなら、まとめただけで理解していなかったからです。
ノートづくりに時間をかけることで、やった気にはなれます。 ですが、「きれいなノート」と「点が取れる頭」は必ずしも一致しないということを覚えておきましょう。
なぜNGなのか?
- 書くだけで終わってしまい、理解が深まらない
- 手を動かすだけで脳が働いていない
- 時間対効果が悪く、他の勉強ができない
- 「まとめる」ことが目的になってしまい、本来の学習内容に意識が向かない
- 色分けや装飾にこだわりすぎて、肝心の復習の時間が減る
「見やすいノートを作ること」がゴールになってしまうと、肝心の「知識を身につける」という目的が薄れてしまいます。
改善ポイント
- まとめるのは自分の言葉で簡潔に(例:5行以内で要点をまとめる)
- インプットよりアウトプットを重視(問題演習や小テスト)
- 「なぜそうなるのか」を意識してメモを取る(→因果関係を理解する)
- 「見返す」前提でノートを作るのではなく、「理解を深めるために書く」と意識する
- ノート作成は時間を決めて行い、それ以外の時間は練習問題にあてる
特におすすめなのが「1ページ要約法」。1教科ごとに、ノート1ページだけに要点をギュッと詰めて書き出す方法です。 これをやるだけで、自分が何を理解できていて、どこが曖昧なのかがハッキリ見えてきます。
ノートは作品ではなく、あくまで学習のツール。使い倒してこそ意味があります!
3. 一夜漬けに頼る
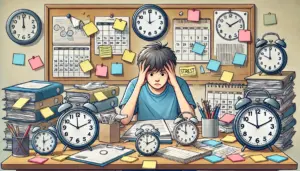
ギリギリまで放置して一気に詰め込む…
テスト前日に慌てて勉強を始める「一夜漬け」。誰もが一度は経験したことがあるかもしれませんが、これは最も非効率な勉強法のひとつです。
短時間で一気に知識を詰め込もうとするこの方法は、脳にとって非常に大きな負担になります。 一夜漬けで覚えた内容は、翌日には何となく覚えていても、その数日後にはほとんど記憶から抜け落ちてしまうのが現実です。
実際、私も「明日がテストだ!」と焦って徹夜で勉強したことがあります。でも、当日は眠くて頭が回らず、ケアレスミスも連発…。 「もっと前からやっておけばよかった…」と毎回後悔していたのを覚えています。
また、一夜漬けは脳を極限まで使うため、翌日のパフォーマンスに大きな悪影響を与えます。 睡眠を削ることで集中力や判断力が下がり、せっかく覚えたこともテスト中にうまく引き出せない、なんてことも起こりがちです。
なぜNGなのか?
- 記憶が短期的で、すぐに忘れてしまう
- 睡眠不足になり、集中力が低下
- 学習が定着せず、次回にもつながらない
- 焦りや不安でストレスが増し、勉強が嫌いになる
- 徹夜が習慣化すると生活リズムが乱れ、体調にも悪影響
改善ポイント
- 毎日コツコツと少しずつ復習する習慣をつける(5分でもOK)
- テスト2週間前から計画的に学習を進める(週ごと・日ごとの計画表を作る)
- 苦手な範囲は早めにチェックして、徐々に得意に変えていく
- 睡眠時間はしっかり確保し、最低でも6〜7時間は眠る
- 暗記よりも理解重視の勉強をして、長期記憶に定着させる
一夜漬けから抜け出すためには、「短時間でもいいから、毎日勉強する」ことが大切です。 1日10分の積み重ねでも、2週間続ければ140分になります。 これは、前日に焦って2時間詰め込むより、ずっと効果的なんです。
今日から少しずつ、コツコツ積み重ねる勉強スタイルを始めてみましょう!
4. スマホを手元に置いたまま勉強する
通知が来るだけで集中力がダウン
スマホが近くにあると、ついつい手が伸びてしまいますよね。
- LINEの通知
- SNSのチェック
- ゲームの誘惑
これらが勉強中の大きな集中妨害要因になっていることに気づいていますか?
中には「通知が来ても無視すればいい」と思っている人もいるかもしれませんが、実は通知が鳴るだけで脳が注意をそちらに向けてしまうのです。ほんの数秒でも、注意が他にそれることで集中状態がリセットされてしまうといわれています。
実際、私も試験勉強中にスマホの通知音に気を取られ、「ちょっと見るだけ…」とSNSを開いたら、気づいたら30分も経っていたということが何度もありました。その時間、本当にもったいなかったです。
また、スマホを手元に置いているだけでも、「気が散る材料」がすぐそこにあるという心理的負担がかかり、知らず知らずのうちに集中力が削がれているのです。
なぜNGなのか?
- 脳が頻繁に切り替わり、学習効率が落ちる
- 気が散って、深い理解ができない
- ついダラダラしてしまい、勉強時間が長引く
- スマホを見ることで一度途切れた集中を取り戻すのに10〜20分かかるといわれている
- 常に「気になるもの」がそばにあることで、勉強そのものへの集中が浅くなる
改善ポイント
- 勉強中はスマホを別の部屋に置く(できれば電源を切っておくのがベスト)
- 「スマホ休憩」を時間で決める(例:45分勉強→5分スマホタイム)
- 通知をオフにする、または機内モードを活用する
- 必要な場合は「集中モード」や勉強専用のタイマーアプリ(例:Study Bunny、Forestなど)を活用
- 保護者に預けたり、目の届かない場所に物理的に置くことで対処
勉強の質を上げるためには、集中できる環境作りが最も大切です。 スマホを手放すのは最初こそつらいかもしれませんが、慣れてしまえば「スマホがない時間」がとても快適に感じるようになりますよ!
5. 苦手科目を後回しにする
得意な科目ばかりやってしまうクセ
数学が苦手、英語が嫌い…そんな気持ち、よくわかります。
人間はどうしても“できること”や“得意なこと”に意識が向いてしまうので、ついつい得意科目ばかりをやってしまいがちです。
でも、**苦手を避け続けても成績は上がりません。**なぜなら、苦手科目を後回しにしているうちは、常に「不安な分野」が残ったままだからです。
「やらなきゃ…」と思いつつも手が伸びない。 「わからないし、面倒くさい」と感じて、また先延ばし。 この繰り返しで、苦手意識がどんどん強くなってしまいます。
私も英語が苦手だった頃、「とりあえず理科からやろう」といつも先延ばしにしていました。 でも結局、英語の点数が足を引っ張って通知表の合計が伸び悩むことに。 苦手を後回しにすることで、自分の将来の可能性まで狭めてしまうこともあるんです。
なぜNGなのか?
- 苦手を放置すると点数がどんどん下がる
- 自信が持てず、ますます手を付けづらくなる
- 得意だけではトータルの成績が伸びにくい
- 高校受験では「苦手1科目」で合否が決まることもある
- 苦手科目があると、勉強そのものが嫌になりやすい
改善ポイント
- 「苦手こそ最初にやる」ルールを決める(最も集中力のある時間に)
- 簡単な問題から始めて、ハードルを下げる(小さな成功体験が大事)
- できないところを明確にして、そこだけに絞って取り組む
- 塾や先生、友達に積極的に質問する(聞くことは恥ずかしいことじゃない)
- 解けたら「できた!」と自分をほめて、ポジティブな印象を持つ
苦手科目=自分が成長できる最大のチャンスです。
苦手をひとつずつ克服することで、成績はもちろん、自信も大きく育っていきますよ!
6. 「ながら勉強」をしている

音楽やテレビをつけながらの勉強…本当に集中できてる?
BGMを流しながら、YouTubeをつけっぱなしで勉強していませんか? 「ながら勉強」は一見リラックスして勉強できそうに思えますが、集中力を大きく削ぐNG習慣のひとつです。
特に歌詞のある音楽や、映像が流れているテレビ・YouTubeは、無意識のうちに脳の処理能力を奪っていきます。 人の声や映像の変化は、思っている以上に私たちの注意を引きつけるんです。
私も中学生のころ、好きなアーティストの音楽を流しながらワークを解いていたことがあります。 その時は「集中できてる!」と思っていたのですが、実際に問題を解いたときの正答率は驚くほど低くてショックを受けました。
なぜNGなのか?
- 脳が複数の情報を処理しようとして疲れる
- 内容が頭に入ってこない
- 集中力が分散して効率が悪くなる
- 情報の記憶定着率が下がる(特に暗記系に弱くなる)
- 作業は進んでいるようでも、質が低くなりやすい
「ながら勉強」は、**勉強した“気分”**にはなれるのですが、成績にはほとんどつながらないのが現実です。
改善ポイント
- 静かな環境での学習を基本にする(図書館やリビングの一角などもおすすめ)
- 音が欲しいなら自然音やホワイトノイズにする(川のせせらぎ、風の音など)
- 「BGMがないと落ち着かない」という人は、環境音アプリを活用する
- エンタメは勉強後のご褒美にする(モチベーションアップにも!)
- タイマーを使って「30分だけ集中」→「5分休憩」のようにリズムを作る
大切なのは、「今は勉強だけに集中する時間」と「楽しむ時間」をしっかり分けること。
集中できる環境があれば、同じ1時間でも成果は何倍にもなります!
7. 覚えるだけで理解していない
「暗記=学習」と思っていない?
ワークの答えをただ覚えるだけ、英単語をひたすら詰め込むだけ… それではテストの応用問題に対応できません。
もちろん、暗記は学習のスタートラインとして大切です。しかし、それだけに頼ると、“使える知識”には育たないんです。
たとえば、数学の公式を暗記しても、「どんな場面で使うのか」「なぜその式になるのか」がわかっていなければ、ちょっとひねった問題に対応できません。
英語の文法も、「be動詞」「一般動詞」といったルールを丸覚えしても、実際の英文を読んだときに意味がつかめなければ意味がありません。
私自身も、英単語をひたすら書いて覚えていた時期がありました。でも、長文問題になると「意味は知ってるのに、内容が理解できない…」と感じることが多かったんです。それは、単語の意味だけにとらわれて文全体の構造や流れを理解していなかったからでした。
なぜNGなのか?
- 表面的な知識で終わってしまう
- 応用問題や記述式問題でつまずく
- 本質的な理解ができていないため、すぐ忘れる
- 問題の本質を見抜けないため、似たような問題でも正解できない
- 記憶の定着が浅く、繰り返し勉強することになって非効率になる
改善ポイント
- 「なぜそうなるのか?」を常に考える習慣を持つ(理屈で覚えると忘れにくい)
- 友達や親に説明してみる(=アウトプットで理解を深める)
- 図や表を使って関係性を理解する(歴史や理科などに効果大)
- 実際に問題を解く→解説を読んで「なぜそうなるか」を言語化
- 「暗記の前に理解」→理解してから覚えるとスムーズに頭に入る
覚えることは大事。でも、理解をともなった暗記こそが“テストで使える知識”になります!
しっかりと「自分の言葉で説明できるレベル」まで持っていくことを意識してみましょう!
8. 解答をすぐに見てしまう
わからないとすぐ答えを見ていませんか?
問題を解いていて「わからない…」と感じた瞬間に、つい解答を見てしまうこと、ありませんか? 答えを見れば一瞬で正解がわかるので、安心できますよね。
でも、その一瞬の「安心感」は、学力にはつながりません。
私も以前、難しい数学の問題にぶつかるたびに、すぐに答えを見て「なるほど!」と納得していました。 しかし、いざ同じような問題がテストに出たときに、全く解けなかったんです。 それは、答えを見たことで「理解した気」になっていたけれど、本当の意味で自分の力で考えていなかったからなんです。
なぜNGなのか?
- 自分で考える力が育たない(試行錯誤がない)
- 思考のトレーニングができない(「なぜ」を深掘りしない)
- 同じ問題でまた間違える可能性が高い(記憶に残りにくい)
- 解答への依存が強くなり、自信が育たない
- 問題解決の「プロセス」を身につけられない
答えを見るだけでは、脳はあまり働いていません。 逆に、1分でも2分でも「なんとか自分で答えを出そう」と粘ることで、脳はフル回転し、理解も深まります。
改善ポイント
- 最低3分は考えてから答えを見る(タイマーを使うのもおすすめ)
- どうしてその答えになるのかを自分の言葉で説明する練習をする
- 間違えた理由をしっかり分析して、ノートに「失敗メモ」を残す
- 次に同じ問題を解くときは、何も見ずにチャレンジしてみる
- 「答えを見る=最後の手段」と考えて、まずは自分で全力を尽くす
解答を見るタイミングはとても大切です。 わからないからすぐ見るのではなく、「ここまでは自分でやってみた!」という自信を持てる状態で答え合わせをすること。
それが、本当の意味での“学力を伸ばす勉強法”です!
9. 時間管理ができていない

ダラダラ勉強、直前になって焦る…
勉強時間を決めず、気が向いたときだけ勉強するスタイルでは、成績は安定しません。 「今日は疲れているからやめておこう」「明日まとめてやればいいや」などと先延ばしにしてしまうと、どんどん勉強がたまってしまいます。
特にテスト直前になってから「あれも、これもやってない!」と焦って詰め込もうとするのは非常に効率が悪く、精神的にも負担が大きくなってしまいます。
時間管理ができていないと、学習内容に偏りが出たり、復習のタイミングを逃してしまうことも。 そうすると、せっかく理解した内容も忘れてしまい、テスト本番で実力が発揮できないことに繋がってしまいます。
なぜNGなのか?
- 計画性がなく、やるべきことが終わらない
- 自信を持ってテストに挑めない
- 勉強が「面倒くさいもの」になってしまう
- 復習のタイミングを逃しやすく、知識が定着しにくい
- テスト前の追い込みで心も体も疲弊する
改善ポイント
- 1週間ごとの学習計画を立てる(曜日ごとに教科を分けると◎)
- 「〇時から〇時まで」と時間を決める(毎日同じ時間帯にすると習慣化しやすい)
- ToDoリストを活用して進捗を見える化(達成感も得られる)
- タイマーを使って集中時間を管理(25分集中+5分休憩など)
- 1日の終わりに「今日やったこと」を振り返る習慣を持つ
10. 「わかったつもり」で終わっている
「あー、それ知ってる」で満足してない?
授業で先生の話を聞いて「なるほど!」と思っても、
実際に問題を解けないなら、それは**“わかったつもり”**かもしれません。
この「わかったつもり」は、意外と気づきにくいのが厄介なポイントです。 話を聞いて納得している状態でも、それを実際にアウトプットできなければ意味がありません。
たとえば、理科の授業で「電流の流れ方」を理解したつもりでも、回路図の問題になると手が止まる…。 こうした経験は、誰にでもあるのではないでしょうか?
私も数学の授業で「わかった」と思っていた単元が、ワークの応用問題になるとまったく歯が立たないということがよくありました。 結局、「授業で聞いた=理解した」ではないということに気づきました。
なぜNGなのか?
- 理解と定着ができていない
- 本番の問題に対応できない
- 自信がつかず、勉強が苦手になる
- 「できた気持ち」だけが先行し、成績に反映されない
- 知識が浅いため、応用問題で対応できなくなる
「知っている」ことと「できる」ことには、大きな差があります。 本当に理解できているかどうかを確認するためには、実際に自分で問題を解いてみることが必要不可欠です。
改善ポイント
- インプットしたら必ず問題演習で確認する(5問でもOK)
- 「説明できるかどうか」で理解をチェック(家族や友達に解説してみよう)
- 模試や過去問などで実戦練習をする(出題形式に慣れることも大事)
- 間違えたところは「どこでつまずいたか」「なぜ間違えたか」を書き出して、原因を把握
- 同じ内容を別の問題形式で解いてみることで、本当の理解を深める
「わかったつもり」から一歩進んで、「自分の言葉で説明できるレベル」まで引き上げる。 それが、学力を確実に伸ばす秘訣です!
まとめ:正しい習慣で、勉強がもっと楽しくなる!
今回紹介したNG習慣、ひとつでも思い当たるものがあれば、それを変えるだけで成績アップのチャンスがあります!
大切なのは、
「量より質」 「やった気分」より「身につく勉強」
勉強は努力の方向を間違えなければ、必ず成果が出ます。
まずはできるところから、今日からひとつだけでも改善してみてください。
あなたの「わかる!」「できる!」が増えることが、勉強を楽しくする第一歩です!
一緒に、コツコツがんばっていきましょう!