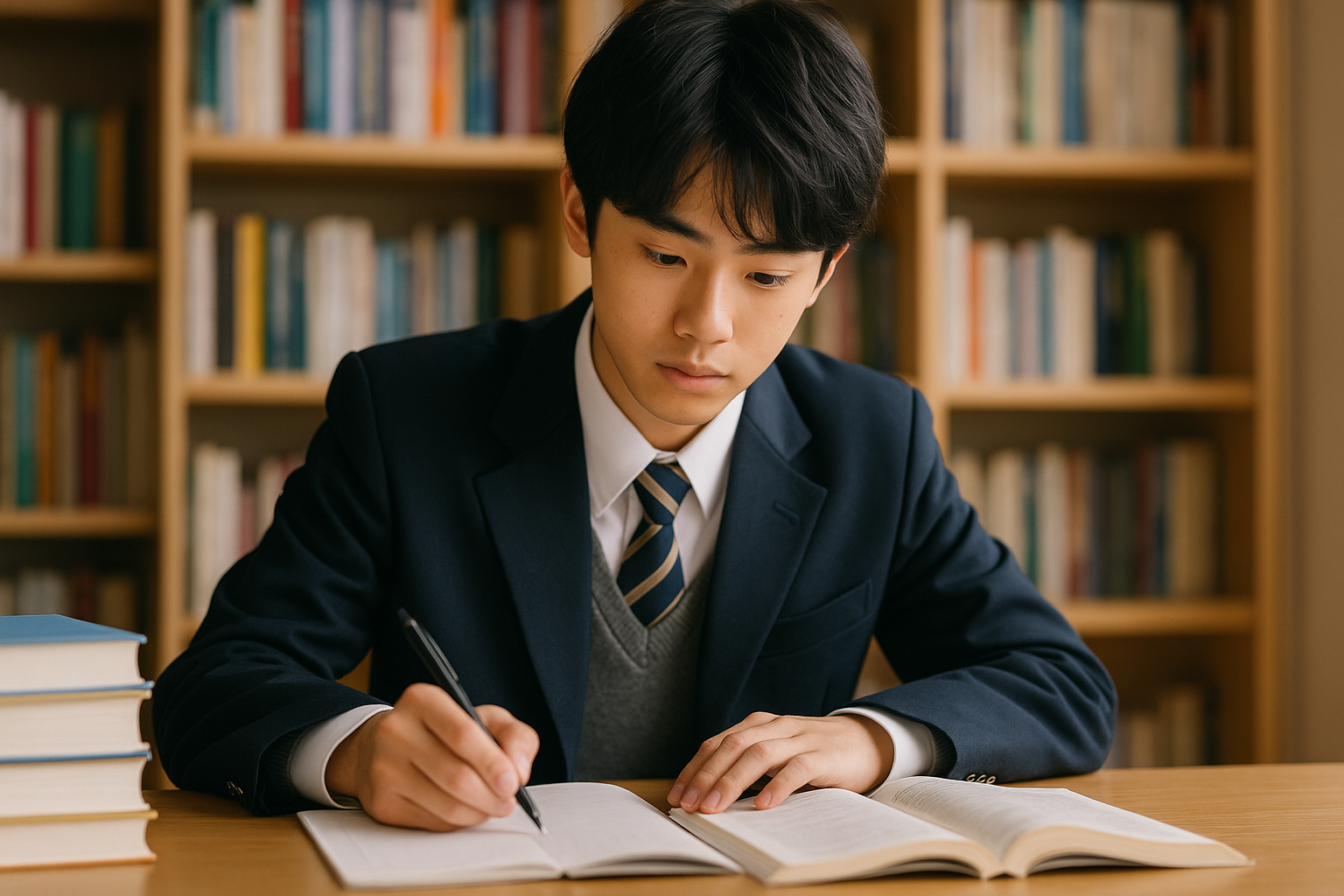はじめに
大学受験って、正直プレッシャーがすごいですよね。「どうやって勉強すればいいの?」「成績が伸びない…」「このままで間に合うの?」そんな不安を抱えている高校生は多いと思います。特に進学校に通っていても、周囲のレベルが高すぎて自信を失ったり、逆に学校の授業についていくのに必死で受験対策にまで手が回らない、という声もよく耳にします。
そんな中で大事なのは、「正しい努力」を「正しい順番」で積み重ねること。 この記事では、偏差値を着実に上げて合格に近づくための“黄金ルート”を、できる限りわかりやすく、かつ実践的にまとめました!
また、実際に偏差値30台から旧帝大に合格した人のリアルな勉強法や、学校や塾ではなかなか教えてくれない「勉強の効率を最大化する方法」も紹介しています。勉強時間をただ増やすのではなく、少ない時間でも最大限の成果を出す工夫が満載です。
この記事を読み進めることで、あなたの中で「今やるべきこと」が明確になり、不安から希望に変わっていくはずです。勉強って孤独な戦いのように感じますが、正しい道筋を知っているだけで、努力の方向性がグッと定まります。
それでは、一緒に受験勉強の道筋を確認していきましょう!あなたの夢の実現に向けて、最初の一歩を踏み出すお手伝いができたら嬉しいです。
高1・高2から始める受験勉強のメリット
早期スタートが未来を変える!
多くの高校生が受験勉強を本格的に始めるのは高3から。しかし、実は高1・高2の過ごし方が合否を左右すると言っても過言ではありません。
この時期は、部活や学校行事なども多く、なかなか勉強の優先順位を上げにくいかもしれません。でも、**今こそ「差をつけるチャンス」**なんです。他の人がまだ本気になっていない時期だからこそ、少しでも先に始めることで後々大きなリードになります。
なぜ早く始めた方がいいの?
- 学力の土台をじっくり築ける
- 苦手科目に時間をかけて克服できる
- 高3での演習時間をしっかり確保できる
- 勉強習慣が身につき、受験モードにスムーズに移行できる
- 模試で早期に成績が安定し、志望校の見通しが立ちやすくなる
特に英語や数学などは積み重ねの教科。高1・高2のうちに基礎をしっかり固めておけば、あとで応用・発展にスムーズに移れますし、焦る必要もありません。
また、暗記科目(日本史・世界史・生物など)も少しずつ触れておくことで、受験期の負担がグッと減ります。
私の体験談
私は高2の夏から英語と数学に力を入れました。初めは勉強時間の確保が難しく、部活と両立するのが大変でしたが、通学時間を使って英単語を覚えたり、土日は予備校の授業に集中したりと、スキマ時間を意識して工夫しました。
結果、基礎がしっかりしたおかげで高3では演習に集中でき、模試の偏差値が60台までアップしました!特に英語は「読む→聞く→書く→話す」の4技能を意識した勉強法を取り入れたことで、長文読解が得意になり、自信につながりました。
今思えば、早く始めたからこそ、高3になってから焦らず「やるべきこと」に集中できたと実感しています。
偏差値を上げるための3ステップ戦略
Step1:基礎固め(高1〜高2)
この段階では、**「インプット中心の学習」**がメインです。まだ受験まで時間がある時期だからこそ、焦らずじっくりと学力の土台を固めていくことが重要です。
- 教科書の内容を完璧に理解する(穴埋めではなく、説明できるようになるまで)
- 定期テストを活用してインプット力アップ(「テスト前だけ」ではなく、復習にも力を)
- 用語や公式の暗記に時間を使う(意味や背景も理解しながら)
- 学校の授業ノートを見直す習慣をつける(1週間以内の復習が効果的)
- 映像授業や参考書を活用して自分のペースで理解を深める
Step2:応用力の養成(高2後半〜高3前半)
基礎がある程度固まったら、ここからは**「アウトプット強化」**の段階です。問題演習を通じて、知識を使いこなす力を育てていきましょう。
- 応用問題や記述式問題に挑戦(思考力・表現力が問われる)
- 問題集を繰り返し解く(3周以上が目安。一度間違えた問題は必ず再チェック)
- 解いた問題は「なぜその解法なのか」を説明できるレベルを目指す
- 自分専用のミスノートを作って弱点を可視化
- 週1回、解いた問題を振り返る時間をつくる
Step3:実戦演習(高3後半)
いよいよ受験本番が近づくこの時期は、「合格点を取る力」を鍛える時期です。時間配分、解答順、志望校の出題傾向など、実戦を意識した勉強が必要になります。
- 過去問演習で時間配分に慣れる(入試本番と同じ時間で解く)
- 志望校別対策に力を入れる(形式・難易度・頻出分野を分析)
- 過去問→復習→類題演習のサイクルを繰り返す
- 模試の結果から弱点分野を分析して対策
- 書く力を鍛えるため、記述問題や小論文の練習も取り入れる
この3ステップを順に踏んでいくことで、ただ闇雲に勉強するのではなく、目的意識を持って効率よく偏差値アップを狙えます!大切なのは、「今自分がどのステップにいるのか」を常に意識すること。迷ったらこのステップに立ち返ってみましょう。
英語の偏差値を爆上げする勉強法

まずは「単語力」が命!
英単語がわからないと、長文も文法も意味がない…と言っても過言ではありません。英語の成績を伸ばしたいなら、まずは単語力の強化が絶対条件です。なぜなら、単語が分からなければ文章の内容を正しく理解することができず、文法問題やリスニングでも苦戦することになるからです。
おすすめのやり方
- 毎日100語を3セット(朝・昼・夜)で復習
- 単語帳は1冊を完璧に仕上げる(周回重視)
- 音読+書いて覚えると記憶の定着率アップ
- 間違えた単語は「間違いノート」にまとめて、定期的に見直す
- 通学時間やスキマ時間をフル活用して反復練習する
単語学習において大切なのは、「どれだけたくさん覚えたか」ではなく、「何度繰り返したか」。同じ単語帳を何度も周回し、目にした瞬間に意味が浮かぶレベルまで仕上げるのが理想です。
長文読解は「音読+精読」で攻略!
長文が苦手なら、まずは音読→精読→和訳の順で取り組むと効果的です。ただ読むだけではなく、一文ずつ文構造を分析し、意味を丁寧に理解する癖をつけましょう。
長文読解のトレーニング方法
- 文章を声に出して読む(音読):リズムと構文感覚が身につく
- 一文ごとに構文をチェックする(SVOCや関係詞など)
- 和訳して正確に理解できているか確認する
- 同じ長文を繰り返し読み、内容を暗記するほどまで読み込む
- 読んだ長文の要約を日本語または英語で書いてみる
読む量をこなすのも大切ですが、まずは「1文1文を正確に読む力」を養うことで、速読力も自然に伸びていきます。
私のアドバイス
私は『速読英単語』を音読して暗記しました。音と意味をセットで覚えると、模試での長文スピードが格段に上がりました!また、音声CDやアプリを活用して、リスニング対策も同時に行っていました。耳と目で同時にインプットすることで、英語の感覚がぐっと身につきました。
さらに、英語のニュースサイト(例えば「NHK WORLD」や「BBC Learning English」など)を日常的に読む習慣をつけたことで、英語に対する抵抗がなくなり、自然と語彙力もアップしました。
英語力はすぐには伸びませんが、毎日の積み重ねで確実に伸びていきます。 焦らず、でも着実に続けることが成功へのカギです!
数学の偏差値を上げるためのコツ
とにかく「理解」→「演習」→「解説確認」
数学は、暗記ではなく「理解すること」がスタート地点です。公式や定理をただ丸暗記するのではなく、なぜそうなるのかを自分の言葉で説明できるようになることが、応用力につながります。
効率的な勉強サイクル
- 教科書や参考書で基本を理解(図やグラフを自分で書いて確認すると理解度アップ)
- 問題を解く(できるだけ自力で。分からないときはすぐに答えを見ず、ヒントを探す)
- 解説を読んで再確認(「なぜそうなるのか」「他の解法はないか」も考えてみる)
- 間違えた問題は「ミスノート」にまとめ、類似問題で再チャレンジ
このサイクルを徹底することで、単なる作業ではなく“考える習慣”が身につきます。特に記述式の問題では、途中式や根拠を言語化する力が重要になります。
1日1題でも“質”を意識して
数学は「質」が命。解いた問題の量よりも、どれだけ深く考えたかが成績に直結します。
- わからなかったら放置せず、解法を「理解」して「再現」できるようにする
- 1日1題でもOK。丁寧に、解答への過程を自分で語れるレベルを目指そう
- 同じ問題を数日後に再挑戦して、定着度をチェック
- 苦手分野はあえて「時間をかけて」克服する
さらに、応用問題を解く前に「基本問題を完璧に」することも忘れずに。数学が得意な人ほど、基礎を軽視せず繰り返し確認しています。
私自身、数学が苦手だった頃は「とにかく問題数をこなせばいい」と思っていましたが、あるとき1問に1時間かけて取り組んだ経験が大きな転機になりました。そこから成績が安定し、模試でも初めて偏差値60を超えることができました。
地道ですが、**数学の力は確実に積み上がっていくものです。**毎日の小さな努力が、将来の得点力につながります。
国語(現代文・古文・漢文)の戦略
現代文は「読解の型」を身につける
現代文は「なんとなく読めるけど、設問で間違える」という声がとても多い科目です。だからこそ、**“感覚ではなく技術で読む”**という意識が大切です。
読解のポイント
- 接続詞や指示語に注目する(「しかし」「つまり」「この」など)
- 筆者の主張を見極める(感情ではなく論理的な構造を見る)
- 段落の役割を理解する(主張、例示、反論など)
- 問題文を先に読むことで、どこに注目すべきかが明確になる
また、評論文と小説ではアプローチが異なります。
- 評論文:論理展開とキーワードに注目
- 小説文:登場人物の心情変化と情景描写に注目
現代文が得意になると、他教科の記述力にも良い影響が出ます。思考力を鍛えるという意味でも、積極的に取り組みたい教科です。
古文・漢文は「単語+文法+音読」
古文と漢文は、「文語」という現代とは違う言語体系を持つため、まずは**“言葉を読む準備”**を整える必要があります。
古文攻略法
- 古文単語は毎日10個ずつ暗記(例文付きの単語帳がベスト)
- 助動詞・助詞の意味と活用を完璧に(接続の確認も)
- 主語補充・現代語訳の練習で理解力アップ
- 和歌や敬語のルールも軽視せず、少しずつ覚える
- 音読で文章のリズムを掴むことで、読解スピードが上がる
漢文攻略法
- 返り点と訓点の読み方に慣れる(レ点・一二点など)
- 重要句法(受け身、疑問、反語など)を整理して覚える
- 書き下し文を正しく訳せる練習を重ねる
- 音読で漢詩や故事のリズム感を体で覚える
私自身、最初は古文も漢文もチンプンカンプンでしたが、毎日音読しているうちに文章のリズムが身体に染みつき、自然と意味が取りやすくなりました。特に古文単語と助動詞の反復練習は効果絶大です。
国語はセンスではなく、**“正しい型を身につけること”**で誰でも伸ばせる科目です。毎日少しずつ触れ続けることで、必ず得意科目に変わります!
理科・社会の効率的な暗記術

理科は「なぜ?」を考える
理科の勉強は、単なる暗記にとどまらず、「なぜそうなるのか?」という根本的な理解が重要です。特に物理・化学では、公式の意味や現象の背景を知ることで、問題に対する応用力が格段に上がります。
理科を理解するためのコツ
- 公式の導出過程を理解する(例:加速度=速度÷時間)
- 実験動画やシミュレーションを活用して、現象を「見て理解」する
- 自分で図を描いて、イメージしながら整理する
- 間違えた問題は「どの概念が抜けていたか」を分析して復習する
- 過去問を解いて「よく出るパターン」を把握する
たとえば、化学のモル計算も、ただ公式に当てはめるのではなく、「物質量が何を意味しているか」「質量や体積とどう関係しているのか」を理解することで、苦手意識が薄れていきます。
私自身、理科は最初とても苦手でしたが、「自分で図を描くこと」と「解説を声に出して読むこと」で、理解のスピードが一気に上がりました。理科は、理解した分だけ楽しくなる科目です!
社会は「ストーリーで覚える」
社会科目は覚える量が多くて大変…という印象を持っている人も多いと思います。でも、単なる暗記ではなく、「物語として覚える」ことが記憶の定着に大きく役立ちます。
効果的な暗記のコツ
- 人物や事件の「背景」「理由」「影響」まで一緒に覚える
- 年号はリズムで暗記 or 語呂合わせを活用(例:「鳴くよウグイス平安京」)
- 地理は地図とセットで覚える。気候・産業・地形の関連を図に描く
- 一問一答だけでなく、記述練習もしてアウトプットを強化する
- 用語を自分の言葉で言い換えて説明できるようにする
特に歴史は、教科書を「読む」のではなく、「読んで話す」練習をすると効果的です。ストーリーで覚えると、忘れにくく、記述問題にも強くなります。
私は日本史を選択しましたが、語呂合わせで年号を覚えるだけでなく、「なぜその戦いが起きたのか?」「その後どう変わったのか?」という因果関係を意識するようになってから、模試の点数が安定しました。
社会は知識の整理と繰り返しがカギです。楽しんで取り組めば、きっと得点源になりますよ!
志望校別の対策法
難関大を目指すなら
難関大学(旧帝大、早慶、国公立医学部など)を目指す場合は、高度な思考力と持続的な学習戦略が必要不可欠です。ただ単に問題を解くだけでは足りません。
- 過去問10年分を分析(頻出テーマ・出題形式・難易度を徹底把握)
- 問題の「出題者の意図」を読み取る練習をする
- 記述力と論理的思考力を鍛える(現代文・数学・理系小論文など)
- 模試や添削を活用して客観的なフィードバックを得る
- 合格者の体験談を参考にして、勉強時間配分や教材選びを最適化
また、「自分の得点源」になる科目を1つ以上つくることも重要です。全科目を平均的に仕上げるよりも、強みを持った科目があると、合格ラインを突破しやすくなります。
中堅大なら
中堅大学(地方国公立・MARCH・関関同立など)を目指す場合は、基礎から標準レベルの徹底演習と、確実な得点力の養成がカギになります。
- 標準問題の徹底演習(教科書レベル+センター・共通テスト形式)
- 解答スピードの強化(時間制限を意識した演習)
- 問題パターンを体で覚えるまで繰り返す
- 教科別に頻出単元を把握して「出るとこ集中」型の対策を行う
- 自己採点と弱点分析をセットで実施し、無駄な時間を減らす
中堅校入試では、「取りこぼしをなくす力」=合格力です。難問に飛びつくより、まずは確実に取るべき点を落とさないように意識して対策を進めましょう。
どちらの志望校であっても、「志望校の出題傾向」と「自分の強み・弱み」を照らし合わせた学習戦略が合格への近道です。
模試の活用法と復習術
模試は“受けるだけ”じゃ意味がない
模試を受けるだけで終わってしまっては、本当にもったいない! 大切なのは、模試後の復習と振り返りの質です。
効果的な模試の活用術
- 間違えた問題をノートにまとめる(「ミスノート」や「復習ノート」を活用)
- 解説を読み込んで「なぜ間違えたか」を分析(知識不足?ケアレスミス?)
- 正解した問題も「運よく合っていた」可能性があれば見直す
- 各教科ごとに「次回までに改善すべき点」をメモする
- 同じ問題が再び出たら確実に解けるように、類題で再演習する
復習ノートの作り方
- 日付・教科・出題内容・間違えた理由・正しい解法・次回の対策を記入
- 自分の弱点が「見える化」され、計画的に改善しやすくなる
- 定期的に見直すことで、繰り返し学習に活かせる
模試は“チェックポイント”であり、“自己分析ツール”です。点数に一喜一憂するのではなく、次に活かすための材料としてフル活用しましょう。
偏差値が下がっても落ち込まない!
模試の結果が振るわなかった時、落ち込んでしまう気持ちはとてもよくわかります。でも、模試はあくまで通過点。本番で合格点を取ることが最終目標です。
偏差値が下がったときこそ、何をどう立て直すかが合格への分かれ道になります。
- 弱点を明確にできるチャンスと捉える
- 他人と比べるのではなく、前回の自分と比べて成長を見つける
- できた問題は「自信」に、できなかった問題は「改善点」に
私も模試で何度も失敗しましたが、そのたびに「どうしたら次は間違えないか?」を考え、ノートにまとめることで成績が安定していきました。
大事なのは“模試を糧にする姿勢”です。 あなたの努力は模試の点数だけでは測れません。継続することで、必ず結果はついてきます!
スマホとSNSとの付き合い方
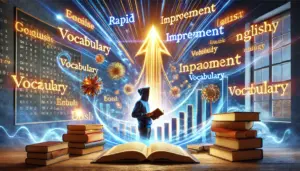
勉強の天敵? いや、味方にもなる!
「スマホ=悪」と思いがちですが、実は使い方次第で最強の勉強ツールにもなります。スマホには、情報収集・学習・モチベーション維持など、受験勉強に役立つ要素がたくさん詰まっています。
活用の工夫
- 勉強アプリで単語チェック(英単語・古文単語・計算トレーニングなど)
- SNSでモチベ仲間とつながる(TwitterやInstagramで勉強垢を作るのも◎)
- YouTubeやPodcastで学習系チャンネルを活用(英語のリスニングや理科の解説など)
- タイマーアプリでポモドーロ学習法を実践
- 手書きノートアプリで暗記カードをデジタル管理
SNSでは、同じ受験生の頑張りを見ることで「自分も頑張ろう」と刺激を受けることができます。勉強記録を投稿することで、習慣化しやすくなるというメリットも。
ただし、注意点もあります。
使いすぎには注意!
便利なスマホも、使い方を間違えると集中力を削ぐ原因になります。
- 勉強中にLINEや通知が来ると、集中が途切れてしまう
- SNSを見ているうちに、気づけば1時間以上経っていた…なんてことも
そんなときは、スマホの「スクリーンタイム制限」や「集中モード」機能を活用しましょう。自分で時間を制御できない場合は、タイムロックアプリ(例:Forest、Focus To-Doなど)もおすすめです。
私の体験談
私自身も、受験期にSNSに時間を取られがちでした。でも、勉強アプリを導入したり、スマホは机に置かず別の部屋に置いたりと工夫することで、集中力を保てるようになりました。また、SNSで同じ志望校を目指す仲間を見つけて励まし合えたことも、大きな支えになりました。
スマホは使い方次第で敵にも味方にもなります。“スマホに使われる”のではなく、“スマホを使いこなす”意識を持ちましょう!
メンタル管理も合格には欠かせない
ストレスとの向き合い方
受験勉強は長期間にわたるため、ストレスとの付き合い方がとても重要になります。放置してしまうと集中力が落ちたり、体調にまで影響してしまうことも。
おすすめのリラックス方法
- 深呼吸や軽いストレッチで心と体をほぐす(勉強の合間に数分でOK)
- 軽い散歩や運動を取り入れて、脳をリフレッシュさせる
- 瞑想アプリ(例:Meditopia、Inscapeなど)で心を整える
- 不安なときは紙に書き出して、頭の中を整理する
- 誰かに話してみる(友達、家族、先生など)ことで気持ちが軽くなることも
「今日は全然集中できなかった…」という日があっても大丈夫。人間ですから波があるのは当然です。大切なのは、落ち込まず次にどう切り替えるか。
自分を褒める習慣を
受験は**“他人との戦い”ではなく、“自分との戦い”です。他人と比べて落ち込むのではなく、「昨日の自分を超えられたかどうか」**を大切にしてみましょう。
自己肯定感を高める習慣
- 「今日も頑張った!」と毎日声に出して自分を褒める
- できたことをメモする習慣を(例:「単語200語復習できた!」)
- 日記や勉強記録をつけて、小さな進歩に気づく
- ご褒美タイムをつくる(週末に好きな映画を見る、好きなおやつを食べるなど)
私も受験期は不安で眠れない日がありました。でも、毎日寝る前に「今日もよく頑張った!」と声に出すことで、気持ちが落ち着き、前向きな気持ちで次の日に臨めるようになりました。
心の健康は、合格を勝ち取るための土台です。 メンタルが安定していれば、集中力も維持しやすく、継続も苦になりません。勉強と同じくらい、自分を大切にしてあげてくださいね。
最後まで伸びる人の共通点
諦めない姿勢と継続力!
どんなに成績が悪くても、最後までやり抜く人が合格をつかみます。 大切なのは、途中であきらめず、失敗しても前に進み続けることです。
受験勉強には波があります。成績が伸び悩む時期もあれば、スランプに陥ることもあるでしょう。でも、「やめなかった人」だけが最後に結果を出せるというのは、多くの合格者に共通する事実です。
勉強においては、「できない時間をどう過ごしたか」が成功のカギになります。モチベーションが下がったときも、ペースを落としてもいいから続けること。1日10分でも、単語を1つでも、積み重ねは必ず自分の武器になります。
実際に合格した先輩たちの声
- 偏差値40台から半年で合格:「毎日、前日の自分に勝つ」を意識してやり抜いた
- 毎日コツコツを1年続けて第一志望へ:「周りが遊んでいる時間に、15分でもやる」ことを続けた
- 成績が落ち込んでも諦めずに勉強を続けた結果、最後の模試で志望校A判定を獲得
- 目標を紙に書いて毎日見返すことで、気持ちをリセットしてモチベを維持した
あなたにも必ずできる!
今の成績がどうであれ、本気で「合格したい」と思う気持ちがあるなら、そこから始まります。
小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな結果につながる。あなたも、今日からその一歩を踏み出してみてください。どんなに遅く感じても、「続ける人」こそが最後に笑います。
受験という長い道のりを、一緒に最後まで走り抜きましょう!
まとめ|今日から始める「偏差値アップ習慣」
受験勉強は長くて不安も多いけれど、正しいやり方で積み重ねていけば、確実に力になります。 成績が思うように伸びない時期があっても、焦らずコツコツ続けることが成功への近道です。
「やらなきゃ」と分かっていても、最初の一歩がなかなか踏み出せないこともあるかもしれません。だからこそ、“小さく始める”ことがとても大切なんです。まずは今日、この瞬間から動き出すことで、あなたの未来は確実に変わります。
最後に、今日からすぐに実行できる行動を紹介します。どれも簡単だけど、確実に効果があるものばかりです。
✅ 今すぐ始めたい!3つの行動
- 単語帳を1冊決めて持ち歩こう(1日10語からでもOK!)
- 模試の復習ノートを作ってみよう(まずは前回の模試から振り返ってみよう)
- スマホの使用時間を1日1時間減らしてみよう(その分を読書や音読に充てよう)
さらに余裕があれば、こんなことも!
- 勉強スケジュールを紙に書いて見える場所に貼る
- 自分だけの「やる気が出る言葉」を書き出して毎日見よう
- SNSの通知をオフにして、集中できる環境を整える
どれか一つでも、「今すぐ」やってみてください! 小さな行動の積み重ねが、大きな成果につながります。
あなたの努力は、決して無駄になりません。今日のあなたの選択が、数ヶ月後の未来を変えます。誰にでも不安はあるけれど、動き出した人から結果が出る。
受験勉強の旅は大変ですが、あなたにはそれを乗り越える力があります。
一緒に最後まで頑張っていきましょう!応援しています📚✨