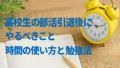はじめに:進路選びに悩む高校生へ
高校生活も後半に差しかかってくると、多くの高校生がぶつかるのが「進路選び」という大きなテーマです。「大学に進学すべき?」「専門学校ってどんな感じ?」「すぐに就職するってどうなんだろう?」と、選択肢が多いからこそ、かえって混乱してしまうのが現実です。友達はもう決めているのに、自分はまだ決まっていない…そんな焦りを感じている人もいるかもしれません。
実際、どの進路にもそれぞれの良さや注意点があり、「これが正解!」という答えは存在しません。大切なのは、自分の価値観や将来の目標に合わせて、一番納得できる選択をすること。この記事では、大学進学・専門学校・就職という3つの進路について、具体的なメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。
また、進路選びを考えるうえで大切な「自己分析の方法」や「将来の目標の見つけ方」、さらには「親や先生との上手な相談の仕方」や「高校生のうちにやっておくべきこと」まで、幅広く取り上げています。さらに、私自身の経験や、身近な友人たちのリアルな進路選択エピソードも紹介していくので、きっと自分の状況に近い話も見つかるはずです。
進路に迷っているあなたが、「これなら自分にもできそう」「少し前向きになれた」と感じられるような、そんなガイドを目指してこの記事を作成しました。読んでいく中で、少しでも自分にぴったりな道を見つけるヒントになれば嬉しいです!
大学進学のメリットとデメリット
メリット:選択肢が広がる
- 幅広い学問に触れられる
- 就職の選択肢が増える
- 社会人になる前の準備期間になる
- 人脈が広がる
- 自由な時間の中で自己成長ができる
大学進学の最大の魅力は、学びの幅広さと将来への選択肢が広がることです。高校までの勉強と違い、大学では自分の興味関心に合わせて学科や授業を選べる自由があります。経済学、心理学、国際関係、芸術など、今まで触れたことのなかった分野に挑戦することも可能です。
また、大学生という身分は社会的にも認められやすく、アルバイトやインターンシップなど、社会経験を積む機会も豊富です。自分でお金を稼ぐ経験や、実際の職場での体験は将来の仕事選びに大きく役立ちます。大学では多くの学生や教授、外部の人とも出会えるため、人間関係や人脈作りの場としても非常に価値があります。
大学生活は勉強だけでなく、部活動やサークル、留学、ボランティアなど、自分の興味を広げられる貴重な時間でもあります。自由度が高いため、自分で何をするかを選び、自己管理能力を高めることができます。こうした体験が、社会人として自立するための大きな土台となります。
デメリット:学費と時間がかかる
- 学費が高額(私立だと年間100万円以上も)
- 目的が曖昧だとモチベーションが続かない
- 卒業後の就職も保証されているわけではない
- 自由すぎて生活がだらけるリスクもある
大学進学には、金銭的・時間的なコストがかかります。特に私立大学では年間100万円以上の学費がかかることも珍しくなく、家庭の経済的な負担になるケースもあります。また、大学生活が4年間と長いため、その期間をどのように過ごすかによって、その後の人生が大きく左右される可能性も。
目的がはっきりしていないまま入学すると、モチベーションを保てず、「なんとなく単位を取って卒業」ということになりがちです。さらに、大学を出たからといって、希望の就職先に必ず就けるとは限りません。就活には自己分析や業界研究、面接対策などが必要で、計画的に動かなければ内定を得るのも難しくなります。
また、自由な時間が多いぶん、自分を律する力が求められます。生活リズムが崩れたり、怠け癖がついたりすることで、せっかくの大学生活が無駄になってしまうこともあるのです。
専門学校という選択肢

実践的なスキルが身につく
専門学校は、特定の分野に特化した教育を受けられるのが魅力です。大学に比べて実習や演習の時間が多く、現場を想定した実践的な授業が中心になります。例えば美容師、デザイナー、看護師、調理師、保育士、ITエンジニアなど、専門職としての知識や技術をしっかりと身につけることができます。
高校の勉強が苦手でも「手を動かして覚えるタイプ」の人には、専門学校のカリキュラムが合っているかもしれません。また、2年間で卒業できる学校が多く、短期間で効率よく学べる点も魅力。さらに、講師の多くが現役のプロであることも多く、業界の最新情報や現場感覚を学べるのも大きなメリットです。
就職に強い
- 業界とのつながりが強い
- 資格取得のサポートが充実
- 卒業後すぐに現場で働ける即戦力に
- 就職率が高い(分野によっては90%以上も)
専門学校は、企業や業界とのコネクションが強いため、インターンや実習を通じて在学中に就職先とのつながりを築くことができます。また、資格取得を重視したカリキュラムが整っており、試験対策講座や個別サポートなどが充実している学校も多いです。
私の友人は専門学校でWebデザインを学び、在学中からフリーランス案件をこなしながらスキルを磨いていました。そして卒業と同時に制作会社に正社員として採用され、今ではクライアントから指名が入るほど信頼されるデザイナーに成長しています。大学に進学した私としては、早くから実践経験を積んでいる彼の姿を見て、「専門学校って本当に即戦力になるんだな」と実感しました。
さらに、専門学校の先生やキャリアセンターは、就職活動のサポートにも力を入れています。履歴書の書き方や面接練習、企業紹介など、個別対応が丁寧で、「ひとりじゃない」という安心感が得られます。
高卒で就職という道
メリット:早く自立できる
- 経済的な負担が少ない
- 社会人経験を早く積める
- 親に頼らず自分の力で生きていける
- 若いうちから責任感を持って行動できる
高卒で働くという選択は、「とにかく早く自立したい」「早くお金を稼ぎたい」「大学に行く意味が見いだせない」という明確な意思を持つ人にとっては、とても有効な選択肢です。学費をかけずに働くことで、親への経済的な負担を減らすことができ、自分で稼いだお金で生活を始めることができます。
また、社会人としての経験を人より早く積めるため、責任感やマナー、職場での人間関係の築き方など、学校では学べない実践的なスキルが自然と身につきます。若いうちから仕事の現場を知ることで、自分の適性や興味のある分野が明確になり、後から進学したり、資格取得を目指す際のモチベーションにもつながります。
私の友人は「早く稼ぎたい!」という強い意志で高卒就職を選びました。最初は覚えることが多くて大変そうでしたが、今ではしっかりと貯金をして、自分の夢であるカフェ開業に向けて準備を進めています。自分で未来を切り開いていく姿に、刺激を受けています。
デメリット:キャリアの選択肢が狭まることも
- 学歴で選考されることがある
- 転職時に不利になるケースも
- 学び直しが必要になることも
- 周囲と比べて不安になることがある
高卒での就職は、大学や専門学校での勉強を経ていないため、就職先によっては「学歴」で判断されることもあります。特に大手企業や公務員などでは、応募資格に「短大卒以上」が求められることもあるため、選べる仕事の幅が限定される可能性があります。
また、一度社会に出た後で「やっぱり別の仕事がしたい」と思ったときに、転職市場で学歴や資格が必要になる場面もあります。その場合は、通信制の大学や資格取得講座などを利用して、学び直すことが必要になることも。
さらに、高卒という進路を選んだあとで、周囲の友人たちが大学生活を楽しんでいる姿を見て、「自分はこのままでいいのかな?」と悩んだり、焦ったりすることもあるかもしれません。
それでも、最近ではスキルや経験を重視する企業が増えており、高卒でもしっかりとキャリアを築ける社会になってきています。努力次第で自分らしい道を切り開ける環境が整いつつあるのは、まさに今の時代ならではの魅力です。
自分に合った進路を選ぶには
自己分析が大事
- 興味のある分野は?
- 将来どんな生活をしたい?
- 勉強は好き?それとも実技派?
- どんな働き方をしたい?(安定志向?チャレンジ志向?)
- チームで動くのが得意?それとも一人で集中したい?
進路選びにおいて、まず一番大切なのは「自分を知ること」です。何をしているときに楽しいと感じるのか、どんな環境が自分に合っているのかを考えてみましょう。趣味や好きな科目、普段よく見ている動画のジャンルなどからヒントを得るのもおすすめです。
たとえば、「小さいころから料理が好き」「人を笑顔にするのが好き」と感じているなら、調理師やサービス業などの道もアリかもしれません。逆に、「数学が得意」「パソコンを使った作業が苦じゃない」という人なら、ITや工学系の分野が向いているかもしれません。
私は高校時代、「人と話すのが好き」「モノづくりが好き」という2軸で考え、自分がどんな場面でワクワクするのかを深掘りしていきました。その結果、メディア系の学部に進学することを決めました。初めて自己分析をしたときは正直戸惑いましたが、ノートに書き出していくことで、意外と自分の中に「答え」があったんだと気づきました。
家族や先生に相談してみよう
進路についてひとりで悩んでいると、どうしても視野が狭くなりがちです。そんなときは、家族や先生、信頼できる大人に相談してみましょう。話しているうちに、自分でも気づいていなかった考えや希望が見えてくることがあります。
家族はあなたの性格や得意なことをよく知っている存在ですし、先生は多くの卒業生の進路を見てきた経験があります。私も進路を考えたときに、担任の先生から「それなら◯◯って学部が合いそうだね」と具体的なアドバイスをもらい、選択肢が広がった経験があります。
また、信頼できる友達との会話も意外と参考になります。友達がどんな理由で進路を選んでいるのかを聞くことで、「そんな考え方もあるんだ」と新しい視点が得られることもあるからです。
将来の目標から逆算する

「やりたいこと」から考える
- 看護師になりたい → 看護専門学校や大学の看護学科へ
- プログラマーになりたい → IT系専門学校 or 情報系の大学へ
- 保育士になりたい → 保育系専門学校 or 教育学部へ
- ゲームクリエイターになりたい → デザイン・プログラミング系専門学校へ
- 海外で働きたい → 国際関係学部や語学留学を視野に
具体的な職業が明確になっているなら、逆算して「その職業に就くにはどんなスキルや資格が必要か」を調べ、それに沿った進路を選ぶことが重要です。例えば、看護師になるには国家資格が必須なので、看護師養成課程のある学校を選ぶ必要があります。プログラマーなら、大学でも専門学校でもスキルは学べますが、自分が理論重視なのか実践重視なのかによって選ぶ道は異なるでしょう。
実際にその職業についている人のインタビュー記事やYouTube動画を見たり、職業体験をしたりすることで、よりリアルなイメージが持てるようになります。また、必要なスキルだけでなく、「どんな働き方をしているのか」「将来的にどのようなキャリアパスがあるのか」なども確認すると、進路選びに具体性が生まれます。
一方で、「何がしたいのかまだよく分からない…」という人も少なくないでしょう。そんなときは、将来の選択肢が広がる大学進学を考えてみるのも一つの方法です。大学では4年間の中でさまざまな分野を学べるため、自分の興味関心を探る時間を確保できます。私の知人は大学入学当初は明確な目標がなかったものの、授業やサークル活動、インターンなどを通して徐々に方向性が定まり、卒業時には自信を持って就職先を選んでいました。
重要なのは、「やりたいことがある人も、まだ見つかっていない人も、自分なりの選び方ができる」ということです。どちらのケースでも焦らず、情報収集をしながら「自分に合った道はどれか」を見つけていく姿勢が大切です。
高校生活のうちにやっておきたいこと
体験してわかることも多い
- オープンキャンパスに行く
- 企業見学やインターンに参加する
- 学校の進路相談を活用する
- 資格や検定にチャレンジする
- ボランティアや地域活動に参加してみる
高校生のうちにできる経験は、将来の選択肢を広げる大きなヒントになります。例えばオープンキャンパスでは、学校の雰囲気や授業内容だけでなく、実際に通っている先輩の話を聞くことができるので、「自分に合いそうか」を直感的に判断する良い機会になります。私もいくつかの大学を回りましたが、「ここだ!」と思った学校に出会えたのは、実際に足を運んだからこそでした。
また、企業見学やインターンを体験することで、「社会で働くってこういうことなんだ」というリアルな感覚を得られます。職場の雰囲気や仕事内容を見るだけでも、自分に合う職種や働き方のイメージが湧いてきます。将来を考えるうえで、この「具体的に想像できる」ということはとても大切です。
学校内での進路相談も、意外と役に立つポイント。進路指導の先生は、過去の生徒の例や最新の進学・就職情報をたくさん持っていて、客観的なアドバイスをしてくれます。漠然とした不安や悩みも、誰かに話すことで整理されることが多いですよ。
さらに、時間があるなら、興味のある分野に関する資格取得や検定試験に挑戦してみるのもおすすめです。将来の履歴書にも書けるし、自分の「好き」や「得意」を証明する手段にもなります。たとえば、英語が得意なら英検やTOEIC、パソコンが好きならMOSなど、今から取れるものは意外とたくさんあります。
最後に、ボランティアや地域活動など、学校外での経験も視野を広げるチャンスです。人と関わる経験や社会との接点を持つことで、「自分がどんな人間なのか」を見つめ直すきっかけになります。実際に行動してみると、新しい興味が見つかったり、意外な自分の一面に気づけたりするかもしれません。
周囲の意見に流されないために
「みんなが行くから」は危険サイン
進路は、あなたのこれからの人生を大きく左右する選択です。周囲の友達が大学に行くからといって、必ずしも自分も同じ道を選ぶ必要はありません。「とりあえず大学に行く」「親がすすめたからこの専門学校にする」など、他人の目を気にした選択は、あとで後悔につながることも。
実際、私の友人で「流れに乗って大学に進学したけど、全然興味が持てなかった」と中退した子もいます。その子はその後、自分の興味を見つけて専門学校に入り直し、今では楽しそうに仕事をしています。最初の選択がすべてではないとはいえ、自分の気持ちを無視した決断は遠回りになることもあります。
自分の軸をしっかり持とう
- 情報収集を怠らない
- 必要なら一度立ち止まって考える
- メリット・デメリットを自分の視点で整理する
- 第三者に相談して冷静に判断する
誰かの意見に左右されすぎず、自分の価値観や考えをもとに進路を決めることがとても大切です。そのためには、まずは情報収集を徹底しましょう。パンフレットやWEBサイト、口コミなど、さまざまな情報を比較することで、自分にとってベストな選択肢が見えてきます。
また、どうしても決めきれないときは、無理に答えを出そうとせずに、一度立ち止まってみるのもアリです。「時間をかけてでも納得のいく進路を見つけたい」という姿勢は、決して間違っていません。
親や先生の意見ももちろん大切です。人生経験が豊富な大人の視点は、時に自分では気づけない視野を広げてくれることがあります。ただし、最終的にその道を進むのは「あなた自身」であり、その選択に責任を持つのもあなたです。だからこそ、自分の心の声を無視せず、「自分は本当はどうしたいのか?」をしっかり見つめることが大切です。
進学か就職か迷ったら「両方」もアリ?

最近では「高卒で就職→数年後に大学へ進学」や「専門学校を出てから大学へ編入」といったように、ひとつのルートに縛られず、複数の選択肢を組み合わせてキャリアを築く人が増えています。これは「どちらか一方を選ばなければいけない」という考えから解放される、柔軟なキャリア設計の例です。
例えば、ある友人は高校卒業後に企業へ就職し、数年間社会人として働いたのち、夜間大学へ進学しました。社会経験を積んだ後の学びは、より実践的で意味のあるものになり、仕事にも直結する知識が得られたと話していました。
また、専門学校で専門知識と技術を身につけた後、さらに理論や幅広い教養を学びたいと大学へ編入するケースも増えています。学びと働くことを交互に繰り返す「リカレント教育」という考え方も一般的になりつつあります。
柔軟なキャリア設計
- 通信制大学や夜間大学という選択肢も
- 社会人入試やリカレント教育制度の活用
- 働きながら学べる制度が整ってきている
- 企業による学費補助や研修制度を活用する
「今はこっち」と一度決めたとしても、あとで「やっぱり違った」と思った時に、方向転換しやすい社会になっています。通信制大学では、自宅で自分のペースで学べるため、仕事や家事と両立しながらでも学位取得が可能です。社会人入試を設けている大学も多く、年齢や背景に関係なく再チャレンジの機会が広がっています。
さらに、企業によっては社員のスキルアップを支援するために、学費補助制度や外部研修への参加制度を整えているところもあります。これらを上手に活用することで、「働きながら学ぶ」ことがより現実的な選択肢となっています。
今は、「高校卒業後にすべてを決めなくてはいけない」時代ではありません。大切なのは、自分のタイミングで、自分にとって必要な選択をしていくこと。選択肢は一つじゃないし、人生には何度でも学び直せるチャンスがあることを、ぜひ覚えておいてください。
高校生が知っておきたいお金の話
学費だけじゃない!進学にかかるお金
- 入学金、授業料、教科書代、交通費など
- 一人暮らしの場合は家賃や生活費も
- 実習や研修で発生する追加費用
- サークル活動や部活動などの自己負担も
大学や専門学校に進学するときに必要なのは、授業料や入学金だけではありません。教科書や参考書、ノートパソコンなどの学習用品費、定期券や交通費など、日々の通学にもコストがかかります。また、実習や研修が多い学部では、そのたびに必要な制服代や移動費が発生することもあります。
さらに、一人暮らしをする場合は、毎月の家賃、光熱費、食費なども大きな出費となります。特に都市部では家賃が高めなので、進学先の地域選びも経済面を考慮する必要があります。サークル活動やゼミ合宿、交際費なども含めると、想像以上にお金が必要になることが分かります。
奨学金や教育ローンを活用しよう
- 日本学生支援機構の奨学金
- 地方自治体や大学独自の支援制度
- 高校の先生に相談して情報を集める
- 無利子・給付型の制度を優先して検討
進学に必要なお金をどう準備するかは、多くの家庭にとって大きな課題です。日本学生支援機構(JASSO)が提供する奨学金制度は、利用者も多く、進学希望者の大きな味方です。無利子や返還義務のない「給付型」も増えており、成績や家庭の経済状況によって受けられる支援が異なります。
また、地方自治体や大学ごとに独自の奨学金や減免制度が用意されている場合もあります。これらは人数に限りがあることも多いため、早めの申し込みが必要です。学校の進路指導室や先生に相談すれば、こうした制度の詳細を教えてくれるはずです。
どうしても奨学金だけでは足りない場合は、教育ローンも一つの選択肢です。ただし、借りたお金は将来返す必要があることを忘れずに、無理のない範囲で利用することが大切です。返済シミュレーションをして、卒業後の生活も見越した計画を立てることがポイントです。
お金のことはちょっと話しにくいテーマかもしれませんが、だからこそ親としっかり向き合って話し合っておくことが重要です。進学の夢をかなえるために、今から準備しておけば安心してスタートを切れますよ。
情報収集のコツとおすすめサイト
信頼できる情報源を見極めよう
- 学校の進路指導室
- 文部科学省や大学の公式サイト
- 就職支援のポータルサイト
- 高校生向け進路情報誌やフリーペーパー
- 教育系の新聞や信頼あるWebメディア
進路に関する情報は、いろいろなところから入ってきますが、どれを信じればいいか迷うこともあるでしょう。そんなときは、まず信頼性のある公式情報を確認することが大切です。学校の進路指導室はもちろん、文部科学省や各大学・専門学校の公式サイトには、最新の入試情報や学費、カリキュラムなどが詳しく載っています。
また、「マイナビ進学」「スタディサプリ進路」「リクナビ進学」などのポータルサイトもおすすめです。これらのサイトでは、学校検索や資料請求ができるだけでなく、進路に関するコラムや体験談も掲載されていて、気軽に比較検討するのに便利です。
新聞や教育専門のメディアも役立ちます。大学改革や入試制度の変更など、タイムリーな教育ニュースをチェックしておくと、より良い判断ができるようになります。
SNSやYouTubeも使いこなそう
- 学生YouTuberや進学Vlog
- TikTokでのキャンパス紹介動画
- Instagramのハッシュタグ検索
- X(旧Twitter)でのリアルな感想
最近は、SNSやYouTubeを通じて、実際にその学校に通っている学生のリアルな声を聞くことができます。特にYouTubeでは、学校紹介動画やルームツアー、1日のスケジュールなど、学校生活の具体的なイメージを掴めるコンテンツがたくさんあります。
InstagramやTikTokでは、キャンパスの雰囲気や制服、イベントの様子が気軽に見られるので、「自分に合いそうかどうか」を判断する材料としてとても有効です。また、X(旧Twitter)では、現役学生が本音で進路や学校生活についてつぶやいていることもあり、生の意見に触れる貴重な機会になります。
ただし、SNSは情報の信憑性にばらつきがあるので、「参考程度」にするのがポイント。公式情報や他のメディアと照らし合わせながら、バランスよく情報収集をしましょう。
最後に:進路選びに正解はない!
進路について考えるとき、「これが正解!」という道を探したくなるかもしれません。でも、現実には一人ひとり価値観や状況が違うため、万人に共通する正解はありません。大切なのは、「自分で考え、自分で選んだ道を信じられるかどうか」です。
人生の道筋は一本道ではなく、分かれ道がたくさんあります。大学に進学する人、専門学校でスキルを磨く人、高卒で社会に飛び込む人。それぞれにメリットもあれば、課題もあるものです。だからこそ、自分が納得して選んだ道には、どんな進路でも価値があります。
進路選びは、未来の自分へのプレゼントでもあります。時間をかけて悩んでいいし、迷っても大丈夫。それだけ本気で考えている証拠です。時には「本当にこの選択でよかったのかな?」と不安になることもあるかもしれませんが、それも自然なこと。大事なのは、自分の気持ちに正直でいることです。
進路を決めるプロセスを通して、自分自身を深く知ることができます。そして、自分で決めたからこそ、その選択に対する責任と誇りを持つことができます。誰かの意見ではなく、自分の考えを軸にした選択こそが、あなたの人生を豊かにする第一歩になるのです。
すぐにできる一歩
- 興味のある分野を書き出してみよう
- オープンキャンパスに申し込んでみよう
- 進路について親や先生と話してみよう
- 気になる職業を検索して、必要な資格を調べてみよう
- 自分の「得意」や「好き」をノートにまとめてみよう
どんな道を選んでも、あなたの未来はあなた次第!今の選択が将来の可能性を広げてくれます。自信を持って、自分のペースで進んでいきましょう。あなたの努力は、きっと未来の自分にとっての大きな力になります。心から応援しています!