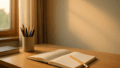- はじめに
- 1. 目標を明確にしよう!【モチベーションアップの第一歩】
- 2. 勉強スケジュールを立てよう【時間を味方につける】
- 3. 教科ごとの勉強法を工夫しよう【暗記・理解・演習】
- 4. 時間を区切って集中力アップ!【ポモドーロ・テクニック】
- 5. 覚えるコツは“アウトプット”!【ただ読むだけじゃNG】
- 6. 自分だけの“まとめノート”を作ろう
- 7. ワークや問題集は「3回解く」がカギ
- 8. スマホとの上手な付き合い方
- 9. 苦手科目の克服法【逃げずに向き合うコツ】
- 10. テスト直前の過ごし方【前日・当日の注意点】
- 11. 勉強を続けるための“ごほうび”ルール
- 12. 家族や先生と協力しよう!【一人で悩まない】
- まとめ:今日からできる一歩を踏み出そう!
はじめに
「テスト勉強、何から始めたらいいのかわからない……」そんな風に感じたことはありませんか?
中学生になると、教科も増えて勉強の難易度もグンと上がりますよね。部活動や習い事との両立で、なかなか勉強時間が取れないという人も多いはず。でも、ちょっとしたコツを知っておくだけで、短時間でも効率よく点数を上げることができるんです!
この記事では、実際に効果があったテスト勉強の方法を7つ厳選してご紹介します。さらに、勉強を続けるコツや集中力を保つ工夫、苦手科目への対処法なども盛り込んで、中学生がすぐに実践できる具体的なアドバイスをまとめました。
読めばきっと、「よし、やってみよう!」と前向きな気持ちになれるはず。ぜひ、最後まで読んでみてくださいね!
1. 目標を明確にしよう!【モチベーションアップの第一歩】
なぜ目標が大事なの?
テスト勉強を始める前に、まずは**「何のために勉強するのか」**を考えてみましょう。
- 〇〇高校に合格したい!
- 前回よりも5点アップを目指したい!
- 苦手な数学で平均点を超えたい!
目標があると、勉強のやる気が全然違ってきます。ゴールが見えていると、そこに向かって自然と行動できるようになるんです。
自分だけの目標を立てよう
目標は、他人と比べる必要はありません。自分なりに「これなら頑張れそう」と思える目標を立てることが大切です。
💡 ポイント:目標は“数字”で表そう! 例)「数学で90点取る」「英語の単語テストで満点を目指す」など
明確な数字があると、進捗もわかりやすく、達成感も得られやすいですよ!
2. 勉強スケジュールを立てよう【時間を味方につける】
いきなり問題集を解くのはNG!?
テスト前になると、「やばい!」と思って急に問題集に取りかかる人も多いですが、計画なしで始めると逆に効率が下がることも。
まずは、テストまでの日数を確認し、
- どの教科を、
- どの順番で、
- どのくらいの時間やるか
をざっくりでもいいので決めておきましょう。
スケジュールは“ざっくり”でOK!
完璧なスケジュールじゃなくても大丈夫! 大切なのは、自分のペースを把握しておくことです。
✅ スケジュールの例
- 月曜:英語の単語復習
- 火曜:数学のワーク1ページ
- 水曜:理科の教科書を読む
こうして毎日少しずつ取り組むだけで、直前に慌てることがなくなりますよ。
3. 教科ごとの勉強法を工夫しよう【暗記・理解・演習】

教科によってやり方を変える!
全部の教科を同じように勉強していませんか? それだと、なかなか成果が出にくいんです。教科ごとに求められる力が違うので、それに合わせた勉強法が必要です。
たとえば、暗記が大事な教科と考える力が求められる教科では、やるべきことがまったく違いますよね。効率よく点数を取るには、「その教科に合った方法」を意識することが大切です。
例:
- 英語・社会・理科(暗記重視): → 単語帳や一問一答を活用して、毎日短時間でも繰り返し覚える。 → 音読や自作クイズ、書いて覚えるなど、五感を使うのがおすすめ!
- 数学(理解&演習): → 公式をただ暗記するのではなく、「なぜその解き方になるのか」を理解することが重要。 → 教科書の例題→基本問題→応用問題の順に段階的に取り組むと◎。
- 国語(読解力・表現力): → 漢字や語彙は暗記、文章問題は読み取りのコツを掴む練習を。 → 新聞や読書で文章に慣れるのも、地味だけど効果大!
自分の得意・不得意に合わせてカスタマイズしよう
さらに一歩進めて、自分の得意・苦手ポイントに合わせて学習法をカスタマイズすると、もっと効果が出やすくなります。
たとえば英単語が覚えにくい人は、フラッシュカードやアプリを使ってテンポよく学ぶのが◎。逆に、数学の図形問題が苦手なら、図をたくさん描いて考える癖をつけるなど、工夫の仕方は人それぞれです。
💡 ポイント:苦手な教科ほど“具体的に何をするか”を決める!
自分に合ったやり方を見つけることで、「やればできる!」という自信につながりますよ。
4. 時間を区切って集中力アップ!【ポモドーロ・テクニック】
長時間勉強=集中している、ではない!
「2時間も机に座ってたのに、あんまり進んでない…」なんて経験ありませんか?
それは、集中できていない時間が多かったからかもしれません。長時間机に向かうこと自体は悪いことではありませんが、ただダラダラ座っているだけでは効果が薄くなります。実際、脳は一定時間を過ぎると注意力が低下し、効率が落ちると言われています。
ポモドーロ・テクニックとは?
ポモドーロ・テクニックは、イタリアの学生が考案したシンプルな学習法です。具体的には、
- 25分勉強
- 5分休憩
を1セットとして繰り返す勉強法。短い時間に集中することで、効率がぐんと上がります。
25分という区切りは「ちょっと頑張ればすぐ終わる」と思える絶妙な時間で、脳の集中力を保ちやすいと言われています。休憩をはさむことで、リフレッシュしながら次の25分に取り組むことができるのです。
ポイント
- タイマーを使って25分に集中!アプリやキッチンタイマーでもOK。
- 5分間はストレッチや水分補給でリフレッシュ!目を閉じて深呼吸するだけでも効果的。
- 4セット(2時間)続けたら、15〜30分の長めの休憩を取るとさらに効率UP!
どんな人におすすめ?
- 「集中力が続かない…」という人
- 「気づいたらスマホを触ってしまう」人
- 「長時間やっているのに成果が出ない」人
に特に効果的です。最初は25分もきついと感じたら、15分+5分から始めてもOK!慣れてきたら徐々に時間を伸ばしていくのもアリです。
🔥 短時間集中+休憩の繰り返しで、“ダラダラ勉強”から卒業しよう!
5. 覚えるコツは“アウトプット”!【ただ読むだけじゃNG】
インプットだけでは記憶に残らない
「教科書を読んだけど、覚えてない……」 そんなときは、覚えたことを自分の口で説明したり、ノートに書いたりしてみましょう!
これが“アウトプット”です。インプット=知識を入れる作業、アウトプット=知識を使う作業。どちらも大事ですが、特にアウトプットを増やすことで記憶が強くなります。脳は「使った情報」を優先的に保存しようとするからです。
おすすめのアウトプット方法
- 一問一答で自分にクイズ:通学中や休み時間に短時間でできる!
- 友達や家族に説明する:人に教えることで「自分が理解できていない部分」が明確にわかる。
- ノートに書き出してみる:ただ書くだけでなく、矢印や図を使って関連づけるとより効果的。
- 音読する:声に出して説明すると、耳と口を使うので記憶が長持ちします。
どう活用する?
たとえば歴史の年号を覚えるなら、「1600年に関ヶ原の戦い!」と自分にクイズを出す。理科の用語なら、友達に「光合成ってどんな仕組み?」と説明する。数学なら、問題を解く過程を声に出して解説してみる。こうしたアウトプット練習が、テスト本番の“説明する力”や“応用する力”につながります。
🧠 覚えた情報は、自分の手や口を使ってこそ記憶に残る!
アウトプット中心の勉強は、テスト本番でも応用がきく力がつきますよ!「思い出す練習」をすることが最大のポイントです。
6. 自分だけの“まとめノート”を作ろう

見返したくなるノートが勉強効率を上げる!
教科書や参考書に書いてあることを全部書き写すのは、時間もかかって非効率。しかも、見返したときに「結局教科書と同じだな」と感じてしまい、モチベーションが下がってしまうこともあります。
そこでおすすめなのが、**「自分が覚えたいところだけ」**をまとめたノート。これは、ただのノートではなく“オリジナル参考書”のような存在になり、短時間で重要ポイントを振り返るのにとても役立ちます。
まとめノートのコツ
- カラーを使って重要ポイントを区別(赤は超重要、青は要チェックなど)
- イラストや図を使って視覚的に覚える(理科の仕組みや歴史の流れなど)
- 自分の言葉で書く(教科書を丸写しせず、理解した内容を言い換える)
- ページごとにタイトルをつけて検索しやすくする
- 暗記用の赤シート対応にするとテスト直前に使いやすい
まとめノートを作るときの注意点
- 時間をかけすぎない:凝りすぎて本末転倒にならないように!
- 完璧を目指さず、まずは「ざっくりまとめる」ことを優先
- 定期的に見返して「ここは要らないかも」と思ったら削る勇気を持つ
✨ 「見るだけで理解できる」まとめノートが理想!
さらに、作ったノートを友達と見せ合うのもおすすめです。友達のまとめ方を見ると、「こんな表現の仕方があるんだ!」と新しい発見があり、自分のノートに取り入れるヒントになります。時には、友達同士でクイズを出し合いながらノートを使うと、楽しみながら復習できますよ!
7. ワークや問題集は「3回解く」がカギ
1回で完璧にしようとしない!
問題集を1回やっただけで安心していませんか? 実は、1回目は「わからないことを知る」時間なんです。だから間違えても落ち込む必要はありません。むしろ「ここが弱点なんだ」と気づくことが、成長への第一歩になります。
3回解くステップ
- 1回目:解けるか確認。間違いをチェック!
- できなかった問題には印をつけておく。
- どこでつまずいたのかを簡単にメモすると、後で役立つ。
- 2回目:間違えた問題だけ再挑戦!
- 1回目で印をつけた問題に集中する。
- 解けるようになるまで解説を読み直す、先生に聞く、動画で確認するなど方法を工夫する。
- 3回目:全体をもう一度、スラスラ解けるか確認!
- ここでほとんどの問題が解けるようになれば自信につながる。
- まだ間違えるところは「苦手リスト」にまとめて、テスト直前に再確認!
さらに効果を高める工夫
- 解くスピードを意識する:ただ正解するだけでなく、短時間で答えられるかも練習する。
- 時間をおいて復習する:1日後、3日後、1週間後に同じ問題をやると記憶が長持ちする。
- 友達と一緒に解き比べをして、解き方をシェアする。
🔁 「できるようになった」実感が持てるようになります!
繰り返し解くことで、自然と自信もついてきますよ。さらに、この方法を習慣化すると「テスト直前に慌てて解く」のではなく、「普段から力を積み重ねる」スタイルに変わります。そうすれば、テスト本番でも落ち着いて実力を発揮できるようになります!
8. スマホとの上手な付き合い方
スマホ=敵ではなく「使い方」次第!
スマホは便利だけど、つい触りすぎてしまって時間がなくなる……そんな経験ありませんか?SNSや動画、ゲームなど、気づいたら1時間以上経っていた…なんてこともよくありますよね。
でも、スマホ自体が悪いわけではありません。問題なのは「どう使うか」です。勉強中にスマホが気になるなら、**「使わない」ではなく「使い方を変える」**ことがポイントなんです。
おすすめの工夫
- タイマーアプリで時間管理:ポモドーロ・テクニックと組み合わせると最強!
- 単語帳アプリでスキマ時間活用:通学中や休み時間に使える。
- 集中モードで通知をブロック:LINEやSNSの通知が来ないだけで集中力は格段に上がる。
- 勉強用アプリでモチベアップ:勉強時間を記録して「見える化」するだけでやる気が続く!
さらに工夫できること
- 勉強時間は「スマホは別室」に置いておく。触れない環境を作るのが一番確実。
- どうしても触りたくなったら「ごほうび」として利用する。30分勉強したら5分だけSNSをチェックなどルールを作る。
- 友達と一緒に「スマホ封印チャレンジ」をすると楽しく続けられる!
📵 スマホは“敵”ではなく“便利な味方”。上手に使えば勉強効率を何倍にも高められます!
自分にとって最適な使い方を見つけましょう!
9. 苦手科目の克服法【逃げずに向き合うコツ】
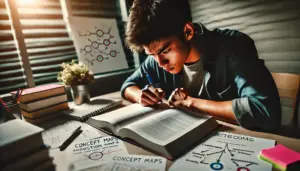
苦手を放っておくと、どんどん嫌になる!
誰にでも苦手な教科はあります。でも、「苦手だからやらない」は一番もったいない! そのままにしておくと、点数が下がるだけでなく、「自分はダメだ…」と自信を失ってしまうことにもつながります。逆に、苦手を少しずつ克服できれば「やればできる!」という自信が湧いてきます。
苦手科目は、「できた!」を積み重ねていくことが大事なんです。いきなり難しい問題に挑むのではなく、小さなステップを繰り返すことで、気づけば得意に近づいているはずです。
苦手克服のステップ
- やさしい問題からスタート:基礎を固めることが一番の近道!
- 教科書や動画で基本に戻る:授業で聞き逃した部分も丁寧に復習できる。
- 友達や先生に質問する:一人で悩まず、説明してもらうことで理解が深まる。
- 「できる問題ノート」を作る:解けた問題をまとめて、自分の成長を実感する。
モチベーションを上げる工夫
- 苦手科目を「ごほうびタイム」とセットにする(例:数学10分やったらチョコ1つ)。
- 苦手な単元を終えたらチェックマークをつけて達成感を味わう。
- 苦手科目をあえて友達と一緒にやることで、楽しみながら克服できる。
💬 「わからない」を恥ずかしがらないことが第一歩!
小さな成功体験が、やる気につながりますよ。特に、苦手を克服できた瞬間は自分にとって大きな自信になります。その自信が、次の勉強への原動力になるのです。
10. テスト直前の過ごし方【前日・当日の注意点】
焦りは禁物!心を整えることが大事
前日は「もっと勉強しなきゃ!」と焦りがちですが、落ち着いて振り返ることが大切です。ここで新しいことを無理に覚えるよりも、今までの復習や睡眠を優先するほうが点数アップにつながります。むしろ、無理に詰め込みすぎると頭が混乱して逆効果になることもあるんです。
前日の過ごし方
- これまでやったことの確認:重要ポイントをサッと見返す程度でOK。
- 早めに寝る:睡眠不足は集中力低下やケアレスミスの原因に!
- 持ち物チェック:筆記用具、定規、受験票などを前夜のうちに準備。
- 軽いストレッチやお風呂でリラックス:リフレッシュすることで翌朝の目覚めもよくなる。
- 勉強道具を机の上にそろえておく:朝からバタバタしないための工夫。
当日のポイント
- 朝食をしっかり食べる:脳のエネルギー源はブドウ糖。ご飯やパンをしっかり食べよう!
- 深呼吸でリラックス:緊張したら、ゆっくり息を吸って吐く。それだけで心が落ち着く。
- ケアレスミスに注意!:問題文をよく読む、計算の見直しをするなど“確認作業”を怠らないこと。
- 時間配分を意識する:最初から飛ばしすぎず、わからない問題は後回しにする勇気を持とう。
- 試験前の休み時間は暗記カードを軽く見返す程度にして、頭を整理することに集中。
気持ちの持ち方
「完璧じゃなくてもいい」「今の自分にできることをやれば十分」と考えると緊張が和らぎます。大事なのは、自分がこれまで頑張ってきたことを信じることです。
🌞 「準備OK!」という気持ちが、実力を引き出します。
11. 勉強を続けるための“ごほうび”ルール
やる気を持続させる秘訣は「楽しみ」!
勉強ばかりだと、疲れてしまいますよね。 そこで大事なのが「ごほうび」!ただ頑張るだけでは長続きしません。人間の脳は「楽しみ」があるとやる気ホルモンが出やすくなるので、うまく活用すれば勉強が自然と続くんです。
ごほうびの例
- 1時間勉強したら好きなYouTubeを10分
- 単語50個覚えたらおやつタイム
- テストが終わったらお気に入りのゲーム
- 苦手な単元をやり終えたら友達と遊ぶ
- 1週間頑張ったら新しい文房具をゲット
ごほうびをうまく使うコツ
- ごほうびは大きすぎないものを選ぶ(毎回ケーキや高額な物だと逆効果)
- 「やったらすぐ」与えるのが効果的(脳が達成感と結びつけやすい)
- 長期と短期で組み合わせる(毎日の小さなごほうび+テスト後の大きなごほうび)
- 自分の好きなことに結びつける(音楽、ゲーム、マンガなど)
ごほうびルールを守ることが大切
せっかくルールを作っても「今日は特別だからいいや」と守らないと意味がありません。小さな約束を守ることで、自分自身への信頼感もアップします。逆に、しっかりごほうびを楽しむことで「次もまた頑張ろう!」という気持ちにつながります。
🎉 自分で決めたルールなら、続けやすくなりますよ!
楽しくコツコツ勉強する工夫をしましょう。勉強=つらいこと ではなく、**「頑張った分だけ嬉しいことが待っている」**と考えられると、勉強習慣が自然に身についていきますよ!
12. 家族や先生と協力しよう!【一人で悩まない】
勉強の悩みは、誰かに話してみよう
「どうしてもやる気が出ない…」「この問題の意味がわからない…」 そんなとき、一人で抱え込まないことがとても大切です。 誰かに話すだけで気持ちが軽くなったり、思わぬヒントをもらえたりすることもあります。
助けてもらう=ズルじゃない!
- 家族に「見てて!」と声をかける:勉強している姿を見てもらうだけで集中力が上がることも。
- 先生に質問する:わからない部分をすぐに解決することで、効率がグンとアップ!
- 友達と問題を出し合う:お互いに教え合うと理解が深まるし、楽しく続けられる。
協力することで得られるメリット
- 安心感:一人で悩まなくていいと気づくだけで気持ちが楽になる。
- 新しい発見:他の人の考え方や解き方を知ることで、自分の幅が広がる。
- モチベーションアップ:一緒に頑張る仲間がいると、「自分もやろう!」という気持ちになる。
🤝 仲間や大人の力を借りることで、勉強はもっと楽になります。
一緒に乗り越えることで、もっと成長できますよ!そして「助けてもらった経験」が、今度は自分が誰かを助ける力にもなっていきます。
まとめ:今日からできる一歩を踏み出そう!
テスト勉強は「やらなきゃ…」と思えば思うほど、気が重くなってしまいますよね。 でも、ちょっとした工夫や考え方を変えるだけで、勉強はグッと楽しくなります。
今回紹介したコツは、どれも中学生の皆さんがすぐに実践できることばかりです。
✅ 今日からできるアクション
- 明日の予定に「15分だけの勉強タイム」を入れる
- 教科書を1ページだけ音読してみる
- 友達と一緒に一問一答を出し合ってみる
「やる気が出るのを待つ」のではなく、「少しだけやってみる」ことが、やる気につながるんです。
一歩ずつ、自分のペースで進んでいきましょう!
みなさんのテスト勉強がうまくいきますように!📚✨